Joy!!(初回限定盤)(ビビッドオレンジ)(DVD付)/SMAP
今日のスマステはキムタクがゲストでSMAPの50枚目のシングル「JOY」の発売を記念して「決定!国民が選ぶSMAPシングルベスト25」というのをやっておりました。(関係ないですけど「JOY」というタイトルとこのジャケット、達郎ファンとしては心中穏やかではいられません。)
予想を裏切り「世界にひとつだけの花」ではなく「夜空ノムコウ」が1位、3位には「らいおんハート」。
「らいおんハート」の”きみはいつも僕の薬箱さ どんな風に 僕を癒してくれる 笑うそばから ほら その笑顔 泣いたら やっぱりね 涙するんだね あり きたりな恋 どうかしてるかな 君を守るため そのために生まれてきたんだ”という歌詞をあらためて聴きながら何故か思い出したのがジェイムス・テイラーの唄う「ハンディマンHandyman」でした。
JAMES TAYLOR - HANDY MAN
女の子たち 集まりな
僕の言うことよく聞きな
ベイビー 僕は君のための便利屋さん
僕は鉛筆や定規を使うようなやつじゃない
僕は恋の便利屋さん 馬鹿じゃないよ
破れた心を繕うよ ほんとだぜ
破れた心を修繕したいなら
僕にまかせなよ
優しい言葉をささやくよ 友達にも自慢しな
みんな僕を頼ってくるよ
僕が言いたいのは ほらこのことさ
24時間暇なしで
破れた心を繕うよ ほんとだぜ
おいで おいで おいで
さぁ さぁ
おいで おいで おいで
みんな僕のもとへ
こうやって訳してみると「らいおんハート」とはかなり違いますが、まぁ両方とも破れた心を癒す「薬箱」であったり「便利屋」であったりということで・・・。とにかくジャイムス・テイラーの77年発売のアルバム『JT』に収録されたこの曲が大好きでいつか紹介したかったので、無理やりのこじつけと笑ってください。
全米チャートで4位と大ヒットしジェイムスに2度目のグラミー(ベスト・ポップ・ヴォーカル)をもたらした「ハンディマン」はいかにもジャイムスらしい優しさに満ちたナンバーなのですが、実はオリジナルではなくカバー曲です。「ハンディマン」は1955年にジミー・ジョーンズとエルヴィスのヒットでお馴染みのオーティス・ブラックウェルによって作られザ・スパーク・オブ・リズムというドゥワップ・グループによって歌われたものがオリジナルとなります。
The Sparks of Rhythm - Handy Man
聴いてもらったお分かりのとおりこれがジェイムス・テイラーの元歌なのか?と疑いたくなるパッとしないヴァージョンでほとんどヒットしなかったようです。ちなみに作者(作詞?)のジミー・ジョーンズはこのスパークス・オブ・リズムのメンバーであったこともあるようですが、この曲のレコーディングの時にはグループを脱退していたようです。そういった経緯もあってか曲の仕上がりに満足の行かなかったジミーとオーティス・ブラックウェルは59年にあらためて「ハンディマン」をジミー・ジョーンズのソロとして発表します。
Jimmy Jones - Handy Man
ジミーのファルセットをフィーチャーして明るいラヴ・ソング仕上げられたニュー・ヴァージョンは全米2位という大ヒットとなります。”カムカムカム カンカカカン”という歌詞も耳に残るこのノヴェルティっぽいジミーのバージョンもいかにもオールディズという感じで大好きなのですが、「君の友達」のアナザー・ヴァージョンのようなしっとりとしたバラードにしてしまったジェイムスに軍配をあげたくなります。ジェイムスってほんとカバーがお上手なんですよね。
「ハンディマン」のヒットに気を良くしたジミー・ジェーンズは”カムカムカム カンカカカン”のような印象的なファルセットを再びフィチャーしたナンバーを発表します。60年に全米3位となった「グッド・タイミン」で、今度は”テカテカテカテカ”でした。
Jimmy Jones - Good Timin' (STEREO)
この歌、九ちゃんが「すてきなタイミング」というタイトルでカバーしていますね。ファルセット部分含め九ちゃんってほんと歌の上手い歌手ですね。半世紀前の日本でこれだけバタくさく歌えたってのは奇跡的な気がします。
坂本九 すてきなタイミング
話は「ハンディマン」に戻りますが米ウィキを見るとカルチャー・クラブの大ヒット「カーマはカメレオン」は「ハンディマン」のパクりだと言われてるみたいですね。そう言われると「カーマ」を初めて聴いたときにデジャヴを感じたのはそのせいだったのかも知れません(遅だしジャンケンみたいですみません)。
Culture Club - Karma Chameleon
カマカマカマカマ カミリオーンのとこかな・・・。久しぶりに聴きましたがパクり云々は置いといて直球のポップス、いい曲です。当時つきあっていた3コ下のガール・フレンドに聴かされたのを思い出しちゃいました。ハンディマンにはなれなかったけどね。
カムカムカム カムカカーン
PR: 今までにない部屋探しサイト「Nomad.(ノマド)」
波乗り公爵デビュー!
朝から真夏のような陽射しがギラギラ。今日も朝から暑くなりそうです。
こんな日はやっぱりサーフ・ミュージックに限ります。
なんとも既視感じゃないか既聴感のあるサウンドで懐かしい気持ちになりますが、デビューしたばかりのハワイの3人組ザ・デュークス・オブ・サーフThe Dukes Of Surfの「ワイキキ」です。まさにコンテンポラリー・サーフ・ミュージックです。
サーフィン ワ・イ・キ・キ/ビクターエンタテインメント
どこがコンテンポラリーやねん!と思いっきりつっこまれそうですが、こういう音って最近なかなか出会うことがない、それこそ昨年の『神が創りしラジオ』以来かも、ので嬉しくなるんです。
The Dukes of Surfはホノルル(ハワイ)をベースに活動するアロハ・ロックバンド。創設メンバーの3人、JP、Lee、Fish(JPの従兄弟)はハワイ、フロリダ、カリフォルニアと、それぞれ異なる州のビーチの近くで育つ。JPはハワイ州ホノルル出身。LEEはフロリダ州ウェストパームビーチ出身。 FISHはカリフォルニア州サンタクルーズ出身。3人共、ビーチ・ライフスタイル、女の子、そして、サーフィンの黄金期にタイムスリップさせてくれるような音楽を好む。何もかもがビーチで始まった、古き良き時代を思い起こさせてくれるクラシックなサウンドを独自にリフレッシュ。そんな彼らのユニークなサウンドを味わいながら、The Dukes of Surfと新しい思い出を作ってみませんか。
公式サイトより
毎年1月に行わるアメリカン・フットボールのオールスター戦「プロボール」の前夜祭に登場、その模様は30分のTVスペシャルとして放映されています。その映像もアップしておきます。ライヴ映像は1分30秒~Waikiki 7分30秒~Doo-Bee-Doo 12分30秒~Humuhumunukunukuapau'a 18分04秒~Surfer's Paradiseです。
The Dukes of Surf - TV Special
いかがでしょうか、少しは涼しい気分になっていただけましたでしょうか?
なにまだ暑い、ではとっておきの一曲をおまけに。
海のないオハイオ州クリーブランドのインチキ・サーフ・バンド(!?)、ユークリッド・ビーチ・バンドの「クリーブランドに波はない」です。
Euclid Beach Band - There's No Surf In Cleveland
インチキ・サーフ・バンドと書いてしまいましたが仕掛け人はエリック・カルメン、そのへんのことは機会があれば書いてみたいと思います。
スターマン この星の恋

次のクルーからスタートするドラマのようです。最近番宣が流れるようになったのですがタイトルが「スターマン」ということもあってか、もうお気づきですねデビッド・ボウイあの曲が流れているのです。
しかし、TVの前でビールかなんかを呑みながらダラーっとしている時に、いきなりブラウン菅の向こう(ほんとは液晶の向こうなのですが、なんかね)からボウイの声が流れてくるというのは不思議な気持ちになります。ちょっと心臓に悪い気も。
番組のHPを見てもボウイの「スターマン」が主題歌との情報は無いので番宣だけの使用かもしれないですね。
ちなみにドラマ自体は堤幸彦監督で脚本が傑作だった「最後から二番目の恋」や「泣くなはらちゃん」の岡田惠和、主演が広末と「あまちゃん」の種市先輩の福士蒼汰、広末の息子に「とんび」の”おとさん”で泣かせてくれた五十嵐陽向くんと、けっこう期待できそうなドラマです。
英国ロック/ポップの名曲20 1967-1975 #1
今月号のレコード・コレクターズの特集は「英国ロック/ポップの名曲ベスト100 1967-1975」でコピーは”サイケ突入からパンク前夜まで、黄金期にリリースされた必聴シングル100曲はこれだ!!”というものです。
レコード・コレクターズ 2013年 07月号
ベスト20はこんな感じです、とこっそり(笑)書いちゃいます。
1位 ザ・ビートルズ「ストロベリー・フィールズ・フォエヴァー」
2位 プロコル・ハルム「青い影」
3位 ザ・ローリング・ストーンズ「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」
4位 ザ・キンクス「ウォータルー・サンセット」
5位 ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス「紫のけむり」
6位 レッド・ツェッペリン「胸いっぱいの愛を」
7位 Tレックス「ゲット・イット・オン」
8位 ピンク・フロイド「エミリーはプレイ・ガール」
9位 フリー「オールライト・ナウ」
10位 10CC「アイム・ノット・イン・ラヴ」
11位 ザ・ゾンビーズ「ふたりのシーズン」
12位 ロッド・スチュワート「マギー・メイ」
13位 クイーン「ボヘミアン・ラプソディ」
14位 ザ・フー「無法の世界」
15位 ジョン・レノン「イマジン」
16位 デレク&ザ・ドミノス「いとしのレイラ」
17位 ザ・ローリング・ストーンズ「ホンキー・トンク・ウィメン」
18位 ザ・フー「恋のマジック・アイ」
19位 クリーム「サンシャイン・ラヴ」
20位 クイーン「キラー・クイーン」
いや、ちゃうやろデビッド・ボウイはどうしたとかエルトンは、パープルは、クリムゾンは(シングルっすからね)とかいろいろあるでしょうが、気になる方は本屋で立ち読みでもしていただくとして、最近ネタ切れゆえに鳥肌音楽的ベスト20を発表しておきます。
1位 パイロット「マジック」
僕がロックを聴き始めた70年代前半、ビートルズは既に存在せず「第2のビートルズ」と呼ばれるバンドが群雄割拠していました。そんな中で僕が特に好きだったのはアメリカであればクリブランド出身のラズベリーズでありイギリスでは「マジック」を歌ったパイロットでした。とはいえアルバムは高くて買えない中学生からするとパイロットはこの曲と「ジャニアリー」位のほぼ一発屋的なところはあるのですが、たった一曲でも完璧に100%ポップな曲が作れたら、それだけで評価してあげてもいいのではないかと思います。
2位 ポール・マッカートニー「アナザー・デイ」
「第2のビートルズ」と呼ばれるバンドのほとんどは何故かポール・マッカートニー的なメロディアスな曲を得意としていました。では本家はどうであったかというと、僕がロックに目覚めるちょい前に発売されていたのがこの曲で「第2のビートルズ」たちに比べ何ともシンプルな作りなんだけど、だからよけいにメロディの良さが際立つという、流石だ、何て当時は想いませんでしたが今は思います。最後らへんの一人多重コーラスもマル。
3位 エジソン・ライトハウス「恋のほのお」
これは後追いで聴いたのですが、一度聴いたらもう寝ても覚めても忘れられないそんな完璧なメロディです。ブリティッシュ・バブルガムを代表する一曲。作曲はトニー・マコーレイ。以前 トニー・マコ-レイ?トニー・マッコウレイ?トニー・マッコーレイ?というエントリーで特集させていただきましたが、書く曲書く曲すべて「ネ申曲」です。「恋のほのお」っていう邦題もいい。
4位 ギルバート・オサリヴァン「アローン・アゲイン」
ギルバート・オサリバンの場合はソロ歌手なので「第2のビートルズ」というよりは、「第2のポール・マッカートニー」という扱いだったような記憶があります。声も似てますもんね。歌詞は全然分からなかったけれどどこか悲しげなメロディに聴くたびに(40年以上聴いてきた今もなお)胸がキュンとなるなんて・・・
5位 ジョージ・ハリスン「ギヴ・ミー・ラヴ」
この曲も頭のジョージのスライドの音色に胸がキュンキュン(50超えたオッサンが気持ち悪いというなかれ)。めちゃウマという訳ではないんですけど絶妙の音色ですよね。このへん、ビートルズの中でのスタンスとも共通するような気がします。
6位 エルトン・ジョン「クロコダイル・ロック」
70年代の前半っていうのはオールディーズ回帰みたいな気運があって、アメリカだとカーペンターズの『ナウ&ゼン』とか、そこで教えられたのは一言で言えば”音楽の愉しみ”。こういう曲をすりこまれたから現在のオールデイズ趣味みたいなものが出来上がったようなような気がします。
7位 リンゴ・スター「ユア・シックスティーン」
これもオールデイズ風味たっぷりのナンバーっていうか、ジョニー・バーネットのカバーでしたね(笑)。他愛もない歌詞にスットボケたリンゴの歌声、それをからかうようなカズー(ポールでしたよね確か)の音色、ビトルズ時代に培ったキャラクターをソロで最も活用したのがリンゴ・スターでした。それにしても『リンゴ』というアルバム、大人になってあらためて聴き直してこんなに豪華なメンツが奏でる音楽を中学時代になんの気負いもなく「普通」に楽しんで聞けたことに感謝いたしました。
8位 クイーン「炎のロックンロール」
「キラー・クイーン」や「ボヘミアン・ラプソデイ」の方が王道なのでしょうけど・・・。ゼップやパープルやヒープやサバスなんかをちょっと齧っていっぱしのハード・ロックを気取っていた僕にロック仲間のM中くんが「なんか、すごい新人バンドが出てきたぞ」というので放課後、ツレの部屋で「ほんとや、すごいよコレ」と何度も繰り返し聴かせてもらったことを昨日のことのよう思い出します。何とも言えない疾走感があるのですが、多重録音でギミックたっぷりのサウンドが自分の趣味にあっていたのかな、なんてことも今は思ったりします。
9位 ザ・ビートルズ「ユー・ノウ・マイ・ネイム」
歳の離れた兄貴がいてビートルズのアルバムが沢山ある近所のツレの家に休みになれば出かけてビートルズを聴くということをやっていました。「レット・イット・ビー」もアルバムで聴いていたのですが、ある日シングルを眺めているとB面に知らない曲が入っていることに気がつきます。なんだろなコレはと聴いてみて唖然、何コレ本当にビートルズなのか、それ以前にこれもロックなの・・・。
ビートルズが分裂しヨーコが完全なパートナーとなったソロのジョンに欠けていたのは、この何だか分からないけど、そこがジョンらしいと思えるユーモア感だと思います。なんか真面目になった気がするんですよね。
10位 クリスティ「イエロー・リヴァー」
これも後追いですが、日本でもよく売れたみたいですね。ソニー系の70年代コンピには必ず入っていますもんね、これとマッシュ・マッカーンは(笑)。
11-20位はまたの機会に。
英国ロック/ポップの名曲20 1967-1975 #2
前回に引き続き「英国ロック/ポップの名曲20 1967-1975」、11位以下の発表です。
11位 ザ・ビージーズ「マサチューセッツ」
本当をいえば、今の自分の趣味で言えばもう少し下という気もしますが、なにせ自分にとって「はじレコ」なので、あんまり下にするのも・・・。何で67年発売のこのシングルを買ったのかと記憶をたぐってみると中学1年の時に映画「小さな恋のメロディ」がヒットしていて、その挿入歌であったビージーズの「メロディ・フェア」が大ヒットしていて、ご多分に漏れず僕も大好きでシングルを買おうかと思ったのですが、すでに友達が持っていたため(少ない小遣いを有効に使うため)、かぶらないものでビージーズのものが欲しいと町のレコード店のエサ箱を見ていたら「マサチューセッツ」があったということだったと思います。カップリングは英国では次のシングルA面だった「ホリデイ」でとにかくA面B面ひっくりかえして聴きまくりました。なにせ「はじレコ」これ一枚しかもってないわけですから(笑)。
12位 ルベッツ「シュガー・ベイビー・ラヴ」
しまったなぁ。動画を観ていたらこれは12位じゃなくて2位でも良かったかなと悔やんでおります。これも完璧なPOPですね。初めて聴いた時から何故か懐かしい曲と感じたのはなんでだったんだろう。ちょっと考えてみたい課題かもしれません。これとかベスト10に入れた「クロコダイル・ロック」や「ユア・シックスティーン」そしてこの後に出てくる「恋のウーアイ・ドゥー」などキッチュな感覚を持った曲が70年代前半には多かった気がします。このキッチュとグラム・ロックに見られるようなキャンプという感覚はアメリカにはあまり無い英国特有の気質なのかもしれません。
13位 スレイド「カモン・フィール・ザ・ノイズ」
ということでグラム・ロックからスレイドを。グラム・ロックと言えばボウイ、T-REX、モットってあたりが代表格で今も評価高かったりしますが、若い人たちだとスレイドのこと知らないんじゃないでしょうか。外連味たっぷりのキャッチーなパワー・ポップはグラムの中でも最も分かりやすくてもっと評価されていいと思うんですが。日本ではやっぱりルックスがモノを言うということなんですかね。
本国では日本と違いちゃんと評価されているのか、国民的バンドであるオアシスもカバーしています。リアムが歌いだすと会場が大合唱、この歌の人気のほどが分かりますね。
14位 ザ・ローリング・ストーンズ「悲しみのアンジー」
中学時代に僕が住んでいた家は鉄骨が入っていたのでFMがうまく入りませんでした。といっても石川県では当時NHKーFMだけで民放はなくポップスが聴ける番組は少なかったのですが、日曜の夕方6時にやっていた石田豊さんの「リクエスト・コーナー」は全米の最新チャートが聴けるのが魅力で、ラジオを持って電波の悪い家を飛び出し田んぼの真ん中で番組を聴くというのをやっていました。73年の秋に稲刈りの終わった田んぼでスウィッチをひねると流れてきたのが赤丸急上昇中の「悲しみのアンジー」で、一番星が煌めき出す薄暮の空の下で聴くイントロのアコギがなんともムードたっぷりで大人な曲やなぁと思ったことが強く記憶に残っています。
雨が降ったり冬になると外でラジオが聴けず困りものでしたが、ある日アンテナと鉄骨を銅線でつないでみるとバッチリ入ることに気づき部屋でゆっくりと聴けるようになりました、めでたしめでたし。
15位 バッド・カンパニー「キャント・ゲット・イナフ」
これも中学時代のツレのM中くんの家で初めて聴いて、アルバムを買ったのでした。ただアルバムについては「キャント・ゲット・イナフ」以外の曲は中学生には地味というか、良さが分からず誰かに売っぱらっちゃった。サイモン・カークのドラムのイントロがとにかくカッコよいのですが、何よりもポール・ロジャースの歌。もう40年近くいろんなボーカリスト聴いてきましたが、ポールほど上手い人は中々お目にかかりません。ということで遡ってフリーを聴くことになるのですが、最初に買ったのが代表曲がいっぱい聴けそうということで『フリー・ライヴ』。完全にノック・アウトされました。ポール・ロジャース、ポール・コゾフ、アンディ・フレイザー、サイモン・カーク平均年齢20歳前でこの演奏、奇蹟のバンドでした。
今回はちょっと横道にそれたりしていろんな動画をサーフィンしてるうちに眠くなってしまいましたので、残り5曲はまた明日以降に。
雨はこわれたピアノさ 舗道の鍵盤叩くよ
バチェラー・ガール 稲垣潤一____________ 大滝詠一
-
雨はこわれたピアノさ
心は乱れた メロディー
My Bachelor Girl
向かいあう傘の中
君は横に首を振った
これ以上逢えない と
予想通りの辛い答えさ
すれ違うバスが 水たまりはねて
雨はこわれたピアノさ
舗道の鍵盤叩くよ
My Bachelor Girl
台風の影響もあってか昨日は一日中雨でした。関西地区はかなり前に梅雨入りしていましたが、ずっと空梅雨でようやく梅雨らしくなってきました、雨は基本的には嫌ですけどね。ということで今日は松本隆・大瀧詠一コンビによる「雨」の名曲「バチェラー・ガール」でスタートさせていただきました。
元々は84年の大滝師匠の『EACH TIME』用に用意されましたが、アルバムには収録されず、翌年稲垣潤一にシングル用の曲として提供されます。そして7月1日に発売されオリコン21位のスマッシュ・ヒットを記録します。その後師匠本人も11月1日に「フィヨルドの少女」との両A面扱いでオリコン31位と、こちらもスマッシュ・ヒットしています。この31位というのが当時の大瀧師匠にとってのオリコン最高位みたいです、今やCMなんかで引っ張りだこで誰もが耳にしたことがあるだろう「君は天然色」もシングルとしては36位が最高位ということでちょっと意外な気がします。ただそれ以前から師匠を聴いていた人からすると、師匠のシングルがオリコンのチャートに入ること自体が意外なことでしたが(笑)。
ちなみにこのシングルはナイアガラ最後のアナログ・シングルでした。
「バチェラー・ガール」はモータウンの影響、特にザ・シュープリームス(ザ・スプリームス)の大ヒット曲「ストップ・イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ」思い出させるメロディとなっています。
The Supremes - Stop In The Name Of Love
師匠にしては偉いメジャーな曲から引用しているなぁと思います。ところが、今朝、次のエントリのネタ用にCD棚でザ・ジャムを探していたら近くの「H」のコーナーにあったブライアン・ハイランドBrian HylandのCDに目がとまり十数年ぶり位に聴いていたところ、ある曲のサビの部分で「あぁコレだったのか」と膝をうってしまいました。曲はブライアン・ハイランドの69年のシングル「ステイ・アンド・ラヴ・ミー・オール・サマーStay And Love Me All Summer」という全米チャートで82位というマイナー・ヒットです。
Brian Hyland - Stay And Love Me All Summer
どうして 夏の間 側にいて そして 僕を愛してくれないの
バケーションにも行かないでくれ
別れたままで暮らすのはたえられない
街にいてくれ ガール 僕の側に ガール 君が必要なんだ
どうして 夏の間 側にいて そして 僕を愛してくれないの
どうして 夏の間 側にいて そして 僕を愛してくれないの
去年も僕らは離れ離れ
9月がくるまで 落ち込んでいた
君がいないと 空は灰色に曇るんだ
どうして 夏の間 側にいて そして 僕を愛してくれないの
どうして 夏の間 側にいて そして 僕を愛してくれないの
わが家にまさる ところなし って言うじゃないか
なのに 僕と来たら 独りぼっち これがわが家なのかい
みじめだ なんてみじめなんだ
この街で夏を過ごさないかい
暖かい夜を分かち合い 明るい日差しも分かち合う 君が欲しいんだ
どうして 夏の間 側にいて そして 僕を愛してくれないの
どうして 夏の間 側にいて そして 僕を愛してくれないの
ブライアン・ハイランドはオールデイズ・ファンならみなさんご存知の全米NO1ヒット「ビキニ・スタイルのお嬢さんItsy Btisy Teeniee Weenee Yellow Polka-Dot Bikini」で有名な人でビートルズ上陸後も地道に歌い続け、この曲の翌年の70年にはデル・シャノンのプロデュースの下にインプレッションズの「ジプシー・ウーマン」をカバーし全米3位という大ヒットをものにしています。作詞作曲はエルヴィスやブリル・ビルディング時代から活動をスタートし70年代は主に映画音楽の舞台で活躍しモーリン・マクガバンの歌った「モーニング・アフターMorning After」(ポセイドン・アドベンチャー挿入歌)や同じくモーリンが歌った「タワーリング・インフェルノ愛のテーマWe May Never Love Like This Again」でオスカーを獲得したアル・カシャAl Kashaとジョエル・ハーシェンJoel Hirschonという名コンビ。
お聴きいただけば分かるかと思いますが”Why can't you stay and love me all summer?”のところのメロディをほとんどそのままに”雨はこわれたピアノさ”と歌っています。
さてここからは、またいつもの勝手な妄想を展開させていただきます。何故大瀧師匠はサビの部分で一般的にはほとんど知られていないだろうブライアン・ハイランドの曲を引用したのか?
それは、「バチェラー・ガール」の松本隆による歌詞のがきっかけだったのではないか。「バチェラー・ガール」では”すれ違うバスが 水たまりはねて”とあるように、恐らくはバス停まで恋人を送った男が傘の下で舗道を叩く”壊れたピアノ”のような雨音によってかき消されそうな恋人からの別れの言葉を聞くという歌です。「雨」「バス停」「傘」「別れ」という要素から思い出すのは「雨」「バス停」「傘」「出会い」というまるっきり反対の内容の歌、そうザ・ホリーズThe Holliesの「バス・ストップBus Stop」です。
Hollies - Bus Stop - 1967 (live)
バス停 雨の日 彼女がいる
傘に入りませんか
バス・ストップ バスは去り 彼女は横に
恋が始まる 傘の下
「バス・ストップ」を思い出した師匠は最初に”ストップ”つながりでザ・シュープリームスの「ストップ・イn・ザ・ネイム・オブ・ラヴ」を曲のベースにすることを考えます。
それとは別に、2番の
All that summer we enjoyed it
Wind and rain and shine
That umbrella, we employed it
By August, she was mine
夏の間 僕らは楽しんだ
雨や風や晴れ どんな日も
あの傘 そいつのおかげで
8月には 彼女は僕のもの
という歌詞の夏の間、いつも一緒に過ごし恋が芽生えていくという物語から、「バチェラー・ガール」と「バス・ストップ」のような正反対の物語、つきあっている恋人が夏になると自分のもとを離れアバンチュールを愉しみ途方にくれる男を歌った「ステイ・アンド・ラヴ・ミー・オール・サマー」を思い出した。なんていうことが師匠の頭の中で数珠繋ぎになったのではないか、なんて考えるのですが、はたして・・・・。
ただ「バチェラー・ガール」は師匠のいつもの無理な譜割が無い歌なので、ひょっとしたら詞先ではなくて曲先で作られた可能性は高いような気もして、そうなると僕の考えは全くの妄想となりますね。
おまけ
ナイアガラからみで杉真理の「バカンスはいつも雨」、ちえみちゃんのCMバージョンでどうぞ。
PR: 豪華夏の特別号受付中★今が入会のチャンス!/ベネッセ
I WANT A NEW DRUG

先日車で神戸を走っていたら「RECORDS」の看板が目に入りました。よく見ると看板の右上にはAEONのロゴ、”へぇ今どき新しいレコード店か、それもイオン系列?”。昨年のCDの売上は前年比で10%近く伸びているとはいえ、基本的には右肩下がりの衰退産業のレコード業界に今更イオンが手をだすとは。
気になって駐車場に車を止め近くでお店を覗くとコンビニ×ドラッグストアの文字。
”??”
もう一度よく看板を見ると「RECORDS」はなく「RECODS」。「R」の文字がありませんでした。
家に帰って検索してみると東海地区で「HAC」というドラッグストアを展開するCFSコーポレーションと関西地区で同じくドラッグストア「ウェルシア」を展開するタキヤ㈱そして「ミニストップ」が融合した㈱れこっずが経営する新業態のお店のようです。
いつもレコードのことばかり考えているから、こういう間違いをしてしまうんでしょうね。お恥ずかしい・・・。
THE RECORDS / STARRY EYES
カーラジオからスロー・バラード
最近は忙しさにかまけてすっかり週一の更新になっていますね。ふと気がつくと昨日7月4日はアメリカ独立記念日とともにこのブログの誕生日でした。2005年スタートということで丸8年で9年目に突入ということで心もあらたにと行きたいところですが、本日も小ネタで。
先ずは3週間ほど前にご紹介したザ・デュークス・オブ・サーフというモロ60年代カリフォルニアな、つまりはザ・ビーチ・ボーイズなハワイの三人組の「ワイキキ」ですが、最近FM802で毎日のようにオン・エアされております。
The Dukes of Surf - "Waikiki" (Official Music Video)
DJが”いやぁ、朝から気温がどんどん上昇している大阪の夏の暑さをふっとばすような爽やかな夏の音楽です”ってなことを言いながらオン・エアされます。確かにこの曲をを聴くと僕も”あぁ夏だなぁ”と思いますし、仕事の関係で若い人にこの曲を聴いてもらう時も”いいですね、コレ、夏って感じするっす”みたいな感想が口をついて出てきます。
チャック・ベリー的な疾走感のあるギターR&Rにフォー・フレッシュメンのようなハーモニーが乗っかり、特に高音のファルセット・ボーカルが縦横無尽に歌いまくるという音楽が「夏の歌」になったのは言うまでもなくザ・ビーチ・ボーイズのおかげです。
初期のザ・ビーチ・ボーイズを特徴づける上記のようなサウンドを考えたのはブライアン・ウィルソンその人で実践したのは彼のバンド、ザ・ビーチ・ボーイズでした。もう少し詳しく言うと新しいサウンドを試してみたいと考えていたブライアンに生粋のサーファーであった弟デニスが”兄貴、サーフィンをテーマにした歌を作ってよ”とたまたま頼み込んだから、新しいサウンドと夏を代表するスポーツであり文化であるサーフィンが結びつくことになります。おまけに元々は流行していたシャツからとった「ペンデルトーンズ」というバンド名だったのにインディーズ・レコードから「サーフィン」でデビューする際にそのレコード会社の社長の”サーフィンの歌ならやっぱビーチ・ボーイズだろ”という勝手な判断によりバンド名は「ザ・ビーチ・ボーイズ」という実も蓋もないダサい名前に変えられてしまいます。
こうしてブライアンの考え出した新しいサウンドは人々の間に最も「夏」を感じさせる音楽として広まり、今回の「ワイキキ」のような音を聴くと「夏だ!!」と思うようになったということなんだと思います。もし、始まりの段階でデニスが野球少年で”兄貴、野球の歌つくってよ”と言っていたら、もしかしたらザ・ビーチ・ボーイズではなくザ・ボール・ボーイズとかいう名前(これでもBB5になりますね)でデビューし「サーフィン・ミュージック」ではなく「ベース・ボール・ミュージック」なるジャンルが生まれていたかもしれないなんて思いながら独りほくそ笑んでいます。
THE BEACH BOYS /HAWAII
ザ・ビーチ・ボーイズの「サーフィン・ミュージック」のスタイルですが、チャック・ベリーにフォー・フレッシュ・メンというのはデビュー曲「サーフィン」の時からあったのですが、ブライアンが自分の声を”女の子みたいでマッチョじゃない”と思っていたようで『サーフィン・サファリ』『サーフィンUSA』のころにはブライアンのファルセットはほとんど登場していません(「ファーマーズ・ドーター」でちょこっとって感じ)。3作目の『サーファー・ガール』の中の「キャッチ・ア・ウェイヴ」や上にリンクした「ハワイ」でブライアンのファルセットが大活躍してこれぞ「ザ・ビーチ・ボーイズ」というサウンドが完成することとなります。
ということもあってハワイ出身のザ・デュークス・オブ・サーフが「ワイキキ」というタイトルの曲でモロにザ・ビーチ・ボーイズしてしまうというのは当然といえば当然という気がいたします(笑)。
ビーチつながりでこれから来そうなバンドをついでに紹介しておきます。その名もザ・ビーチ・デイ、60年代カリフォルニアのガレージ・ロック臭がぷんぷんする男女3人組です。
さて802で最近よくかかっていると言えば、せっちゃんの「カーラジオ」という曲です。
斉藤和義/カーラジオ
斉藤和義 - カーラジオ (FM音源) 投稿者 OsakaTarouOsaka
ケータイばっかいじってないで
ちょっとこの曲を聴いてごらんよ
カーラジオからガッタガッタガタガッタ
あの人が叫んでいる
誰かのナイス・リクエスト
DJ グッド・セレクト
どうして 今でもこんな風に
胸にズンズンくるんだろう
なぁ お前はどう思う
お前はどう思う
あぁ そうだな世界中
ロックン・ロールが足りないのかな
オーイエー オーイエー
そのとおり それでいい
真っ暗な森で転んでも
明日の鍵をなくしても
そのまま まっすぐ行けばいい
お前なら 分かってるんだろ
せっちゃんらしいギター・オリエンテッド・ロック、歌詞で歌われるカーラジオで叫んでる「あの人」はもちろん「あの人」ですね。
トランジスタ・ラジオ / RCサクセション
「カーラジオ」はFM NORTH WAVE(北海道)、J-WAVE(東京)、ZIP-FM(名古屋)、FM802(大阪)、cross fm(福岡)によるJFL(JAPAN FM LEAGUE) が、2013年10月に結成20周年を迎えるということで同じくデビュー20周年の斉藤和義にアニバーサリー・ソングを依頼し出来上がったナンバーだとのこと。
当然のことながらテーマは「ラジオ愛」なわけで、そこから斉藤和義が連想したのは実際に自分もラジオで聴いて夢中になった「ラジオ愛」に溢れた「トランジスタ・ラジオ」であったり、市営グラウンドの駐車場に停めた車のカーラジオ(タイトルはここからでしょうね)からスローバラードが流れる「スロー・バラード」といったRCサクセションの曲たちで忌野清志郎の叫びだったのでしょう。ラジオ愛というよりはRC愛にあふれる曲なのかもしれないですね。
RCサクセション/スロー・バラード
涙がでるな・・・
サーフィン ワ・イ・キ・キ/デュークス・オブ・サーフ
Trip Trap Attack/Beach Day
ゴールデン☆ベスト RCサクセション/RCサクセション
きみのママならきっと知ってるよ

YOUR MOTHER SHOULD KNOW ⇒ 視聴はこちらから
さぁみんな立ち上がり踊ろう
お母さんが生まれる前にヒットした歌さ
かなり歳はとってしまってるけど
お母さんならきっと知ってるよ 君のお母さんならきっと
も一度 歌おう
さぁみんな立ち上がり踊ろう
お母さんが生まれる前にヒットした歌さ
かなり歳はとってしまってるけど
お母さんならきっと知ってるよ 君のお母さんならきっと
高鳴る心で歌っておくれ
お母さんが生まれる前にヒットした歌を
かなり歳はとってしまってるけど
お母さんならきっと知ってるよ 君のお母さんならきっと
お母さんならきっと知ってるよ 君のお母さんならきっと
も一度 歌おう
かなり歳はとってしまってるけど
お母さんならきっと知ってるよ 君のお母さんならきっと
Dear Angie ~あなたは負けない/それぞれの夜 (通常盤)/竹内まりや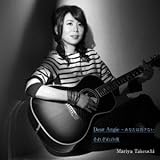
7月3日に発売された竹内まりやのニューシングル「Dear Angie~あなたは負けない」です。このシングル初回限定版にはまりや初となるPVを収めたDVDが付いているのが話題となっています。個人的にはまりやの映像よりビートルズの「ユア・マザー・シュッド・ノウ」のカバーが収録されていることに興奮してしまいました。さらに言えばDVD抜きの通常盤にはさらにもう一曲ビートルズのカバー「ジス・ボーイ」が収録されていて、結局2曲のビートルズ・カバーに惹かれて通常盤を手に入れました。
実はこのカバー山下達郎のサンディ・ソング・ブックのリスナーであればご存知のように夏休みと年末恒例のプログラム「夫婦放談」用に2009年に杉真理、松尾清憲率いるBOXをバックにスタジオで吹き込んだものです。その際今回収録の「ユア・マザー・シュッド・ノウYour Mother Should Know」「ジス・ボーイ(こいつ)This Boy」以外に「素敵なダンスI'm Happy Just To Dance With You」「テル・ミー・ホワイTell Me Why」という計4曲が録音されています。今回はファンからのリクエストに応えそのうちの2曲をCD化したのですが、残りの2曲もぜひ次のシングルなどでCD化していただきたいと思います。
まりやはRCA時代にもビートルズの「アスク・ミー・ホワイAsk Me Why」を録音したことがあるのですが、上の4曲を含め選曲が通好みというか、本当にビートルズが好きなんだろうなぁというのが伝わってきます。
事務所が権利関係に厳しいこともあって2曲のカバーの動画が見つからず試聴いただけないのですが、両曲とも変にいじらず原曲に忠実なカバーで非常に好感がもてるカバーになっています。杉真理、松尾清憲という日本を代表するビートルズ・フォロワーを擁するBOXがバックですからね、本家に勝てるアレンジなんて無いということが判った上でのカバーというよりコピーなのでしょう。
BOX - TOKYO WOMAN
「ユア・マザー・シュッド・ノウ」に話を戻します。お聴きいただければすぐ分かるようにこの歌はポール・マッカートニーによって作られています。自らの発案でTV番組「マジカル・ミステリー・ツアー」の撮影を行なっていたポールはラストの大きな階段からタキシードを着たザ・ビートルズが降りてくるシーンのための新曲が必要となりお得意のミュージック・ホール的な美しいメロディを大慌てでひねり出します。歌詞については、旧いヒット曲だけど君のママだったら知ってると思うよというサビの繰り返しの多い他愛もないもので、よっぽど時間がなかったのか、ジョンの手助けがなかったのかと勘ぐっりたくなります。
ところで、歌詞に歌われている”お母さんが生まれる前にヒットした歌”というのはどんな曲なんでしょうね。曲のタイトルは舞台劇「蜜の味」の脚本の中から引用しているということなのでひょっとするとザ・ビートルズもカバーした「蜜の味」なのでしょうか。ただ初演が58年ということで少々新しすぎる気もします。
まぁいずれにせよポールの好きなミュージック・ホール的な楽曲だったんじゃないかと思われます。まりやが唄う「ユア・マザー・シュッド・ノウ」を聴いているとポールが歌ってから50年近くの月日が流れていることもあり、今や「ユア・マザー・シュッド・ノウ」それ自体が”お母さんが生まれる前にヒットした歌”の一曲になっているとも言えると思います。本来はオールデイズを歌ったはずなのに、その曲自体がオールデイズになってしまう、例えばカーペンターズの「イエスタデイ・ワンス・モア」なんかも同じなのですが、入れ子のような構造というか・・・。作った本人もいつかこんな日がくるとは思わなかったでしょうね。
最近のライヴではポールがこの曲を取り上げることもあるようですが、どんな気持ちで歌っているのでしょうか。
PS.
エントリを書くため「ユア・マザー・シュッド・ノウ」について調べていると、この曲はブライアン・エプスタインが最後に見たザ・ビートルズの演奏だったみたいですね。本来であればアビー・ロード・スタジオで録音が行われるはずでしたが、スケジュールがいっぱいのため1967/8/23のセッションは外部のチャペル・レコーディング・スタジオで行われています。事前の連絡もなくふらりとスタジオに現れたブライアンはスタジオの後ろで無言のまま演奏に聴き入っていたようです。ザ・ビートルズのライヴ活動の休止により自分の存在感が小さくなったと思っていたブライアンはこの懐かしい昔の曲をもう一度歌いみんなで踊ろうと歌われる歌をどんな想いで聴いていたのか?ブライアンは4日後の8/27アスピリンの過剰摂取によって事故死(自殺?)しています。
マジカル・ミステリー・ツアー/ザ・ビートルズ
マイティ・ローズ/BOX
Don't count your chickens before they're hatched
英国ロック/ポップの名曲20 1967-1975 #3
本文に入る前にお断りを。
最近YOUTUBEなど動画サイトでの権利保護が厳しくなったのか、以前は簡単にブログに埋め込みができた動画が貼り付けできなくなり、アメーバー用のコードに変換してから埋め込むようになりました。この変換の際に著作権者のチェックが入るようになっているのか、埋め込んだ動画はブログ上では再生できず、「この動画には○○○さんのコンテンツが含まれており、特定のサイトの再生が制限されています。」という注意書きが画面にあらわれます。そしてそのコメントの下に「You Tubeで見る」というリンクが貼られており、そこからYOUTUBEにとんで初めて視聴ができるという具合です。動画を見たい方はご面倒でも手順にしたがいYOUTUBEでごらんいただくようにお願いいたします。
では間がかなりあきましたが英国ポップ/ロックの名曲20の16位からです。
16位 バッド・フィンガー「嵐の恋」
「デイ・アフター・デイ」とどっちにしようか迷ったのですが・・・。バッド・フィンガーが活躍していた時代にはまだ「パワー・ポップ」といった言葉は無かったのですが、まさにそのお手本のようなサウンドです。
後追い世代からするとアップル所属でビートルズの弟分として華々しく活動をしていたように思ってしまうのですが、契約時点ではバッド・フィンガーではなくアイヴィーズであり、なかなかレコードが出してもらえなかったり。バッド・フィンガーでヒットを出し始めてからもアップルのゴタゴタのせいで正当に扱われていないと思いワーナーに好条件で移籍のハズが実際はアップルの契約のほうがアーチストには有利だったことが後に判明。おまけにワーナーからのアドヴァンスをマネジャーが不正に着服し後に訴訟問題に発展し小売店からレコードが回収されたりゴタゴタ続き。ヒット曲はあるもののメンバーは常に極貧状態にあったようで、バンドの顔であったピート・ハムも一時的に脱退をしたりと精神的に不安定になり最終的に身重の恋人を残し首吊り自殺。なんとも不幸な運命を辿ったバンドでした。
ビートルズ帝国アップルの真実/ステファン・グラナドス
アップル・レコードについてはバッド・フィンガーのようなビートリーなバンドから、メアリー・ホプキン、ビリー・プレストン、ドリス・トロイといったポップ・フィールドだけでなくサージェント・ペパーズのモデルのようなブラス・バンド、ブラック・ダイク・ミルズ・バンドや新進気鋭の前衛音楽家ジョン・タヴナー、MJQ、ラヴィ・シャンカール、ヨーコ・オノと、とにかくある意味無節操とも言えるリーリースは、売上を最優先にするメジャーのレコード会社にはできないもので、インディーズとしての理想と可能性を示したという意味では高く評価されてしかるべきと思います。
ただ残念なのはザ・ビートルズの理想を実現するようなレーベルではありましたが、自分たちもレコーディング・アーチストであるために、所属アーチストのレコーディングに積極的に参加することができず、4人の中ではジョージがいちばん積極的だったようですが、なかなか満足のいくレコーディングやプロモーションができなかったこととポールとの対抗意識からジョンが経営責任者としてアップルに呼び込んだアラン・クラインが唯一採算がとれていたレコード部門にまで事あるごとに口をはさんできたことで、結果的にアップル・レコードも崩壊してしまいます。
ところで、アップルの契約候補の名前の中にハリー・ニルソンがいるのは当然なのですが、イエス(ピート・アッシャーのお気に入り)やクイーン(前身のスマイル)の名前があるのは意外でした。ほんと幅広くアンテナをはっていたと言えるんじゃないでしょうか。
YES/EVERY LITTLE THING
イエスによる「エヴリ・リトル・シング」のカバーもそうしたアップルとの関係性の名残なのでしょうか。
17位 レッド・ツェッペリン「胸いっぱいの愛を」
中学に入り洋楽を聴き始めたのですが、最初聴いていたのはサイモンとガーファンクル(解散したけどラジオでよくかかっていた)やカーペンターズ、ミッシェル・ポルナレフ、エルトン・ジョン、この人たちラジオでかかる3巨頭という感じでした、そしてもちろんビートルズといったところがメインでした。どっちかといえばポップスよりなものを聴いていた(40年経った今もそうですが)のですが、何度か登場してるロック好きのM中に聴かされたレッド・ツェッペリンのアルバム、確か1stでした、に”じぇじぇじぇ”となり、慌てて買ったのがシングル「胸いっぱいの愛を/リヴィング・ラヴィング・メイド」でした。
僕がこのシングルを買ったのが発売後3年ほど経った頃だったので、ジャケの安っぽさからベスト・カップリングの再発ものかと思っていたのですが、最初からこのジャケ、この組み合わせだったんですね。それにしても中央上部にある「Mark45」っていうのは何なんでしょね。
このシングル買った後に、駅裏の三洋バラチェーンの電気屋さんの店の片隅に仕方なしに置かれていた50枚ほどのLPの中に『レッド・ツェッペリン1』があるのを見つけて、なけなしの小遣いをはたいて買ったことがありました。家に帰ってレコードを聴こうとするとツレのM中の家にあったジャケと違って、見開きのジャケになっているし、裏ジャケの4人の写真のメンバー紹介も名前が間違っているという酷いもので、なんじゃこりゃパチもんかと思ってしまった僕は数回聴いただけで、次のLP購入のための軍資金にするために売り払ったか、友だちとトレードしたか、いずれにせよ1ヶ月ほどで手放してしまいます。
今思えばあれは日本ポリグラムから初めて日本発売されたツェッペリンのLP『レッド・ツェッペリン登場』だったんですね。ツェッペリンの発売元アトランティックの日本での契約がポリグラムから新興のワーナー・パイオニアに移ったため短期間で廃盤になっていて、くだんのバラチェーンのお店は廃盤時にメーカーに返し忘れてデッド在庫になっていたということだと思われます。
先日、「題名のない音楽会」でROLLY、野村義男、佐野史郎をゲストに招いてジミー・ペイジの凄さが語られる題して「なんたってジミー・ペイジ」(佐渡裕さんやりますね)というのをやっていたのですが、その中で佐野史郎がお宝として『レッド・ツェッペリン登場』を持ってきていて、あのROLLYですら”噂では聞いていたけど現物は初めて”というくらいですから、かなりレアなものになっているのでしょうか。
それにしても廃盤になってからすでに2年以上は経過しており、店の片隅とはいえ僕が買うまで誰も気づかなかったというのが不思議な気がしてしまいます。ただ、そういうのはコレクターズ・アイテムやレア・アイテムをありがたがる風潮が定着した今の視点ではそう思うといえるのではと思います。正直当時の思いとしてはM中が持っているシングル・スリーヴで輸入盤と同じジャケが本物で、日本ポリグラムの見開きで、その見開き部分に例えばメンバーの写真なんてのがあればそれも有りでしょうが、日本語の解説が印刷されていて、裏ジャケには前述のように間違ったメンバー名が書かれ、収録曲もカタカナで書かれている、どう考えてもダサいパチもんにしか思えませんでした。
なんか、ランキングと関係ない話になってしまいました。当時ポップスしか聴いていなかった僕にとっては「胸いっぱいの愛を」みたいな音楽こそ「ロック」なんだと思わせるに十分のかっこ良さでした。まぁ今思えば狭義の「ロック」ではあるのですが、カタルシスを感じさせてくれるものが欲しかったんでしょうね、中学生ですから。
いろいろ横道にそれちゃったので、今回は2曲のみ、残りは3曲・・・・
胸いっぱいの愛を
前回のエントリで上のようにワーナー・パイオニオから発売された「胸いっぱいの愛を」について書かせていただいたところデビュー当時からリアル・タイムでツェッペリン聴いていたデューク中島先輩から、このシングルが再発ものであること、Mark45という共通ジャケで他にもいっぱいでていたことをコメントでいただきました。
僕の方でも少し調べてみたので、前回の補足として書かせていただきます。
レッド・ツェッペリンのデビュー当時、発売元のアトランティック・レコード及びアトランティックを傘下に収めていたワーナー・セブン・アーツ(現ワーナー・ミュージック)の日本での販売権は日本グラモフォン(現ユニヴァーサル・ミュージック)が持っていました。そのため「胸いっぱいの愛を」の日本での最初のシングルは日本グラモフォンからDT-1139の品番で1970年に発売されています。

デューク中島先輩のコメにもあるように断然こちらの方がかっこいいジャケです。面白いのはB面曲が「リヴィング・ラヴィング・メイド」ではなく「サンキュー」となっていることです。調べてみると前年にアメリカで発売された「Whole Lotta Love」のシングルのB面曲は「Living Loving Maid (She's Just a Woman)」で僕の持っていたワーナーのMark45盤は米盤に準拠していたことになります。本国イギリスはどうだったのかと調べましたがゼップの場合本人たちの意向でイギリスではシングルを発売していないということのようで米盤がオリジナル・シングルということになるようです。
では「リヴィング・ラヴィング・メイド」はどこへいったのか?ちゃっかり「胸いっぱいの愛を」の次のシングルとして「ブリング・イット・オン」とのカップリングでDT1146の品番で発売されています。

確かにアルバムの中では最もキャッチーな曲であるし(ギターのリフの部分とかラジオのジングルでも使われていたような記憶が)、シングルのB面にしてしまうのは勿体ないからもう一枚シングル作っちゃえというのも分かる気がします。このへんの仕掛けは当時担当アトランティックのディレクターだった折田育造さんによるものでしょうか。
日本グラモフォンからのシングルはもう2枚あって一枚は69年のデビュー・シングル「グッド・タイムス・バッド・タイムス/コミュニケーション・ブレイクダウン」でDT1105の品番で発売されています。

これこそ、シングル2枚に分けてもいいような名曲のカップリングなのですが、元ヤードバーズのジミー・ペイジ率いるバンドとはいえ日本じゃ売れるかどうかも分からんし、もったいないけど出しちゃえということだったのか。
-
もちろんこのシングルもワーナーのMark45シリーズで発売されています。カップリングはそのままでP2576Aという品番でした。「胸いっぱいの愛を」がP2550Aという品番ですが、番号からすれば「胸いっぱいの愛を」の方が先に出たことになるのですが、再発シリーズとして一気に何十枚も出ていた可能性もあるようですので、そのへんのところは不明ではあります。

そして日本グラモフォンからのラスト・シングルとなったのが3rdアルバムからのカットの「移民の歌/アウト・オン・ザ・タイルス」で品番はDT1180でした。
 -
-日本ではブルーザー・ブローディの入場テーマとして知られている曲でTVでも乱闘シーンなんかのBGMにひんぱんに使われ、本来とは違ったイメージがこびりついてしまった曲といえるかもしれません。この曲ももちろんワーナーから再発されていますがMark45ではなく通常のシングルとしてリリースされたようです。

米ワーナー・グループとオーディオ・メーカーであるパイオニア、そして渡辺プロの共同出資でレコード会社ワーナー・パイオニアが設立されたのが1970年の11月11日となっています。アメリカでの「Immigrant Song/Hey Hey What Can I Do」の発売が11月5日となっていますから、日本グラモフォン盤の「移民の歌」は発売即生産中止だったのではと思われます(相当レアだったりして)。そして、すぐにワーナー盤の「移民の歌」が発売されることとなるのですが、ユザーにとっては再発というよりはほとんど新譜としてとらえていたんじゃないでしょうか。品番もP1007Aと非常に若い(1001からのスタートでしょうから)番号ですし70年の11月後半か12月に発売だったのでしょう。
グラモフォン盤では差し替えられていたB面曲もワーナー盤はオリジナルの米国盤に準拠したカップリングに戻されているのも興味深い気がします。会社内のいちレーベルではなく外資が半分入った、つまりは本国のワーナー・グループ直結の会社からの発売なので、原則としてオリジナルの仕様に準拠という方針になったのでしょうね。ですから1stアルバムもグラモフォンの見開きジャケのような日本でアレンジされたものではなくオリジナル準拠のものになったということだと思います。ワーナーだけではなくEMIやCBSやポリグラムといった外資による合弁会社が70年前後に登場していて、洋楽のレコードはどんどんオリジナル準拠の仕様になっていきます。
おそらくは60年代に比べればいろんな情報がダイレクトに入るようになり、例えばアルバムの発売なんかも1ヶ月どころか数ヶ月遅れも当たり前みたいな状況から時間差もなくなったりと良いことはいっぱいあったのでしょうが、情報の少なさを知恵を絞って日本のマーケット向きに加工していた時代の「面白さ」みたいなのはどんどん失われていったようにも思います。
最後に、Mark45について、デューク中島先輩がワーナーの社員の方に確認いただいてコメントをくださったので引用させていただきます。
>発足当時のワーナーパイオニアに勤めて居られた方に電話で聞きましたら「ネーミングの由来は、覚えてないなあ。旧譜の再発で、いっぺんに200種類とか出したら 小売店も買いにくいだろうから 毎月小出しに発売して、専用のボックスを付けたり 最初は、売ってもらう為に 支払いを1ヶ月、2ヶ月猶予とか やってたってのは、覚えてますが…」と言われてました。私の想像では、MARKには「有名」の意味も有りますから 「有名なシングル盤」のつもりでしょうかね? 折田育造氏あたりに聞いたら わかるのかもしれませんが。
なるほど、レーベル移行に伴い旧譜のシングルをベスト・カップリングで再発売したシリーズということだったんですね。品番から見ると恐らくはP2501から始まっているシリーズみたいなのですが、ちなみにP2501はピーター・ポール&マリーの「レモン・トゥリー/ハンマーもったら」でした。

当時のワーナー・グループではPPMが最もプライオリティが高いアーチストだったということでしょうか。ちなみに正式な品番はP2501Wと最後に「W」が付きます。この「W」はワーナー・ブラザースのWです。「胸いっぱいの愛を」はP2550Aと「A」がつきますが、この「A」は、お分かりですねアトランティックのAです。他にもP2522Rと「R」のつくものもあります。ワーナーで「R」、そうですリプリーズです。P2522Rはリプリーズ社長のこんなシングルです。

アトランティックものではP2578Aでこんなシングルもありました。「青い眼のジュディ/ロング・タイム・ゴーン」です。

Wikiで見るとシングル・バージョンは4:35となっていて、オリジナルのアルバム・バージョンより3分近く短いのですが、これってCD化されてましたっけ。YOUTUBEで音源探しましたがシングル・バージョンはみつかりませんでした。3分も短いとかなり印象が違うのでしょうね。
英国ロック/ポップの名曲ベスト20 1967-1975 その4
「胸いっぱいの愛を」で横道にそれてしまって、3曲残したままになっていた「英国ロック/ポップの名曲ベスト20 1967-1975」の続きです。サラっと行きます。
18位 ポール・マッカートニー&ウィングス「マイ・ラヴ」
以前に書いた「いつもと同じあたらしい一日が始まる」で触れたようにポール・マッカートニーはビートルズ解散後、4人の中でいちばん「ビートルズ」っぽい音楽を期待された人だったと思われます。ソロになったポールはこのランキングで2位に選んだ「アナザーデイ」や「ジャンク」や「アンクル・アルバート」といった佳曲はあるものの、まだまだこんなもんじゃないでしょといったファンの溜飲を下げてくれたのが「マイ・ラヴ」だったんじゃないでしょうか。
タイトル通りのストレートなラヴ・ソング、もちろんポールの視線の先にはリンダがいたのでしょうが、ジョンの唄うラヴ・ソングがジョンとヨーコのプライベート・ソング然としてしまうのに対し「マイ・ラヴ」は普遍性を持ち多くのカバーも生まれています。ジョンにはジョンのポールにはポールの魅力があるということです。
19位 リンジー・ディ・ポール「シュガー・ミー」
72年末のヒットということなので僕は中学1年。この曲と翌73年の頭にヒットするカーリー・サイモンの「うつろな愛」のジャケットは中1には刺激的すぎるものでした。隠れて読んでいた川上宗薫のエロ小説にでてくる「コケティッシュ」な女というのはリンジーのような女なんだろうなぁと想像をめぐらし・・・。
20位 ザ・ローリング・ストーンズ「イッツ・オンリー・ロックンロール」
「黒くぬれ」や「19回目の神経衰弱」「悪魔を憐れむ歌」といったタイトルや『山羊の頭のスープ』の鍋で煮込まれる山羊の頭の写真や”俺がこのペンを心臓に突き刺してステージを血だらけにしたらどうよ”と歌われるこの歌のおかげで僕のストーンズ=不良の音楽というイメージは絶対的なものとなります。そのイメージはいまだに頭にあって、それが今やストーンズを少し遠ざける要因になっている気もします。デビュー50年、ストーンズ=不良であったのはその歴史の1/4くらいだったようにも思うのですがいったんこびりついたイメージというのは変わらないものです。
After midnight,we're gonna chug-a-lug and shout

Musician JJ Cale dies; wrote Clapton, Skynyrd hits
心臓発作で享年74歳。
”僕(クラプトン)が地面に埋められる前に 僕の手で JJケールのアルバムを作りたかったんだ"といって『ザ・ロード・トゥ・エスコンディード』が発表されたのが2006年。ソロ以降のクラプトンの成功にいちばん大きな影響を与えたのは実はJJケールとの出会いだったと思う者としては、70を前にした老ギタリストへのクラプトンからの素晴らしい恩返しだったと思う。
Road to Escondido/Reprise / Wea

今年発売されたクラプトンのアルバム『オールド・ソック』の2曲目にはJJケールが作りギターでも参加した「エンジェル」が収められていて、おそらくはこの曲がJJケールの遺作ということになるのでしょうね。クラプトンとの強い絆を感じさせてくれます。
>音楽家がレコードを売った枚数ではなく影響を与えた音楽仲間の数で評価されるとしたら、JJケールは70年代ロックンロールの金字塔と言えるだろう。 JJの追悼記事より
マーク・ノプラーもJJのような音が出したくてたまんなかったんだろうなぁ・・・
R.I.P.
ローリング・ストーンズ解体新書

お馴染みの中山康樹さんのローリング・ストーンズ本です。中山さんの場合世間一般の通念を一旦チャラにして時間軸を縦から横にしたり、地域性を考慮したりと新しい視線での分析を行うことが多く、目からウロコというのがよくあるのですが、今回面白かったのは”ローリング・ストーンズの作り方”という章にあったこんな一覧でした。
1926/1/3 ジョージ・マーティン 37歳
1934/9/19 ブライアン・エプスタイン 29歳
1936/10/24 ビル・ワイマン 27歳
1938/7/18 イアン・スチュワート 25歳
1940/7/7 リンゴ・スター 23歳
1940/10/9 ジョン・レノン 23歳
1941/6/2 チャーリー・ワッツ 22歳
1942/2/28 ブライアン・ジョーンズ 21歳
1942/6/18 ポール・マッカートニー 21歳
1943/2/25 ジョージ・ハリスン 20歳
1943/7/26 ミック・ジャガー 20歳
1943/12/18 キース・リチャーズ 20歳
1944/1/29 アンドリュー・オールダム 19歳
ごらんいただけばお分かりのようにビートルズとローリング・ストーンズ関係者の年齢的な関係の一覧です。右端の年齢は本文にはなかったのですが、最年少のアンドリュー・ルーグ・オールダムがローリング・ストーンズのマネジャーになった63年4月の各人の年齢を付け加えてみました。
”今更なにを言うとるんじゃい”といわれそうですが、ミック・ジャガーとキース・リチャーズってジョージ・ハリスンより若かった、9月新学期のイギリスですからキースにいたっては1学年下だったんですね。「彼氏になりたい」のようなイマイチの楽曲をありがたく受け取ってシングルにしてしまったのも年齢的な上下意識があったのかもしれないですね。まぁ本当に曲がかけなかったみたいですけど。
あとチャーリ・ワッツって意外に若かったんですね、ジョンより歳下。元々ジャズ・ドラマー目指していたからか、そのルックスのせいか老成してみえます。それとビル・ワイマンってこんなにおっさんだったんですね、年下のイアン・スチュワートがメンバーを外されたのにおっさんのビルが残ったのは若作りのルックスのせいなんでしょか。
そしてなんと言っても驚いてしまうのはデビュー時のローリング・ストーンズの売り出しに大きな貢献をしたと言われるアンドリュー・ルーグ・オールダム。44年生まれのアンドリューはまだ19歳!高校生に毛が生えたような歳でローリング・ストーンズのマネジャーになっているのです。

年齢を意識せずにアンドリューを見ていた時は、ブライアン・エプスタインの下で働いた後にローリング・ストーンズに目をつけアンチ・ビートルズとして「不良性」を戦略として売り出したクレヴァーな男と思っていました。でも19歳という年齢を知った上だと”戦略”として選んだというよりは当時のアンドリューの引き出しとしてはエプスタインの下で経験したビートルズ路線か 自分たちの素とでも言うべき”怒れる若者Angry Young Men”しかなかったんじゃないか。ビートルズ路線をとった場合揃いのスーツを着せたらミック、キース、ブライアンはイケてるけど、チャーリー、ビル、イアンはおっさんにしか見えないし、だったらスーツじゃない若作りの服装で、でもイアンはどうやってもアカンからメンバーからは外そう、みたいなことだったんじゃないかと思ってしまいました。

上の写真の6人(よりにもよってイアン、チャーリー、ビルが前面とは)だったら果たして成功できたのでしょうか?これはこれでチープ・トリックの20年先を行っていたかもしれませんが・・・
PR: 若い世代につなぐ-北方領土返還運動-政府ネットTV
考古学、分かりやすく…権威主義に反発 森浩一さん死去
森浩一さん死去:考古学、分かりやすく…権威主義に反発
森浩一先生がお亡くなりになりました。
僕は専攻がアメリカ文化史だったので一般教養の授業以外では直接教えを受けることはありませんでしたが、森先生が指揮をとる発掘の現場でバイトしたりなんて事があって、ちょこっとばかりご縁を持たせていただきました。その鬼瓦のようなルックスから怖い人という第一印象でしたが、実際は優しく気取らない近所のおっさんという感じの方でした。国からの賞なんかはすべて辞退していたのに熊楠賞のみ喜んで受けたというのも「現場からの人」という感じでいいエピソードです。 謹んでご冥福をお祈りいたします。
PS.新聞の片隅にはカレン・ブラックの訃報も小さく載っていました。
「イージ・ライダー」「ファイブ・イージー・ピーセズ」「エアポート75」いろいろありますがヒッチコキアンとしては「ファミリー・プロット」の金髪好きのヒチコックがわざわざブロンドのカツラまでかぶせて演じさせたインチキ霊媒師が最も記憶に残っています。相棒のブルース・ダーンとともにいい味出していました・・・。 R.I.P.




