さてここの所、忙しさにかまけてほとんど更新ができていない拙ブログ「鳥肌音楽」ですが、昨日7月4日をもって目出度く(!?)10年目に突入いたしました。スタートしたは2005年といえばシーツ、金本、今岡のクリーンアップやJFKの大活躍で阪神が最後に優勝した年、楽天イーグルスが誕生しセパ交流戦が始まった年でした、あれから10年、光陰矢のごとしであります。
それにしてもこの年のタイガース2位中日と10ゲーム差のぶっちぎりの優勝、宿敵巨人には25.5ゲーム差ですからね、本当に強かった。日本シリーズは・・・思い出したくありませんが。
ちなみにタイムリーなワールド・カップで見るとジーコ・ジャパンがFW大黒の活躍で2006年のドイツ大会行きを決めています。覚えてます大黒(笑)。
今回、ブログの1回目の記事を読んでいて、最初はこのブログのタイトルは「鳥肌音楽」じゃなかったことを思い出しました。
最初のタイトルは「ROCK BETWEEN THE LINE」というもので、これは当時刊行されていたピーター・バラカンさんの書籍のタイトルをそのままいただいたものでした。
ロックの英詞を読む/ピーター バラカン 
”Read Between the Line”といったら「行間を読む」ということになりますが、歌詞を理解するためには、まさに行間を読まなければならないのです。そうするための最低限の時代背景などを提供したい、という気持ちでこの本を作りました。「行間のロック」を楽しんでいただければ、と思います。
というピーターさんの巻頭の言葉にのって大好きなロックやポップの音の行間を読んでみようという思いで始めたブログでした。
ブログを始めたちょうど同じ時期に映画の世界に行ってしまっていたライ・クーダーの久々のポップ・アルバムである『チャベス・ラヴィーン』が発売されて、昔のアルバムを含め何かとライ・クーダーを聞く機会が増えていました。
そうしてライの昔のアルバムを聴いていて、ひっかかって来たのが『Chicken Skin Music』というアルバム・タイトルでした。
Chicken Skin Musicをそのまま訳せば「鳥肌音楽」となります。「鳥肌」というのは本来は寒さや恐怖を感じたときに立つものなのです。鳥肌イコール関西では「さぶいぼ」となりますが、関西で「さぶいぼ出たわ~」と言えば昔から感動したときに使われていました。それが全国にも広まったのか最近では「鳥肌立つ」というのは必ずしも負の表現ではなく「ファンペルシーのダイビング・ヘッドに鳥肌立ったわ」みたいな、感動を表す時にも普通に使われるようになってきています。
ということで鳥肌音楽=鳥肌が立つような感動的な音楽、うん、これこそが自分のブログにはぴったりだということでピーターさんには申し訳ないのですがわずか2週間あまりでタイトルを「鳥肌音楽」に変え現在に至っています。
タイトルを変えてしばらくしてから、ブログを読んでいただいた方から「鳥肌」の英訳は「goose flesh」「goose bumps」で「Chicken Skin」という言い方は無いというご指摘をいただいたことがありました。「違う」と言われると本当に違うのか自分で確かめたくなるのは昔からで、いろいろ調べたところChicken Skin=鳥肌という意味があるという一文を見つけました。
それはPidgin Englishと呼ばれるハワイで使われるローカル英語にありました。
>チキンスキン chicken skin 語源は日本語の鳥肌の直訳。英語で鳥肌は「グースバンプス」"goosebumps" であるが、ハワイではチキンスキンとなってしまう。
ハワイという島は中国や日本、フィリピン、ポルトガルといった国からの移民が多く、それらの人々が持ち込んだ言葉が英語と合体して独特の英語になっているようなのですが、まさかChicken Skinが日本語の「鳥肌」の直訳だったとは。
と、ここまでが「鳥肌音楽」というタイトルをつけた経緯だったのですが、せっかく昔のことを振り返ったので、もすこし「チキン・スキン・ミュージック」について掘り下げてみます。
ライのアルバム『チキン・スキン・ミュージック』ではハワイのギターの神様ギャビー・パヒヌイをゲストに迎えハワイアン・ミュージックが大きくフィーチャーされています。
Ry Cooder / chloe
おそらくはレコーディングなんかでハワイを訪れた際にビジン・イングリッシュを知り、そのいろんな国の言葉が交じり合ってできたという成り立ちに、自分自身の音楽に通じるものを強く感じてビジン・イングリッシュを使ったタイトルをつけたくなった、そういう事ではないかと想像します。
そして選んだのが鳥肌の立つ音楽という意味の『チキン・スキン・ミュージック』というタイトルだった。
ところで、欧米人も日本人のように感動した時にも鳥肌が立つのか、もし感動で立つのであれば『チキン・スキン・ミュージック』というアルバムはまさに名は体をあらわすアルバムということになりますし、拙ブログのタイトル「鳥肌音楽」もライからいただいて正解だったことになります。
米ヤフーで検索をかけてみると「idioMeaning」というサイトに次のような用例が出てきました。
(verb) to be very excited, cold or scared, and have spots on one’s skin
Example Sentences:
The young boy had goosebumps when his football team won the championship.
Sara has goosebumps all over her legs, because she’s wearing a short skirt in the cold.
A: Did you like the movie “The Ring“?
B: No! I had goosebumps the whole time. It was so scary!
最初の用例
>その若い男の子は自分たちのフットボール・チームが大会で優勝し、鳥肌が立った。
というのは、まさに感動で鳥肌が立つと言う意味で使われています、やはり英語でも使われるんですね。洋の東西、肌の色にも関係なく人間の生理現象は同じであるということなのでしょう。
ということでブログ「鳥肌音楽」はこれからも、鳥肌の立つすばらしい音楽を記事にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ごきげんよう、さようなら。
Ry Cooder - Goodnight Irene
PS.毎年のことながら拙ブログの誕生日にお祝いメールをくれるKに感謝いたします。
Thank You Girl
ADD SOME "CHICKEN SKIN MUSIC" TO YOUR DAY
37年前のロック・アルバム特選100

昔から音楽絡みの記事を切り抜いたり、フライヤーを集めたりという収集癖がありました。社会人となり家庭を持ち仕事の関係で引越しが多かったので自分以外には「ゴミ」なものとして捨ててられてしまったものが多いのですが、時々捨て忘れが顔を出したりします。
今回見つかったのは小学校から40過ぎまでずっと買ってた「少年マガジン」に特集されていた「ロック・アルバム特選100」というもの。一緒に残っていた広告などから判断すると1977年の秋口に掲載されたもののようです。
37年前のアルバム100選、この37年でロックに対する評価軸も大きく変わっている(と思います)こともあるので、リストを眺めるだけでも何かを感じられるのでは?ということでピックアップされている100枚を紹介してみたいと思います。
とりあえず、今回はここまで。
Mott The Hoople - The Golden Age Of Rock 'N' Roll
35年経つとこのくらい変わるのね
MIKA - We Are Golden
37年前のロック・アルバム特選100 その2
予告いたしました37年前の「ロック・アルバム特選100」の中味に入ってまいります。この特選は少年マガジンの1977年秋ごろの号に掲載されたものと書いたのは、特集の扉の頁に書かれた以下のような前書きから判断してのことです。
>”ロックの王者”エルビス・プレスリーが急死し、全世界に悲しい衝撃を与えた!しかし、ロックンロールは死なない!ヤングの生活にすっかり溶け込んだロックは、さまざまな響きをもって、巨大な流れを形づくり、新たな息吹をわきあがらせている。この100選はこうしたロックの歴史の中で重要な役割を果たした名盤を、膨大な発表作品から厳選したものである!エルビスに捧げる鎮魂の特集!
”ヤングの生活”という書き方に時代を感じますが、当時はナウかったんでしょうね(笑)。
エルヴィス・プレスリーが亡くなったのは1977年の8月16日のこと。42歳、まだまだ現役バリバリで亡くなったという感を持たれるかもしれませんが、当時の日本のロック・ファンの印象としては「もう終わった人」がこの世を去ったという方が正解のような気がします。
>ストレスからくる過食症に陥ったことが原因で体重が激増したことに加え、1975年くらいからは主治医だったジョージ・ニコポウラスから処方された睡眠薬などを「誤った使い方」で服用していた。(ウィキペディアより)
公式の死因は処方薬の極端な誤用による不整脈ということですが、その誤用の原因であったストレス太り(上の写真参照)が当時は大々的に取り上げられて「ドーナツの食べ過ぎで死んだ」(ピーナツバターとバナナのサンドイッチという噂もあり)と半ば嘲笑気味に語られていた記憶があります。
そんな状況の中で”ロックの王者”エルヴィスの急死に捧ぐ特集を少年マンガ誌が組むというのは、「巨人の星」「あしたのジョー」「男おいどん」「天才バカボン」「アシュラ」「ワル」なんていう連載をもち、70年安保の時代の大学生の風俗として「右手に(朝日)ジャーナル左手にマガジン」とまで言われた「少年マガジン」だからでしょうね、サンデーや後追いのジャンプ、チャンピオンに比べ「硬派」な感じがします。
またまた前置きが長くなりました。ではABC順に。
オールマン・ブラザース・バンド/フィルモア・イースト・バンド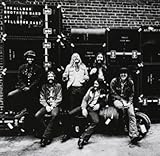
このアルバムについてはオールマンの最高傑作であるのはもちろんブルース・ロック、というよりは今ではジャム・ロックの傑作として評価は変わっていないのでは。このアルバムの評価によりこれからビッグになるという時にバンドの中心であり不世出のスライド・ギタリスト=デュアン・オールマンをバイク事故で亡くします。享年24歳、もしデュアンが生きていればなぁ・・・と77年には誰もが思っていたでしょうが、それから30年以上たってもオールマン・ブラザースがデュアンに勝るとも劣らないギタリストを加え活動を続けている(今年いっぱいで活動停止)とは想像つきませんでした。ギタリストとはもちろんデレク・トラックスのことですが、『フィルモア』でドラムを叩いていたブッチ・トラックスの甥っ子でデュアンのギターをロック・ファンに決定づけたデレク・アンド・ドミノスというバンド名から名付けられた、ある意味、デュアンのスーパー・サブを運命づけられた男だったというのも「物語」を感じます。
Duane Allman's LAST performance - Statesboro Blues - Allman Brothers Band
ジャケットがありきたりなステージ写真じゃなくて器材の山を前にポーズをとるメンバーの姿というのもツアーで人気をものにした実力派バンドという感じで新鮮でした。
ザ・バンド/ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク

これは近年のロックのひとつの潮流である「ルーツ・ロック」のルーツといえるアルバムということで時を経ても重要性は変わらないでしょう。ディラン画伯のヘタウマなジャケットも古びないですね。U2の『ヨシュア・ツリー』のヒントはこのジャケじゃないかと思うのですが、はたして。
THE BAND - We Can Talk
んだけど おいら 南部で凍え死ぬくらいだったら
カナダで 焼け死にてぇよ!
ビーチ・ボーイズ/グレイテスト・ヒッツ
37年前の100選を記事にしている理由は、もちろん、その間にどのようにロックに対する評価軸が変わったのかというのを書きたいわけで、「なんでこんなアルバムが選ばれてんねん、ちゃうやろ」とツッコミを入れたいからです。
ということで最初のツッコミ。
このブログでも何回も書いていますがビーチ・ボーイズといえば『ペット・サウンズ』、そして『ペット・サウンズ』は20世紀最高のロック・アルバムであるという評価はここ20年くらいで生まれてきた評価軸です。77年のイメージでいえば前年に15周年記念の『15ビッグ・ワン』というアルバムがそこそこのヒットはしていましたが、やはり一昔前に終わったオールデイズ・バンドというのが正解だと思います。なのでオリジナル・アルバムでなくヒット曲を集めたベスト・アルバムが選ばれるのもやむを得ないとは思います。ただここで選ばれているベストは日本編集のもの、せめて『終わりなき夏』くらいにしとけなかったのか。
とにかく77年当時、ビーチ・ボーイズはベストですませとけ、そんなバンドだったということです。
THE BEACH BOYS/FUN FUN FUN
ザ・ビートルズ/サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド
ザ・ビートルズ/アビー・ロード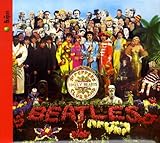
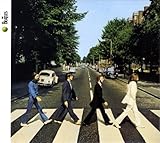
このアルバム100選に同一アーチストで2枚選出されているのは3組のみ。ディランとストーンズそしてビートルズ。さすがはビートルズという感じですが、ビートルズのアルバムから2枚選ぶとしたら・・・。『ペパーズ』と『アビー・ロード』というのは当時としては至極当然に思えますが、今選ばれるとしたら『ペパーズ』の代わりに『リボルバー』になるかも知れません。はたまた、77年当時はオリジナルが日本では発売されていなかったので選ばれにくかっただろうと思われる衝撃のデビューアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』っていうのもありかも。日本での人気を考えれば『ビートルズ』(通称ミート・ザ・ビートルズ)や『レット・イット・ビー』なんていうのも・・・。まぁとにかく「ザ・ビートルズ」が広い意味で世界一のロック・バンドだったという評価は今も昔も変わっていないといえるのではないでしょうか。
THE BEATLES/SOMETHING
ジェフ・ベック/ワイヤード
ビートルズの『アビー・ロード』の次に並ぶというのは流れ的にきれいなジョージ・マーティンのプロデュースによるジェフ・ベックの76年の革新的なアルバム。とにかく1曲目の「レッド・ブーツ」から超絶テクニックの応酬に舌を巻きました。まだまだ、上手い演奏=素晴らしい音楽みたいな「偏見」を持っていた高校生だったんですね。とはいえ素晴らしいアルバムであったのは間違いないのですが、現在はどっちかといえば同じくジョ^ジ・マーチンのプロデュースによる前作『ギター殺人者の凱旋(ブロウ・バイ・ブロウ)』の方が評価されているようです。
それにしても、米国16位、英国38位、日本7位(オリコン調べ)というアルバム・チャートを見ると、テクニック至上というのは僕だけでなく日本人の価値観としてあるのかなと思ってしまいます。グルーヴみたいなものではなかなか欧米にはかなわなかった日本人ですが速弾きや正確性といったテクをものに歌のない(日本人の弱点ですからね)フュージョンで欧米に肩を並べ、その延長でコンピューターでグルーヴを作るという逆転の発想で世界に飛び出したのがYMOだったんじゃないかと思います。その名の通り日本でしか生まれえなかったバンドだったと思います。
Jeff Beck Wired Full Album
ということで、ようやく1頁、先は長いなぁ。
The child is father of the man.

ナット・ウェラー NATT WELLER という名前を聞けばピンとくる人多いでしょうが、そうあのポール・ウェラーの息子がデビューいたしました。ポール・ウェラーとは1歳違いということもあり、なんかツレの子供みたいな気分でCDを聴いてみました。
It Begins (MINI ALBUM+DVD)/NATT WELLER
今回のアルバムは日本企画のようで発売元はavex、頭のアー写を見てなんとなく嫌な予感がしたのですが・・・
>6月25日発売デビューミニアルバム「It Begins」収録。父であるポールウェラーがギターで参加した話題曲。「Burning in The light」のMusic Video公開!!
ということなのですが、アルバム自体はかなりソフィスケイトされているようですが、下にアップした動画を見ると、おそらく本人はV系のラウド・ミュージックがやりたいんじゃないかと思われます。
親父がポール・ウェラーだからといって親父みたいなガッツのあるロックを期待されてもナットとしては迷惑なのでしょうが。ちょっと残念な気分です(笑)。
37年前のロック・アルバム特選100 その3
前回の追記になりますが、現在のアルバムの評価の指標として米ローリング・ストーン誌の「Rolling Stone's 500 Greatest Albums of All Time」(以下「500 Album」)の順位を記しておきます。
オールマンの『フィルモア・イースト』は49位、バンドの『ビッグ・ピンク』が34位、参考としてビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』が堂々の2位、そして『ペット』を抑えての1位がビートルズの『ペパーズ』。やはり『リボルバー』より上なんですね。『アビー』は14位。ビートルズ関係でいうと3位に『リボルバー』5位に『ラバーソウル』ちょこっと嬉しいですね、10位に『ホワイト』、39位に『プリーズ・プリーズ・ミー』、53位に『ウィズ・ザ・ビートルズ』と100位以内に7枚もランク・イン。FAB4という呼名は伊達じゃないですね。ジェフの『ワイヤード』はランク外ですがギタリストとしては「100 Greatest Guitarists」では14位、デュアン・オールマンは2位、ジョージ・ハリスンが21位、ロビー・ロバートソンは59位ちょっと低い。
では続きです。
ブラッド・スウェット&ティアーズ/B.S&Tの歴史
こちらも日本編集盤のベストですね。バンド名をそのまま訳してはいるのですが『血と汗と涙の歴史』というタイトルからは非常に暑苦しいものを感じます。アル・クーパーの絡みで1stくらいしか聴いたことのない僕がいうのもなんですが、77年当時のBSTのイメージとしてはシカゴと並ぶブラス・ロックの雄というよりは、三面記事番組「ウィークエンダー」のアノ曲(「スピニング・ホィール」)の人たちという方も多いのでは。
Blood Sweat & Tears - Spinning wheel
新聞によりますと(笑)
「500 Album」ではアル・クーパーが中心だった1st『子供は人類の父である』が266位。
ところでこの「子供は人類の父である」というタイトルはビーチ・ボーイズの『スマイル』の曲のタイトルでも使われています。調べてみるとワーズワースの「虹」という詩からの引用のようです。
「THE RAINBOW」 by William Wordsworth
MY heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky
So was it when my life began
So is it now I am a man
So be it when I shall grow old,
Or let me die!
The Child is father of the Man
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.
大地を穢す「原発」を再稼働しようとしている、どこぞの首相に読んでいただきたい素晴らしい詩です。
デビッド・ボウイ/屈折する星くずの上昇と下降 そして火星から来た蜘蛛の群
これまた、仰々しい邦題ですが原題がThe Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Marsですからある意味直訳ではあるんですけどZiggy Stardustとthe Spiders from Marsが固有名詞なので「ジギー・スターダスト&ザ・スパイダーズ・フロム・マーズの成功と没落」といった意味になるかと。現在は単に『ジギー・スターダスト』になっていてこれはこれで素っ気ない気もしますけど。『ペパーズ』から始まったとされるロックのコンセプト・アルバムのひとつの完成形であり、近未来的でSF的で中性的なジギーというキャラクターはボウイでしか演じられないもので、日本のV系ロックは勿論、その世界観は直接的であれ間接的であれジャパニメーションの世界なんかにも影響を与えているのではと思ってしまいます。
「500 Album」では35位、ちょっと低い気もしますが永遠の名盤だと思います。
David Bowie - Starman (1972)
美しい!
ジャクソン・ブラウン/プリテンダー
76年の『プリテンダー』もいいけど、やっぱりジャクソン・ブラウンと言えば『レイト・フォー・ザ・スカイ』やろ、いややっぱ瑞々しい1stが・・・。と言ったツッコミが聞こえてきそうですが、彼の70年代のアルバムは(その後もか)「青春」という文字の書かれた金太郎あめという気がします。例えるならアメリカの尾崎豊、ちょっと違うか(笑)。自分の事務所に「ロード・アンド・スカイ」なんてジャクソン・ブラウンの曲のタイトルをつけてしまったので、アメリカの浜省の方が適正かな。なんて書いているとジャクソン・ブラウンの事が嫌いだと思われるかもしれませんが、高校時代は毎日のように彼の歌声を聴いていたくらい大ファンです。
なので今も昔も変わらず人気があると言いたいところですが、「青春」の人ですからオジさんになっちゃった今は若い人にはちょっとでしょうね。昔、若かった僕たちにとっては永遠のアイドルなのですがね。
「500 Album」では391位、ちなみに『レイト・フォー・ザ・スカイ』は少しだけ上で375位やっぱ低すぎですね。
Jackson Browne - BBC 1978 - Here Come Those Tears Again
やっぱ、いいなぁ。そうそう『プリテンダー』が出たころ、ツレとの間で何が一番の「プリテンダー」かっていうとジャケの雑踏を歩いてくるジャクソン・ブラウンの姿、Tシャツをチノパンに突っ込んだちょっとお腹の出たその姿こそが「プリテンダー」なんちゃうと言うてたことを思い出しました。
ポール・バターフィールド・ブルース・バンド/ SAME
64年にブリティッシュ・インヴェイジョン嵐が吹き荒れ、R&Rがいったん廃れていたアメリカの多くの白人の若者たちが元々は自分たちの国の音楽、同じ国だけど違う世界の音楽であるブルーズやR&Bを再発見します。ただし黒人のブルーズ・マンからすればストーンズなどを代表とする英国勢の音楽は自分たちのレコードをコピーしただけの「プラスチック・ソウル」に聞こえていました。そして、そんなプラスチック・ソウルに対して米国の「本物」たちからの反撃が始まるのですが、その急先鋒となったのが白黒混合ではありますが本場シカゴのリトル・ウォルター直伝のブルーズ・ハープ吹きポール・バターフィールド率いるポール・バターフィールド・ブルース・バンド(PBBB)でした。
Paul Butterfield Blues Band / Born In Chicago
PBBBの登場はプラスチック・ソウルに対する米国の返答という意義も大きいのですが、フォークに同時代音楽としての限界を感じていたボブ・ディランをエレクトリック化させロックン・ロールをロックへと進化、深化させたという意義には最大限の評価が与えられるべきかと思います。
⇒ マギーズ・ファーム(Live At Newport Folk Festival 65)
それを考えると「500Album」で468位というのはかなり低すぎるんじゃないのかなぁ。
ちなみに日本ではそういった歴史的意義はおいといてマイケル・ブルームフィールドやエルヴィン・ビショップが抜けエイモス・ギャレットがリード・ギタリストであった通称ベター・デイズ時代のPBBBの人気が高いようです。
Paul Butterfield's Better Days - Please Send Me Someone To Love
M.ブルームフィールドのゴリゴリのブルーズ・ギターも良いけど、エイモスの痒いところ手の届きそうで届かないような、思いっきりじらされ悶絶しそうになるギターが個人的には大好きです。
ザ・バーズ・グレイテスト・ヒッツ/ザ・バーズ 
バーズもベスト・アルバムですましてしまうのが77年の評価なのでしょうね。一応、日本編集ではなく米コロムビアによる公式ベスト・アルバムで67年に発売されています。ちなみにオリジナル・アルバムを「500Album」で見ると120位に『ロデオの恋人』、127位に『昨日より若く』、171位に『名うてのバーズ兄弟』、そしてデビュー・アルバムの『Mr.タンブリンマン』が233位といったところで、フォーク・ロックの始祖でサイケデリック・ロックを牽引し、60年代後半にはカントリー・ロックに回帰(?)し現在のルーツ・ロックの礎を築いたバーズの評価としてはどうなのという気もします。
THE BYRDS - You Ain't Going Nowhere (1968)
それにしても手っ取り早くバーズを知る一枚としてこのベストがあったおかげで、フォーク・ロック~サイケ期(スペース・ロックでしたっけ)のバーズしか知らず、カントリー・ロック期を聴くのが遅れてしまいました。ベスト・アルバムの功罪といっていいかもしれないですね。
ハレルヤ/キャンド・ヒート
申し訳ありませんが、キャンド・ヒートはウッドストックの「ゴーイング・アップ・ザ・カントリー」くらいしか聴いたことありませんでした。今回アルバム『ハレルヤ』の曲を中心に何曲かYOUTUBEで聴いてみたのですが、良いですね、ビール片手に身体を揺らしながら聴いたら楽しめるだろうなぁという音楽。
Canned heat/Time Was
ベンチャーズのドン・ウィルソンの弟にしてブルーズの研究家であったアル・ウィルソンとブルーズのレコード・コレクターであったボブ・ハイトの二人の趣味が高じてブルーズ・バンドをやっちまったのがキャンド・ヒートということなのですが、自分たちの大好きな音楽をみんなと共有できる楽しさが缶詰にされている、そんなバンドの喜びが伝わってくる。中心人物のアルが70年にドラッグの過剰摂取で亡くなり。80年にはボブも他界ということもあってか日本ではほとんど忘れ去られたような感じがするのが寂しいところです。
主要メンバーを亡くしながらも、なんとキャンド・ヒートは解散せず現在もライヴ・バンドとして全米を廻っているようです。
昔の名前で出ていますじゃなくて、その場で鳴っている音楽をバンドも聴衆も楽しんでいる感じがするのはブルーズという音楽ゆえかもしれないですね。
こういうエントリ書きながら言うのも変ですけど、一般的な評価の「一般的」ってのは何なんでしょうね・・・。結局、音楽ってのは一対一で楽しめるか否かだけという気がしてしまうキャンド・ヒートでした。
二人だけのデート、ただ貴方といたいだけ

ということでYOUTUBEでピクシー・ロットの動画をいろいろ見ていたら、こんな曲をカバーしていました。
Pixie Lott - I Only Want To Be With You (Acoustic)
そう「二人だけのデート」ですね。この曲、80年代の英国を代表する女性歌手が若かりし頃にバンドとしてカバーしていましたね。
The Tourists - I Only Want To Be With You
79年に英国で4位となったスマッシュ・ヒットなのですがボーカリストは誰かお分かりでしょうか。かなりけばい化粧と衣装なのですが、25歳のアニー・レノックスです、かなり無理のある感じもします。
ツーリスツのこの曲が日本で紹介された時に、20歳前後だった僕のような年代の人はおそらくみんなこの曲はあのアイドル・バンドのカバーだと信じて疑わなかったことと思います。
I only wanna be with you-Bay City Rollers
今や人口に膾炙することもほとんど無くなりましたが70年代半ばの日本のヒット・チャートを席巻していたベイ・シティ・ローラーズが76年に大ヒットさせ、僕も彼らのバージョンでこの曲を知りました。
でも、勿論この曲のオリジナルはこちらですね。63年のヒット。
Dusty Springfield (True Stereo) I Only Want To Be With You HD
ツーリスツのカバーも、おそらくはこちらに対してのリスペクトですよね、それはその後のユーリズミックスのアニーの姿を見れば想像つきます、そしてピクシー・ロットもちの論で英国ブルー・アイド・ソウルのルーツ、ダスティ・スプリングフィールドへのリスペクトですね。
途中のストリングスも素晴らしく、クリスタルズを英国流に消化するとこんな感じか、なるほど。
とにかくカバーの多い曲ですが、なんとボレロの王子様ルイス・ミゲール君も87年にカバーしてたんですね。ラテンにも不思議と会いますね。
Luis Miguel - Ahora Te Puedes Marchar
忘れてましたが、愛しのニコレットちゃんもカバーしてました。
Nicolette Larson∻"I only want to be with you"
これは初めて聴きましたが、好きですね、こういうの。マリリン・マンソン。
I only want to be with you - marilyn manson
トミー・ヘブンリー!智ちゃん可愛いから許す(笑)
TOMMY HEAVENLY6 - I Only Want To Be With You
余談ですが、学生時代のサークルでは「二人だけのデート」を歌っているといつの間にかラズベリーズの「明日を生きよう」になってしまうというネタが一時期はやっていました、逆やったかな・・・。
Raspberries - I Wanna Be With You
PR: Windows 7搭載の中古PCならおまかせ
こいつはお前へ贈る俺のロックン・ロール・ラヴレターさ
前回のエントリの中でベイ・シティ・ローラーズの歌う「二人だけのデート」を取り上げました。ダスティ・スプリングフィールドのオリジナルより前にローラーズのカバーを聴いたためか、「二人だけのデート」はどうしてもアイドル・ソングに思えてしまいます。
当時(75年~78年ごろ)をご存知の方ならお分かりかと思いますがとにかくこの日本でも女の子がワァワァキャーキャー、タータン・チェックの衣装を着て笑顔を振りまきながら口パクのステージと、今でいえば「ちゃらい」アイドル・バンドそのものでした。
アイドル・バンドなのでメンバーも10代かと思いきや、デューク中島さんからいただいたコメにもあるように、
>若いレスリーでも 昭和30年、ウッディが昭和32年生まれ。F田君や 故M原君がやってるような感じですよね。それどころか、エリックは、昭和28年生まれ、アランに至っては、昭和24年生まれ。私のD大同期最年長が 昭和25年生まれでしたから あの人より年上かあ…と違和感有りましたね。でも キャッチ-で、いいバンドでした。
「二人だけのデート」ヒット時の年齢でいうとレスリーが21歳、ウッディがかろうじて19歳でエリックは23歳、アランは27歳と結構大人なバンドだったんですね、意外ですが。元々65年にアラン(16歳)とデレク(14歳)のロングミュアー兄弟によって結成され68年にベイ・シティ・ローラーズに改名し71年に「朝まで踊ろう(Keep on Dancing)」(全英9位)でデビューという経歴ですから、ひょっとしたらエジソン・ライト・ハウスなんかのブリティッシュ・バブルガムのひとつと考えた方が良いのかも。
ちなみに彼らのデビューを仕掛けたのはあのジョナサン・キングでいきなり9位というのはさすがという気もしますが、その後は何故か泣かず飛ばずでローラーズの代表曲である「サタデイ・ナイト」も4枚目のシングルとして73年に発売されますがチャート・インできずと不遇の時代が続きます。売れないのはルックスのせいと考えたのか既に加入していたポール・マッカートニー似のエリックに加え、ボーカルのノビー・クラークをレスリー・マッコーエンに(これはかなりのポイント・アップ)、 ⇒⇒
⇒⇒ 
そしてあごがキュートなウッディくんを加え、心機一転、これが功を奏したのか74年のアルバム『エジンバラの騎士(Rollin')』(うっ!宝塚か)が全英NO.1を獲得しタータン・ハリケーンが吹き荒れることになります。
エジンバラの騎士/ベイ・シティ・ローラーズ
そして75年5月に「バイ・バイ・ベイビー」で遂に全英No.1を獲得します。
このシングルで日本でもタータン・ハリケーンが吹き荒れることとなるのですが、いつもの文化放送の「ALL JAPAN POP 20」のチャートを調べると75年の7月第一週に38位に初登場し2ヵ月後の9月第二週にそれまで6週間1位をキープしていたウィングスの「あの娘におせっかい」を蹴落としみごと1位を獲得。その後カーペンターズの「ソリテアー」(ニール・セダカ作の名曲だ)に抜かれるまで8週にわたり1位を続けています。ちなみに3位はイーグルスの「呪われた夜」でした。
>”新しいビートルズ”を見つけた!英米を征服した噂のローラーズ旋風日本上陸
というキャッチ・コピーですが、元ビートルズのポールのバンド=ウィングスを抜いての一位獲得と、人気という面においてはまさに”新しいビートルズ”というのはローラーズに相応しいものでした。
Bay City Rollers - Bye Bye Baby 1975
さてこの「バイ・バイ・ベイビー」も当時はてっきりローラーズのオリジナルと思っていましたがこれもカバー・ヒットでした。オリジナルはフォー・シーズンズで65年に全米12位のヒットを記録したものでした。
Frankie Valli & The Four Seasons - Bye Bye Baby
金持ちのご令嬢と貧乏男の恋「悲しき朝焼け」や金持ちのボンボンと下町の女の子の恋「ラグ・ドール」といった単なる甘いポップスではない歌詞でヒットを飛ばすフォー・シーズンズですがこの「バイバイ・ベイビー」も御多分にもれず愛し合っているのに別れざるを得ないカップルの歌です。
一緒には居られないと 彼女に話すべきだった
僕の指には結婚指輪
(彼女は僕をとりこする だけど 僕は自由じゃない)
だから バイバイ ベイビー さよならだ
オリジナルはローラーズ版よりテンポはぐっと抑え目でフランキー・ヴァリーの歌声は辛い気持ちを彼女に一言一言噛んで含める、そんな風に聴こえます、さすがという感じ。それに対してローラーズのバージョンはなんかあっけらかんとしてるというか、フォー・シーズーンズのオリジナルとは落差があるように感じられます。
Jon Kutnerの「1000 UK #1 Hits」という本よれば、実はローラーズのメンバーはフォー・シーズンズのオリジナルを聴いたことがなかったようです。彼らが聴いていたのはウッディのシングル・コレクションにあったシンボルズSymbolsが67年にカバーしたバージョンだったようなのです。
The Symbols - Bye Bye Baby - 1967 45rpm
確かにこれだとフォー・シーズンズほどには落差はないですね。それにしても既婚男性と若き乙女の恋というのは、ティーンエイジ・バンドだと嘘くさくなりますがメンバーの平均年齢が20歳を超えているローラーズだったら有りなんというか、メンバーの年齢をうまく逆手に取った選曲だったのかもね。
75年暮れには郷ひろみもカバー。安井かずみが訳詞していますが、郷ひろみも55年生まれとレスリーと同年なのでOKだったのでしょうか。それにしても郷ひろみという人その時々の自分にあった洋楽曲を見つけるセンスを感じてしまいます。
余談ではありますが、ピクシーズ・スリーの「コールド・ウィンター」からの引用といわれるまる子ちゃんの主題歌、渡辺満里奈の「うれしい予感」ですが、「バイバイ・ベイビー」も少し入っている気がします。
渡辺満里奈/嬉しい予感
「二人だけのデート」と同じくオリジナルより先にローラーズを聴いてしまったおかげで、後にオリジナルを聴いたときに何か違和感を感じて、その良さに気付くのに時間がかかってしまいました。正直言って歌詞も今回初めてきちんと読んで”あぁ、そういう意味だったのね、単なるカップルの別れの歌じゃなかったんだ”と繰り返しになりますが、フランキー・ヴァリの歌い方が腑に落ちたわけで、遅すぎますね。
ローラーズは他にもロック・クラシックスと呼べる曲をカバーしています。以下の曲はさすがにローラーズを聴く前にオリジナルを聴いていたので、カバーに幻惑(!?)されることは無かったのですが、中には、ローラーズで初めて聴いてしまってオリジナルの良さに気付くのが遅れたという人もいるのでしょうね。カバー・バージョンというのはオリジナルへの入門に大変役立つものなのですが、最初にきいたものの印象が残りすぎるという功罪相半ばということがあるので要注意です。
たとえばこんな曲。
Don't Worry Baby - Bay City Rollers in Japan with Pat McGlynn
ローラーズ版もけっして悪いとは言わないけど、やっぱりブライアンの声が先で良かったなと。
一瞬在籍したイアンが抜け新たにパット・マグリンが加わった直後に来日した時の映像のようですが、パットくん可愛いですね、エリックがほとんどカメラに無視されてるのがかわいそうという気も。
こんな超名曲も。
Bay City Rollers Be My Baby .wmv
「ビー・マイ・ベイビー」と「ドント・ウォーリー・ベイビー」をカバーするというのはこの2曲の関係性からすれば必然性ありのナイス選曲なのですがちょっと軽い気がするなぁ。ドラムスはかなり力入ってますが。それにしても女の子たちの熱狂ぶりがハンパない、ステージー上は彼女たちが投げたゼリービーンズで完全に埋まっているのもすごいですね。
上の2曲も次の曲の落差に比べれば思いっきり許せてしまいます。ローラーズにちょこっとだけ在籍したイケメン、イアン・ミッチェルくんが結成したロゼッタ・ストーンによるブルース・ロックの名曲のカバー、邦題は「サンシャイン・ラヴ」なのでオリジナルに気付かなかった人もいるかもしれません(笑)。
Sunshine Of Your Love by RosettaStone
映像見て知ったのですがこのバンド、イアン・ミッチェルがボーカルじゃなかったんですね。てっきりイアンがフロントにたってギター弾きながら歌ってというイアンの「人気」を前面に出したバンドと思っていたのですが、どうやらイアンはギターで勝負という「実力」バンドをめざしていた感じですね。にしてもボーカルいちびりすぎ(笑)。
次は”この曲がまさかあの人のカバーだったとは”とずいぶん後になって絶句した曲です。
Rock 'N Roll Love Letter - Bay City Rollers
実はこの曲、その昔ダリル・ホールと一緒にガリヴァーというバンドをやっていたフィラデルフィアのシンガー・ソング・ライター=ティム・ムーアの2ndアルバムの中のナンバーです。ティム・ムーアといえばアート・ガーファンクルが取り上げた「セカンド・アヴェニュー」や1stアルバムのオープニング・チューンの「フール・ライク・ユー」のような洗練されたシティ・ポップスの人というイメージだったので、ローラーズがティムの曲をカバーという驚きよりはむしろあのティム・ムーアがこんな曲書いちゃったんだという驚きの方が強かったりしました。
Tim Moore - Rock and Roll Love Letter
うーん、これは良質のパワー・ポップスに仕立て上げたローラーズの方が良いかな、ティム・ムーアが歌うのには無理がある気がします。でもこれティムのボーカルをダリル・ホールにするとホール&オーツの曲でいけそうな気もします。ひょっとしてガリヴァー時代の作品?
おまけ
「ビー・マイ・ベイビー」と「ドント・ウォーリー・ベイビー」とくれば次はこの曲(笑)。第二のローラーズ狙いのバンドがいっぱい出てきましたが、この曲はビーチボーイズの香りがしてとっても好きでした。大雨の日曜ですが、この歌で少しは爽やかに、「すてきなサンデー」です。
Buster -Sunday
37年前のロック・アルバム特選100 その4
いつもながら大きく間が空いてしまいましたが、37年前の少年マガジンによるロック・アルバム100の続きです。
シカゴ・ライヴ・イン・ジャパン/シカゴ
そう来たか、まさかのライヴ・イン・ジャパン!。72年の来日時大阪フェスティバル・ホールで録音され日本でのみ発売(2007年には海外でも発売)ということでディープ・パープルなんかと並ぶライヴ・イン・ジャパンもののはしりと言えるアルバムです。余談にはなりますがパープルもメインはフェス音源だったし、後のBB&Aなんかも含めやっぱフェスって音がいいんでしょうね。
Chicago 25 Or 6 To 4 Live in Japan 1972 Osaka Festival Hall
シカゴもバーズなんかと一緒で年代によって同じバンドなのかと思うほど音楽性が違ったりするのですが、77年時点ではテリー・キャスも生きてたし、まだまだブラス・ロックという印象ですからブラス・ロック・バンドとして乗りに乗っていた5枚目(「サタデイ・イン・ザ・パーク」のヒットあり)までの代表曲が演奏された『ライヴ・イン・ジャパン』を選ぶのも妥当といったところでしょうか。
もひとつ余談です。シカゴの15枚目まで、つまりコロムビア時代のカタログが80年代まではCBSソニーから出ていましたが、90年代にはテイチク(イメージあわんなぁ)そして今はワーナー(ライノ)から発売されています。これはシカゴ自身がコロムビア時代のカタログの権利を有しているからです。ワーナーに移籍しデヴィッド・フォスターと組んですっかりAOR路線となったシカゴですが、おかげでコロムビア時代の作品は昔ほど売れなくなり、コロムビアは権利を持っててもしょうがないと二束三文でバンドに売ってしまったようなのですが、CDの時代になり過去のカタログが再発されあらたな需要が生まれ権利を手にれていたバンドは思わぬ利益を得ることになったようです。シカゴのような大所帯バンドが解散もせずにやってこれたのは楽曲の権利をバンド自体がもっていたことによるようです。
Chicago "Questions 67 & 68" 1995 日本語バージョン Vo.ジェイソン・シェフ
忘れていましたが「500Album」にはシカゴのランク・インはなし。そんなもんなんですかね。
マッド・ドッグス&イングリッシュ・メン/ジョー・コッカー
お恥ずかしながらこのアルバムもいまだ聴いたことのない一枚です。デラニー&ボニーのバンドピアニスト&ギタリストとしてスワンプ・ロックの重要人物になっていたレオン・ラッセルがイギリスからやってきたソウルフルな歌手ジョー・コッカーを成功させるためにデラニー&ボニー&フレンズの主要メンバーを引き抜いて行なった大所帯ツアーの実教録音盤。
Mad Dogs and Englishmen - Honky Tonky Woman
デラボニから引き抜かれたのはカール・レイドル、ジム・ゴードン、ジム・プライス 、ボビー・キーズ 、リタ・クーリッジ といったところで、リズム隊はデレク&ドミノスへとつながっていくわけでスワンプ・ロックの代表作の一枚なのですが、「500Album」には残念ながらランク・インしていません。
Joe Cocker/ I Hope
44年生まれということで70歳のジョー・コッカーですが、上の音源は2年前のアルバムからディシー・チックスをカバーしたナンバーですがいぶし銀のような素晴らしいボーカルです。それにしても、こういう音楽でいまだにメジャー・メーカー(コロンビア)からアルバムが出せているってのは奇跡のような気がします。
コラシアム・ライヴ/コラシアム
これも名盤だという記事を読んだりしたことは何度もありますが音は全く聴いたことがありませんでした。こんなんじゃ大学時代のサークルの某F先輩に「お前、何も分かっとらんのやな。」と言われそうです。よくよく考えるとこのリストに挙げられているアルバムで聴いたことがないものはジョー・コッカーやコラシアム、後に出てきますがクリーム、EW&F、フラワー・トラベリング・バンド、ロリー・ギャラガー、GFR、ゼップ、ウィングス、サンタナなどで、すべて2枚組もしくは3枚組で、おまけにどれもライヴ・アルバム。
つまりは金がなくて買えなかったことと、熱い音が基本的に苦手というのがあったのかなと思ってしまいます。
Lost Angeles (part 1) - Colosseum
このコラシアムのライヴもテンション高いですよね、これを2枚通して聴くのは今でも無理かもしれません。これも残念ながら「500Album」には未ランク・インです。
チキン・スキン・ミュージック/ライ・クーダー
このアルバムは当然聴きこんでいます、拙ブログの「鳥肌音楽」というタイトルは勿論このアルバムから。ライのアルバムではひとつ前の『パラダイス&ランチ』が一番好きなんですけどね(笑)。
Ry Cooder - Always Lift Him Up _ Kanaka Wai Wai
自分の名前を冠したデビュー・アルバムやインストなのに歌が聴こえてくる名演「ダーク・エンド・オブ・ザ・ストリート」を含む2ndではアメリカ不況時代のフォーク・ソングを中心に歌っていたライですが『パラダイス&ランチ』で国境(Borderline)を超えメキシコへ、そしてこのアルバムではハワイへと取り上げる音楽の幅が一気に広がっていきます。
ライを聴くまでは大観衆が見つめるステージでスポットライトを浴びて歌っているような音楽が素晴らしいんだと思っていましたが、ローカルな祭りであったり、街角であったりといった歌い手と聞き手が非常に近い場所で歌われる音楽にだって、というかだからこそ聴き手の琴線に触れてくる音楽というものもあるのだということを教えてもらった気がします。そして歌がうまい(味のあるライの歌声を聴けば)、演奏がうまいことが(もちろんライはテクニシャンなのですが)音楽の価値を決めるわけではないということを教えてもらいました。
バイヨー・カントリー/クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイバル
CCRって好きなバンドなんですが、結局オリジナル・アルバムは『ウィリー・アンド・プア・ボーイ』しか持っていません、それもLPのみ。LP時代は2枚組のベスト、CD時代にはそのLPを1枚のCDにしたベストを聴くのがほとんどでした。オリジナル・アルバムが廉価CDで再発されるたびに買わなきゃなぁと思いながらずるずる現在に至っています。中古で安く出ていれば買うとこなんですけど、思い返すと中古盤店でもCCRのオリジナルってめったに見ないような気がしてきましたら。ひょっとしたら僕のようにベストですましている方が多いのかもしれませんね。
CCR - PROUD MARY(LIVE 1970)
いい意味で「金太郎飴」的なイメージがあるんですよね、どのアルバム聴いても同じなんじゃないかという、それはCCRだけじゃなくジョン・フォガティのソロまで含めて。
僕にとってCCRから受けた一番大きな影響はチェックのコットン・シャツを着るようになったことかも知れません。中学くらいまでは母親の買ってくる服を着ていましたが、高校入って着るものは自分で決めるとなったのですが、ライの着ているようなアロハ・シャツは地方都市のショッピング・センターにはなかなか無く、というかあったとしてもちょっと着るのは恥ずかしかったかも、かわりにチェックの赤いコットンシャツを買ってきて、Gパン(ジーンズ)もラッパからストレートに変えてジョン・フォガティを気どっていました。少しするとGパンにはつぎあてが縫い付けられニール・ヤングに変わっていくのですが(笑)。
ところで上にアップしたCCRの代表曲である「プラウド・メアリー」ですが、最初に聴いたのは友人の家にあったキャンディーズのライヴだったような気がします。
キャンディーズ プラウド・メアリー(ライブ)
リード・ヴォーカルをとるミキちゃんの選曲じゃないかと思いますがCCRバージョンじゃなくてアイク&ティナ・ターナー・バージョンのカヴァーというのがただのアイドルじゃないって気がします。
アイク&ティナ・ターナー/プラウド・メアリー
神曲だね。
クリームの素晴らしき世界/クリーム
クリームもちゃんと聴いたことがないバンドです。これは中学の時にすごいバンドらしいから何か一枚買うてみようということで手に入れたのが『グッバイ』という何とも中途半端なアルバムだったこともあるのかなと。
クリームやジミヘン、あとザ・フーといったあたりがブルース・ロックを大音量のハード・ロックへと変貌させていった張本人として昔も今も変わらず評価されつづけているのでしょうが、個人的に暑苦しいロックが苦手というのがクラプトンのソロは聴いてもクリームが聴けない理由かなと思います。
上記3アーチストがライヴで使用していたアンプはマーシャルスタックという、ピート・タウンゼントがとにかくデッカイ音を出すためにマーシャルに作らせたシステムでした。ロックの巨大化に対してのマーシャル社の貢献の大きさみたいなこともどなたか検証してもらえないでしょうか。

おとなだろ 勇気をだせよ

あの頃、忌野清志郎と ~ボスと私の40年/片岡 たまき
たぶん僕と同年代だと思う片岡たまきさんによる清志郎本を読みました。TV神奈川の番組で観たフォーク・バンドRCサクセションのボーカルに一目で心を奪われた中学生の女の子。そんないちファンの女の子がただひたすら清志郎一緒に働くことだけを夢にみて、見事にRCの衣装係となり、RCが事務所独立後はマネージャーとして常に清志郎の隣にいたというのだから、なんともファン冥利に尽きるたまきさんによる清志郎の回想録。
>これから先、清志郎に訊きたいことができても、自分で自分に訊いて答えを出さなければならない。そういうとき、自分の中の清志郎に訊くのだ。
だから清志郎はいるのだ。
たまきさんの場合は迷ったら直接に清志郎に訊くことが出来た。ぼくたちは直接に清志郎に訊くことはできなかったけれど、清志郎のいない今は”清志郎が生きていたらこの状況をどんなふうに歌にするのだろうか”とたまきさんと同じように「自分の中の清志郎」に訊いてみる。
「自分の中の清志郎」に訊くように、僕は時々「自分の中のジョン・レノン」に”もしジョンが生きていたら・・・”と訊いてみることもある。でも日本人以外の人たちはジョンに訊くことがあっても清志郎に訊くことはまず無いだろうと思う。それを思うと「自分の中の清志郎」を持っている僕たちはなんて倖せなんだろうとも思う。
キヨシく~ん。
忌野清志郎・空がまた暗くなる
おとなだろ 勇気をだせよ
おとなだろ しってるはずさ
入れ子ソングの元歌は その1
相変わらずブログの更新が滞っています。出張が増えてなかなかパソコンに向かう時間がないというかパソコンに向かっても集中力がなくなっているといいますか。集中力が無くなっているのは歳のせいでしょうか?
出張の車の中では普段はながら聴きしかできない、CDを大音量で聴くことができるのはいいんですけどね。で、曲にインスパイアされてブログのネタを思いつくことがあるのですが、運転中とあってメモとるわけにもいかず、仕事先に着いて車を降りるころにはどんなネタだったのか忘れています。どうやら記憶力も減退しているようです。
ということで今週の出張でもレココレ70年代アイドル特集の影響でキャンディーズ、南沙織、山口百恵のベスト、筒美京平の作品集などを聴いていて、中に異様にベースが表に出ている歌があって”なんじゃこりゃ”とネタに使おうと思ったのですが、どの曲だったか忘れてしまいました。
あの頃、忌野清志郎と ~ボスと私の40年/片岡 たまき
他にマネジャーのたまきさんの書いた清志郎本を読んでいたのでRCサクセションのベストも聴いていて思いついたネタ、こっちはしっかり憶えていたので今日はそのネタを。
まずはRCの名曲中の名曲である「スローバラード」をお聴きください。
スローバラード RCサクセション
昨日はクルマの 中で寝た あの娘と手をつないで
市営グランドの駐車場 二人で毛布にくるまって
カー ラジオから スローバラード
夜露が窓をつつんで、 悪い予感のかけらもないさ
この曲を聴くたびに思うのが、おそらくは僕だけじゃなく多くの方が思うと思いますが、夜の駐車場の車の中で彼女と体を寄せ合いながら聴いたスロー・バラードはなんという曲だったのかということです。この「スローバラード」だけじゃなくて歌の中に「歌」が出てくる歌ってままあるんですよね、で、そういった歌を聴くたびに「いったい何を聴いたんだろう」と思ってしまします。便宜的にそういう歌を「入れ子ソング」と呼ばせていただき、いくつか取り上げていきたいと思います。
「スロー・バラード」に関してはけっこうヒントが多いんですよね。ホーンがフィーチャーされたそのサウンド、清志郎の歌い方、そして上のライヴ映像でも歌いだしの前に出てくるあの”愛し合ってるか~い”というMC。
やっぱり、カーラジオで流れていたのはオーティス・レディングでしょうね。
そして曲は、月並みな気もしますがやっぱこれですかね「愛し続けて」。
Otis Redding, "I've Been Loving You Too Long"
RCには他にも「入れ子ソング」があります。
Sweet Soul Music - Strawberry Fields Forever / RCサクセション
Ah あの夜はじめて聴いた お前のナンバー
くちびるに くっついたまま そのまま.
Ah 陽焼けしたままの 二人の約束
くちびるに くっついたまま そのまま.
Baby Baby Now Sweet Soul Music あのいかれたナンバー.
Sweet Soul Music シートに しみ込んでる
おまえの匂い
他の女とは 区別がつくさ
もろスタックスなサウンドで歌われる「Sweet Soul Music あのいかれたナンバー」は何なのか?これは単純に考えるならばスタジオ・テイクの最後で一節を口ずさみネタ晴らしをしてるオーティスの「ドク・オブ・ザ・ベイ」ということになるのかな。
Otis Redding-Sittin' on the dock of the bay
ただ「スウィート・ソウル・ミュージック」と言えばアーサー・コンレイのそのものズバリのタイトルのナンバーがありますよね。
Arthur Conley - Sweet Soul Music
この歌自体が、ルー・ロウルズの「ラヴ・イズ・ハーティング・シング」、サム&デイヴの「ホールド・オン・アイム・カミン」、ウィルソン・ピケットの「ムスタング・サリー」、オーティス・レディングの「ファファファ」といった曲が入れ子になったスウィート・ソウル・ミュージック賛歌。この4曲のどれか、もしくは4曲すべてかも知れません。
実を言うとRCを聴いて最初に思い浮かべたのは上に出てきた中の一曲、オーティスの「ファファファ」でした。
Otis Redding Fa Fa Fa Fa Fa Sad Song)
♪ファファファファファファファ♪ってとこが”くちびるに くっついたまま”になりそうじゃないですか。
とりあえず、本日はここまで。
おまけ
「入れ子ソング」というと、最初に”へぇー、こういうのありなんだ”と思ったのはニール・ヤングの「ボロード・チューン "Borrowed Tune"」でした。
Borrowed Tune ~ Neil Young (1975)
borrowは「借りる」ですから「借り物の歌」というタイトルになります。
僕はこの借り物の歌を歌っている
ローリング・ストーンズから拝借したんだ
からっぽの部屋に独り
ネタ切れで曲が書けやしないから
最初聴いた時からどこかで聴いたことある曲だなぁと思っていたら、歌詞の中で”ストーンズから借りた”とネタ晴らしされています。その曲は「レディ・ジェーン」ですね。
The Rolling Stones/Lady Jane
しかし、一番驚いたのは「借り物の歌」と言いながらクレジットはニール・ヤングになっていること。いいのかそれで。
入れ子ソングの元歌は その2
さて入れ子ソングの元歌(っていう言い方は変ですか)探し第2弾。
今回はRC以上に多くの人の記憶に残っているであろうGAROの72年の大ヒット「学生街の喫茶店」です。
君とよくこの店に 来たものさ
わけもなく お茶を飲み話したよ
学生でにぎやかな この店の
片隅で聴いていた ボブ・ディラン
あの時の歌は聴こえない
人の姿も変ったよ
時は流れた
RCの場合と違ってこの歌で学生街の喫茶店でBGMに流れているのはボブ・ディランというところまで特定されています。あとはディランのなんという曲かということになrのですが。
ところで、当時僕は中学生だったのですが、恥ずかしながらボブ・ディランという名前をこの歌で初めて知った、否、意識したという記憶があります。たぶん同年代には同じような方多かったのではと思います。ひとつ言い訳しておきますと70年の『新しい夜明け』から73年の映画のOST『ビリー・ザ・キッド』までの間ってのは『グレイテスト・ヒットVol.2』を出したくらいで70を超えた今でも働き続けるディランの歴史の中でポッカリと穴の開いた期間で音専誌なんかの露出もなかった時期だったんですよね。ビリー・ザ・キッドの時は旬な監督サム・ペキンパーの映画に本人も出演し主題歌も歌うということで露出も多く、あぁディランってこんな顔の人なんだと思ったものでした。映画の役は「爆裂都市」の町蔵くらいにビミョーでしたが(笑)。
閑話休題、喫茶店でかかっていた曲です。
「学生街の喫茶店」というタイトル、”時は流れた”という歌詞からもお分かりのように、この歌は大学を卒業して社会人となった主人公が学生時代に恋人とよく来ていた喫茶店を訪ね今は別れてしまった恋人を思い出しノスタルジーに浸っている(失礼)、そんな歌です。学生時代というのはBGMとしてディランが引用されていることからも分かるように70年安保闘争で学生運動が盛り上がっていた60年代末のことです。そしてこの歌がヒットした72年といえば2月にあさま山荘事件とその後のリンチ殺人の発覚などがあり学生運動は後味悪くフェイドアウトしてしまいます。当時36歳、大人な作家、山上路夫がそんな時代の空気を歌詞にしたということでしょう。
ディランに関して言えば60年代末には反体制的ないわゆるプロティスト・ソングは歌っていません。というかそのパブリック・イメージに反してディランが主にプロティスト・ソングを歌っていたのは60年代の半ばくらいまでです。ただ60年代末の日本ではメッセージ性も強いフォーク・ミュージックが学生を中心に人気があり、ディランはそのルーツ的な存在として認識されており、今更ながらで60年代前半の「フォークの神様」時代のディランが評価されていたというのがあったと思われます。そしてこの時代のディランの評価=「フォークの神様」という、本来であればデビュー後数年間のイメージが、日本でのディランのパブリック・イメージになってしまったのが非常に残念なことに思えます。
まぁ、そういった事を踏まえた上で60年代末の学生街の喫茶店でかかっていたのは最も代表的な「風に吹かれて」あたりだったんじゃないでしょうか。
Blowing In The Wind (Live On TV, March 1963)
それとも、わずか数年間でディランの歌とは反対方向に”人の姿も変ったよ”という皮肉をこめて「時代は変わる」なんかだったら面白いんですが、それはないでしょうね。
Bob Dylan The Times They Are A Changin' 1964
60年代末に実際にヒットしていた「レイ・レディ・レイ」なんかだと、昔の恋人を思い出してる未練心にはぴったりなんですがね。
Lay Lady Lay (Bob Dylan) 45 RPM
おまけ
ボブ・ディランといえばニール・ヤングの「バンデット」の中にもその名前が引用されています。
Neil Young - Bandit (from Greendale)
No one can touch you now
But i can touch you now
You're invisible
You got too many secrets
Bob dylan said that
Somethin' like that
Someday You'll find
Everything you're looking for
PR: New Jeep Cherokee 試乗キャンペーン
今宵 豊穣の月の下で
中秋の名月。通勤途中にいつも聴いているBARAKAN MORNINGでアイズレー・ブラザースの「シャイン・オン・ハーヴェスト・ムーン“SHINE ON HARVEST MOON”」がかかっていた。
中秋の名月にあたる月は英語ではHarvest Moonになるらしい。それを聴きながら、”やっぱハーヴェスト・ムーン言うたらニール・ヤングでしょ”ということで次にニール・ヤングの「ハーヴェスト・ムーン」がかかるのを期待したのですが中秋の名月がらみはこの1曲のみでした。
ちょっと肩透かしをくらったので、帰ったら「ハーヴェスト・ムーン」をアップしたろと決めました。
そして帰り道、駅に着いて家に向かうBGMにFMをつけたらTFMのAORという番組がニール・ヤング特集をやっていました。なかなか奇特な番組じゃのーとニールの歌声を楽しみながら帰っていて家にたどり着こうかというタイミングで「ハーヴェスト・ムーン」のイントロ。夜空を振り返ると天高く真ん丸なお月様、出来過ぎやなぁこりゃ。
Neil Young / Harvest Moon
もう少しそばに寄りなよ
僕の想いを聞いておくれ
眠りについた子供のように
二人で朝まで夢をみようじゃないか
だけど 満月が満月が浮かんでる
光を浴びて踊ろうじゃないか
音楽だって聴こえてくる
おもてに出て夜に包まれよう
僕はいつだってきみを愛してるから
きみの踊る姿がみたいんだ
いつだってきみを愛してるから
今宵 豊穣の月の下で
見知らぬ同士だったころから
僕は遠くからきみを見ていた
そして恋人になり
心の限りきみを愛してる
夜も深まり
月は天高く
君の瞳で輝く月を
僕は祝福したいんだ
僕はいつだってきみを愛してるから
きみの踊る姿がみたいんだ
いつだってきみを愛してるから
今宵 豊穣の月の下で
この歌が発表される以前からニール・ヤングには何故か月のイメージがあったのですが、それってやっぱり「ヘルプレス」と映画「いちご白書」のせいなんでしょうね。
Helpless from Strawberry Statement
おまけ
「いちご白書」と言えばこの歌好きでした。
Thunderclap Newman Something In The Air
サンダー・クラップ・ニューマンの「サムシング・イン・ジ・エアー」。歌詞に”レヴォルーション”という言葉が出てきて、「いちご白書」にも挿入歌として使われたせいか邦題は「革命ロック」、うーん。
Compass Altitude Sport フェア: PR
BYE BYE BOBBY,BIG BOY DON'T CRY
大滝詠一/FUN×4
>フォー・シーズンズのサウンドをやろうと思ったのは『A Long Vacation』(81年)の中の「FUN×4」。これはご存知ビーチ・ボーイズの「Fun Fun Fun」よりももうひとつFUNが多いというアイデアから作ったものですが(笑)、あれはフォー・シーズンズ・サウンドをそのまま。中の間奏は,誰にも言わなかったけどビリー&リリーの「ラッキー・レディバッグ」っていう、フォー・シーズンズをやる前にボブ・クルーがプロデュースしてたグループの曲。そのホーンのサウンドを間奏に使ったわけ、わかる人には当然わかるわけで、フォー・シーズンズじゃなくて、フォー・シーズンズ以前にプロデュースしたグループのサウンドを使うことで、これはフォー・シーズンズへのトリビュートであるということを示した。
by大瀧詠一 fromレコードコレクターズ'92年3月号
Billy And Lillie / Lucky Ladybug
なるほど、フォー・シーズンズのサウンドにトリビュートした楽曲であることを示すためにわざわざ、プロデュサーのボブ・クルーが以前に手がけたグループのホーンを引用してヒントを与える一方で「FUN×4」などという、60年代前半フォー・シーズンズのライバルであったビーチ・ボーイズから引用したタイトルをつけるあたりは大瀧師匠の真骨頂といえるんじゃないでしょうか。
>僕は大瀧さんほどひねらないから、単細胞だから(笑)。うちのカミさん(竹内まりやさん)の『Variety』っていうアルバムに「もう一度」って曲が入ってるんですけど、それは完璧にフォー・シーズンズ以外の何物でもないという感じです。僕はもともと専門がコーラスなんで、ヴォーカル・グループとしてはフォー・シーズンズが好きだったし、譜面死ぬほどコピーしましたからね。<中略>だいたい複合リズムで曲を作ろうと思う時は、半分くらいフォー・シーズンズを意識して作ってるな。なぜかっていうと、リード対コーラスの対比がフォー・シーズンズって一番おもしろいんですよ。
by山下達郎 fromレコードコレクターズ'92年3月号
大瀧詠一、山下達郎という日本が誇る2大ポップ・マエストロに大きな影響を与えたというフォー・シーズンズですが、その楽曲の多くを作りプロデューサーでもあった、つまりはこの人がいなければフォー・シーズンズは存在しなかった、ボブ・クルーが9/11に亡くなりました。享年85歳。
ポップス・ファンとしてボブ・クルーという名前は勿論知っていましたけど、今回の訃報に際するまで写真を見たことありませんでしたが、まるでヴィスコンティの映画に出てきそうな2枚目だったことに驚きました。経歴をみると一時期俳優もやっていたみたいな記述も見受けられるのですが、さもありなんという感じです。
ボブ・クルーと言えばフォー・シーズンズとなるのですが、自身も歌手としてレコードを出したり、もちろんフォーシーズンズ以外でもヒットを生み出していました。米ウィキに記載されたボブによる作詞作曲/プロデュースで全米TOP40入りした楽曲リストは以下のようになります。
1957:The Rays "Silhouettes", #3.
1957:The Rays "Daddy Cool", #10.
1958:Billy&liliy "La Dee Dah", #9.
1959:Billy&Liliy "Lucky Ladybug", #14.
1962:Four Seasons "Sherry", #1
1962:Four Seasons "Big Girls Don't Cry", #1
1963:Four Seasons "Walk Like a Man, #1
1964:Four Seasons "Dawn (Go Away)", #3
1964:Four Seasons "Ronnie", #6
1964:Four Seasons "Navy Blue", #6
1964:Four Seasons "Rag Doll, #1
1964:Four Seasons "Save It For Me", #10
1964:Four Seasons "Big Man in Town", #20
1965:Four Seasons "Bye, Bye, Baby (Baby, Goodbye)", #12 ("Bye Bye Baby" on initial release)
1965:Four Seasons "Let's Hang On!", #3
1965:Herman's Hermits cover "Silhouettes," #5
1965:Four Seasons "Girl Come Running," #30
1965:Mitch Ryder & the Detroit Wheels "Jenny Take A Ride," #10
1966:Mitch Ryder & the Detroit Wheels "Devil With A Blue Dress On," #4
1966:Frankie Valli "The Sun Ain't Gonna Shine," #13
1967:Mitch Ryder & the Detroit Wheels "Sock It To Me, Baby," #6
1967:The Bob Crewe Generation "Music To Watch Girls By," #15
1967:Tremeloes cover "Silence Is Golden," #11
1967:Frankie Valli "Can't Take My Eyes Off Of You," #2
1967:Frankie Valli "I Make a Fool of Myself," #18
1967:Frankie Valli "To Give (The Reason I Live)," #29
1969:Oliver "Jean," #2
1969:Oliver "Good Morning, Starshine," #6
1974:Labelle "Lady Marmalade", #1
1974:Disco-Tex and the Sex-O-Lettes "Get Dancin'," #10
1975:Frankie Valli "Swearin' To God", #6
1975:Frankie Valli "My Eyes Adored You," #1
1975:Disco-Tex and the Sex-O-Lettes "I Wanna Dance Wit' Choo," #23
1975:The Osmonds cover "The Proud One," #22
2001:Christina Aguilera cover "Lady Marmalade", #1
素晴らしいですね。
フォーシーズンズ以外は聞いたことない曲も多いのですが、何曲か動画をアップしておきます。
The Rays - Silhouettes
The Rays Daddy Cool
ボブ・クルーの記念すべき1stヒットはNYの黒人ドゥーワップ・グループ、ザ・レイズに書いた「シルエット」という曲で後にストロベリー・アラームクロックを見出すフランク・スライJrとの共作で全米3位の大ヒット。この曲は後にハーマンズ・ハーミッツでも65年5位のこれまた大ヒットとなります。ボブ・ディランもお気に入りのようで、ザ・バンドとの地下室セッションで録音されながらずっとお蔵入りしたままでしたが、もうすぐ発売される『ベースメント・テープ・コンプリート』でようやくお目見えするようで楽しみです。
続く「ダディ・クール」も全米10位のヒット。「ダディ・クール」と言えば鈴木慶一がザ・ぼんちに提供した「恋のぼんちシート」の元ネタですね。ただ慶一さんの場合ザ・レイスのオリジナルではなく、77年にブリティッシュ・ドゥーワップ・バンド、ザ・ダーツによるカヴァー・ヒットが元ネタと思われます。とあるラジオ番組で「うなづきマーチ」はザ・ダーツのパクリと紹介されて以来、ずーっとこの曲ザ・ダーツがオリジナルと思っていたのですがザ・レイズだったんですね。
ザ・ぼんち / 恋のぼんちシート
ザ・レイズの後は冒頭で取り上げたビリー&リリィのヒットがあり、60年代に入るとザ・ロイヤル・ティーンズのメンバーで日本では「タモリ倶楽部」のOP曲として有名な「ショト・ショーツ」を共作していたボブ・ゴーディオと運命の出会いをします。二人のボブの初めてのコラボがゴーディオのグループ、フォー・シーズンズの「シェリー」でした。楽曲はゴーディオが作り、サウンド・プロデュースをクルーが行いチャーリー・カレロがアレンジを行う、鉄壁の3頭体制、否フランキー・ヴァリの声を加えて4頭体制のスタートでした。
Four Seasons Sherry Original Stereo
さてこの「シェリー」ですが、同時期にヒットしていたブルース・シャネルの「ヘイ・ベイビー」を聞いたゴーディオがインスピレーションを感じてわずか15分で書き上げたといわれます。
Bruce Channel - Hey! Baby
この曲で印象的なハーモニカを吹いてるのがデルバート・マクリントンで、62年にブルースが英国に演奏旅行に出かけた際に、共演したとある若いバンドのリーダーにデルバートはハーモニカを手ほどきします。そのリーダーは本来自分が歌うはずだったデビュー曲のリード・ヴォーカルをもう一人のヴォーカリストに譲り自分は覚えたてのハーモニカでバックをつけることになります。そうして出来上がったのがこの曲です。
Love me Do-The Beatles ' 62
繋がってますね。面白いもんです。
フランキー・ヴァリのファルセットをフィーチャーし一度聴いたら忘れられない「シェリー」は見事に全米NO1を獲得します。この成功を皮切りに「ビッグ・ガール・ドント・クライ」「ウォーク・ライク・ア・マン」と3曲連続でNO1を獲得しトップ・グループの地位を得ます。
THE 4 SEASONS - Big Girls Don't Cry (1962)
映画「テネシーズ・パートナー」という映画の中で顔を平手打ちされた主人公が”大人の女は泣かないのよ”というのを聞いて、曲想が閃きクルーと一緒に完成させたらしいのですが、歌詞はどうあれ曲調は完全に二匹目のどじょう狙いですね。安易だけど昔はこのパターンが多かったものです。
Dawn (go away) The Four Seasons
バディ・サルツマンのドコドコドコドコドコっていうドラムがいいなぁ、ビーチボーイズとフォーシーズンズのライバル関係は西のハル・ブレイン東のバディ・サルツマンの対決でもありました。
64年の1月に発売された「悲しき朝焼け」は山の手の女の子と下町の男の子という身分違いの恋を描いた歌詞といい、前面に出ていたフランキーのファルセットが少し引っ込みコーラス・グループとしての一体感が強く感じられる、新機軸を感じさせてくれる1曲で、くだんの3曲に勝るとも劣らぬ曲で1位は確実と思われたのですが結果は3位どまり。これまたビートルズと深い因縁があったようです、
録音されたものの販売元が決まっていなかった「シェリー」はフランキーの知己でヴィージェイ・レコードの西海岸の販売担当だったランディ・ウッドの口利きでヴィージェイから発売されることとなり、全米NO.1の大ヒットとなるのですが、なぜか正式な契約書は交わしていなかったようです。その後3曲連続No1という快挙を成し遂げトップ・グループとなったフォー・シーズンズはヴィージェイの待遇に不満を抱きレーベルを替わることにします。契約書はなかったものの裁判沙汰になったこともあり、63年の11月に録音されていた「悲しき朝焼け」はマーキュリーとの契約が決まる1月まで寝かされたままの状態になります。
これが不運を呼びます。
64年1月にアメリカの音楽業界で何が起こったか?もうお分かりですねビートルズ台風の上陸です。1月に発売された「悲しき朝焼け」はチャートを急上昇しますが最高位はビートルズの「抱きしめたい」と「シー・ラヴズ・ユー」に阻止され3週連続3位に終わってしまいます。
ところで思い出してほしいのは63年にイギリスではトップグループになっていたビートルズですが、発売元のEMIの子会社にあたる米キャピトルはEMIからの再三のオファーにもかかわらずビートルズのレコードを発売しようとはしませんでした。業を煮やしたブライアン・エプスタインはシカゴのインディーズであるヴィー・ジェイと契約して「プリーズ・プリーズ・ミー」を発売しています。63年には米国でまったく売れなかったビートルズですが64年1月のエド・サリバン・ショーで火が付きようやくキャピトルも重い腰をあげることとなり、ここでもヴィー・ジェイはトップ・バンドとの契約を打ち切られてしまいます。なんとも不運なレーベルです。
と言ったことをあらためて踏まえると、昔は”こんなパチモンみたいなレコード出しやがって、けしからん”と非難していたのが申し訳なくなってきます。
なんなんや「世紀の国際対決」いうのはと思っていたキャッチもやけっぱち感のなせる業だったんでしょうね。一番下の「審査してあなたの判決を」というのもなんやねんだったのですが、今回裏ジャケの写真を初めて見ることができて”なるほど、そういうことだったのね”と初めて理解しました。
このアルバム2枚組でビートルズの曲とフォー・シーズンズの曲が交互に収録されているのですが、1曲1曲をひとつのラウンドとみなしてラウンドごとのトータルポイントを10点として12ラウンドまでの合計点で勝者を決めるというものになっていたのです。一番下にはご丁寧に勝者のグループ名を記入する欄までついています。
「えぇい、もうどうにでもしやがれ・・・」という感じがしてしまいます。悔しくてたまらなったんだろうなあ。
ところでフォー・シーズンの1位を阻止した2曲のうち「シー・ラヴズ・ユー」についてはスワンというインディーズより発売されていたものですが、冒頭で紹介したビリー&リリィのシングルはスワンから発売されたものでした。ボブにとっては自分がかって働いたレコード会社に1位を阻止されたわけでこれまた不思議な因縁を感じてしまいます。
と、話がそれてしまいましたが、ほんといい曲ばかりです。ほんと残念です。R.I.P.
中途半端な終わり方ですが、気が向けばも少し続けます。
今夜 きみは僕のもの

ジェリー・ウェクスラーの伝記本「私はリズム&ブルースを創った」を通勤途中に読むにあたりBGMとしてアトランティックのソウルのコンピ「The Ultimate Soul collection」を聴いていたのですが、収録されているバーバラ・ルイスの「ベイビー・アイム・ユアーズ」を聴いていて、”あぁ、なるほど、そうだったのか”と膝をぴしゃり。この曲何度か聞いたことあったのに今の今まで気づいていませんでした、お恥ずかしい。
Barbara Lewis -- Baby, Im Yours
ベイビー 私はあなたのもの
星が空から落ちる日まで あなたのもの
川の水が乾いてしまう日まで
つまり 私が死ぬ日まで
ベイビー 私はあなたのもの
太陽が輝きをなくす日まで あなたのもの
詩人の韻が尽きる日まで
つまり 時の終わりがくる日までよ
私は ほら あなたのそばにいるわ
貴方の望むようにすべてを捧げるの
何物も私を自由にはできないの
いつだってあなたが私にささやきかけるから
ベイビー 私はあなたのもの
2たす2が3になる日まで
山が海へと沈む日まで
つまり 永遠にあなたのもの
ベイビー 私はあなたのもの
星が空から落ちる日まで
ベイビー 私はあなたのもの
川が乾いてしまう日まで
ベイビー 私はあなたのもの
詩人の韻が尽きる日まで
ベイビー 私はあなたのもの
ということで、頭にジャケットの画像を載せているのでお分かりかと思いますが、この曲は大瀧さんの「幸せな結末」の元ネタだったんですね。大瀧さんも曲の最後の方でちゃんと”Baby I'm Yours”と歌ってますしね。
大滝詠一/幸せな結末
大瀧さんのロマンチックな歌の中にさらにロマンチックな「Baby I'm yours」が入れ子になってるんですね。甘いわけだ。
DISCOVER JAPAN II/ERJ
「幸せな結末」は最近発売された鈴木雅之のニュー・アルバムにも松たか子とのデュエットで収録されています。このアルバムには「夜明け前の浜辺」も収録されており、マーチンの大瀧さんへのリスペクトが感じられるいいアルバムです。
鈴木雅之/幸せな結末
(「禁煙音頭」のレコーディングで)”ちょっと宇崎さんぽく歌ってくんない”って言われて”でも大瀧さん、音頭なんですよね”って言ったら、一言”あのね、音頭も立派なダンス・ミュージックだから”って言ったんですよ・・・
大瀧さんらしいですね。
禁煙音頭 DJ 達郎 サウンドストリート85
これまた入れ子がいっぱいですが、長くなるので割愛。
おまけ
20140712THE MUSIC DAY 音楽のちから(大瀧詠一名曲選)
PS.
ちょっと間違いがありました。
>大瀧さんも曲の最後の方でちゃんと”Baby I'm Yours”と歌ってますしね。
と書きましたが、”Baby I'm Yours”じゃなくて”Baby You're mine”ですね。女性からの”ベイビー私はあなたのものよ”というささやきに”ベイビーきみは僕のもの”と答えているというものですね。いわゆるアンサー・ソングのようなものと考えて良いのではと。
くだんのマーチンのアルバムでは松たか子とのデュエットで歌われているのですが、その最後は二人のかけあいみたいになっていてマーチンが”Baby You're mine”と歌い松が”Baby I'm Yours”と歌っています。正しい解釈ですね(笑)
ぴったりが選べる!mineoで簡単SIMデビュー!: PR
Baby,I Love You
Ronettes/Baby I love you
出張中の車の中で聴くためにカバンの中にCDを忍ばせるのですが、あれもこれもでけっこう重くなるのであらかじめMP3データーをCDに焼いてなんていうことをやったりしていました。今回カーナビにCDを入れながら、ふとカーナビのAUXジャックが目に入り、AUXにつなげばスマホの中の音源聴けんじゃないのと、早速ダイソーでピンコード買ってきてつないでみたら、当たり前ですが、聴けるじゃないですか。今までの苦労はなんだったんだ。
ということで昨日はスマホの中の音源から昨年正月のピーター・バラカンさんのウィークエンド・サンシャインの亀淵昭信さんがゲストの特番を聴いていました。番組の内容はロックンロール誕生からビートルズのアメリカ、日本登場の64年までの洋楽事情をお二人が薀蓄(これがすごい)を語りながら、曲を聴きながら、たどっていくというもの。
でビートルズの登場直前にアメリカで売れていたロネッツの「ベイビー・アイ・ラヴ・ユー」がかかるのですが、さんざん、50年代半ばから60年代前半の音楽を聴いてきた後にこの歌が流れた瞬間に思わずひとりごちてしまいました。
「革命や」
ぜんぜん違うんですよね、フィル・スペクターの音楽って、それ以前の音楽と。
Darlene Love - Christmas (Baby please come home)
乱暴に言ってしまえばそれまでの音楽はバック・トラックは単純に歌のバック・トラックでしかなかったものが、スペクターはバック・トラックこそが歌の主役といえるものに変えてしまいました。
楽曲をたんなる「歌」から「サウンド」に革命的に変えてしまったんです。これは後に英米で独自のサウンドを作り上げるビートルズとビーチボーイズの同時期の楽曲を聴けば「サウンド」の片鱗は感じられるもののやっぱり「歌」なんですよね。
スペクターの「サウンド」として楽曲を聴かせることにいちばん影響を受けたのはやはりブライアン・ウィルソンかもしれないですが、60年代後半のロックなんていうのは完全に「サウンド」主体ですから、ゼップやピンクフロイドなんかのルーツも考えようによってはスペクターだったといってよいのかもしれません。
ほんのちょっとでいいから ここに居ておくれ

ということで、最近のヘビー・ローテーションはミュージカル『ジャージー・ボーイズ』のサントラ。4か月ほど前にBOOK OFFの¥250コーナーで見つけたアルバムです。その時点ではもちろんこのミュージカルのことは知ってはいましたが、イーストウッド監督で映画化されていることは知らず、”さすがはブロードウェイ・ミュージカル、なかなかにフォーシーズンズっぽいですやん”くらいで一回聴いたくらいでCD棚の肥やしになりそうだったのですが・・・。
映画の公開を知り、作家でありプロデューサーであったボブ・クルーの逝去もあり、フォー・シーズンズのベストとともに棚から引っ張り出してヘビローとあいなったというわけです。
クレジットを確認するとミュージカル版でフランキー・ヴァリ役のジョン・ロイド・ヤングとボブ・ゴーディオ役のダニエル・リチャードはそのまま映画版でも同じ役柄を演じているようですね。
最初聴いたときは2曲目の「ジ・アーリ・イヤーズ」というメドレーの頭に「シルエット」という曲が歌われているのを聞いても「?」でしたが、ボブ・クルーを追悼するエントリーを書くためにいろいろ調べたおかげで、何故真っ先に「シルエット」が歌われるのかわかり、あらためてこのサントラを楽しむことができました。
音楽(だけではないですが)ってやつはいろいろ知識を得ることで楽しみが増えることが,
けっこうあります。
このアルバムにも収録されている「ステイ」。僕はこの曲、ジャクソン・ブラウンの77年のライヴ・アルバム『孤独なランナー』で初めて知りました。
JACKSON BROWNE STAY
途中でファルセットで歌われる部分があって、デヴィッド・リンドレーが歌っているのですが、ここでドッと受ける観客の声が記録されています。初めて聴いた当時はこれはリンドレーがウケを狙って女の子のような裏声で歌い、そのルックスとのギャップにお客がウケていると思っていました。
「ステイ」と言えばホリーズが歌っているのを聴いていて、ホリーズ・バージョンにはウラ声が出てこないのでそう思ったのでした。
THE HOLLIES- "STAY"
それが、後にフォー・シーズンズのベスト2枚組を買い、そこに収録されているオリジナル(?)バージョンを聴いて「なるほど、そういうことだったのね」と得心したのでした。
The Four Seasons - Stay (Stereo)
ジャクソン・ブラウンのライヴで聞ける観客の感嘆の声はフォーシーズンの看板であるフランキー・ヴァリのファルセットを真似ているリンドレーに対する賞賛だったのかと。それほどにフォーシーズンズ、フランキー・ヴァリの歌声は世代を超えて愛されているんだと納得したのでした。
ところが、全米16位となったフォーシーズンズ・バージョンも実はカバーで1960年に全米NO.1となったモーリス・ウィリアムスとゾディアックスのものが本当のオリジナルだということを知りました。しかし、当時は今みたいに、知らない曲があったらYOUTUBEで検索してすぐ聴くなんてできませんし、フォーシーズンズがカバーの際にアレンジしたものと信じて疑っていませんでした。何故って、フランキー・ヴァリと言えば「ウラ声」っていうのが鉄板(昔はこんな言い方はありませんでしたけど)でしたから。
で、それからまた数年たってたまたまラジオでゾディアックスの「ステイ」を聴く機会がきます。
Stay-Maurice Williams and the Zodiacs-original song-1960
なんと、オリジナルですでにウラ声が使われているじゃあーりませんか、目から鱗。
思えば、フォーシーズンズの「ステイ」も発売当初は「ピーナッツ」のB面に収録された曲でした。カバーだしおまけでB面にというところでしょう。でも、この「ピーナッツ」が正直たいした曲じゃなかったこともあってかDJはシングルをひっくり返してB面の「ステイ」ばかりをかけてたらしいのです。おそらくは
”さぁ次はおなじみフォーシーズンズの新曲だ。みんなは3年前のNO1「ステイ」を覚えているかい。モーリス・ウィリアムスとゾディアックス、楽しかったデートの夜、門限を忘れてもうちょっとだけいてくれっていう、みんなも経験あるだろ。モーリスのウラ声がせつなかったよな。でもウラ声と言えば今はフランキーだ!じゃぁ行ってみよう、フォーシーズンズで「ステイ」!!”
ってな具合でかけやすかったんじゃないかと想像します。
ラジオでB面の「ステイ」の方ががんがんオン・エアされるのを聴いたヴィージェイはすぐさま「ステイ」をA面にしたシングルを出し直し、見事スマッシュ・ヒット。まだまだDJがヒットを生み出せるいい時代だったということか、オールデイズ・バット・グッドデイズです。
というわけで、リンドレーのウラ声はフランキーもあるかもしれませんが、オリジナルのゾディアックスのウラ声も踏まえていて、そのことを一世代から二世代下の若い観客も理解した上での歓声だったということに思いいたりました。
たんなるウケ狙いじゃなくちゃんと歴史を踏まえている、そう思って聞くとリンドレーの歌声がさらに味わい深く聴こえてきませんか。
ゾディアックのオリジナルの尺はわずか1分50秒。TOP10ヒッツの中では最も短い曲なんだとか。3分どころか2分間にも満たないマジック溢れるナンバー、いやぁ音楽って本当にいいですね。
おまけ ジャージー・ボーイズ・バージョンを最後に。
Cast of Jersey Boys London sing "Can't Take My Eyes Off You", "Stay" & December 1963"



