虫の知らせだったというべきなのでしょうか?レノン/マッカートニーの楽曲を管理する出版社ノーザンソングスについての記事を書いた直後に5人目のビートルズと言われたジョージ・マーティンが帰らぬ人となり、今度はめぐりめぐってマイケル・ジャクソンとソニー・ミュージックが共同で所有していたレノン/マッカートニー楽曲が100%ソニー・ミュージックのものになるというニュースが飛び込んできました。
>マイケル・ジャクソンの負債とうとうゼロに。ソニー・ミュージックが出版社におけるマイケルのビートルズ楽曲の持ち分を7億5000万ドルで購入へ。
記事はコチラから→Michael Jackson Debt-Free At Last: Sony Music Buying His Part of Beatles Catalog, Publishing Company for $750 Mil
記事によれば、ソニー・ミュージックはソニー/ATVの株式でマイケル一族が保持していた分を7億5000万ドル(約840億円)で買収することになったようです。これによりマイケル一族は莫大な借金をすべて返済でき、一方のソニー・ミュージックは旧「ノーザン・ソングス」に登録されていたレノン/マッカートニーの楽曲すべてを所有することとなります。
本来であれば作者自身、レノンは亡くなっているのでヨーコとポール・マッカートニーが所有するというのが望ましいのでしょうが、もはや両家の財産では買い戻せないほどその価値が大きくなっていることもありソニーが所有というのもいたしかたないことかと思います。
まぁ投機目的で音楽と無関係な会社に買収されるよりは音楽業界のメジャーであるソニー・ミュージックが持っていた方がベターかとは思います。日本の会社が持っているかと思うとちょっぴり誇らしい気もしますしね。
ノーザンソングスその後
魔法かけてくれた天使が ここにいるんだよ

DEBUT AGAIN(初回生産限定盤)/SMR
¥3,240
Amazon.co.jp
3/21、ナイアガラの元旦ともいえるサンニーイチの朝、今日も『デビュー・アゲン』から。
このアルバムってほらね
いつかみていたゆめが
今日はかなうといいな
そんなことがおこりそうだよ
ほんとほんとだよ
ほんとにおこっちゃった
そんなアルバムなのかも、そして
きのう見つけた時計
今もチクタク動く
続いているよずっと前から
そしてこれからも
NHKのソングスのマーチンの言葉じゃないけど
いるね、ここに 大瀧さん
魔法かけてくれた天使が
ここにいるんだよ
ここにいるんだよ
いつもまってるよ。
ほんと、うれしい予感がほんとになった。
さくらももこさんの詞はうれしい預言だったのか?
PS.ネットで亡くなった大瀧さんの音源をかってに使ってニュー・アルバムだなんてなんだかなぁみたいな意見を散見いたしましたが、そんな小さいこといわずに大滝詠一、大瀧詠一フアンであれば買うべきアルバム、損するよ。大瀧さんいるんだから。
祝! 「ビートルズと日本」熱狂の記録 出版!!

→「ビートルズと日本」熱狂の記録 ~新聞、テレビ、週刊誌、ラジオが伝えた「ビートルズ現象」のすべて/シンコーミュージック Amazon.co.jp
会社の同僚、大村亨さん(いうても僕より年下です)によるビートルズ本が出ます。大村亨という名をご存知ない方もいらっしゃるかも知れませんが、レコード・コレクターズの「マジカル・ミステリー・ツアー」特集の時の、日本放映時の放送事故(リールの放映順を間違えた)についての記事や、最近では日本盤のCD-BOXが発売された時のビートルズ・ヘアを売りにした床屋さんの記事を書いた人と言えば、あーっあの人かと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。大村さんの記事の特徴は国会図書館などに足しげく通いとにかくビートルズについて書かれた音楽雑誌、週刊誌、女性誌、新聞、スポーツ新聞などありとあらゆる記事、一次文献を徹底的に読破し(新聞30万ページ、スポーツ新聞37万ページ!、週刊誌115万ページ!サバ読むなコノヤロー(笑)、でも大げさじゃないようです)、記憶ではなく記録から当時の日本でビートルズという存在がどのように受用され影響を与えていたのかを追及していくところにあると思われます。
宣伝資料に書かれた内容を引用してみますと。
☆日本滞在を時間単位で追った完全ドキュメント
☆新聞30万ページ、スポーツ新聞37万ページ、週刊誌115万ページを徹底分析
☆"記憶"ではなく"記録"から浮かび上がる当時の真相
☆ビートルズの激レア写真&グッズが満載!
☆ビートルズに最初に会った日本人は?
☆日本のラジオで最初にビートルズがかかったのはいつ?
☆ホントは65年に来日する予定だった? 幻の日本公演計画のすべて
☆来日公演より前に海外でビートルズのライヴを見た日本人
☆ビートルズ展の写真に失神! 女性ファンたちの熱狂
☆武道館公演のチケットは実は余っていた?
☆中高生の大半がビートルズを嫌っていた?
☆こんな人も日本公演を観に来ていた
☆ホテルに芸者? 日本公演終了後、夜の出来事
☆ファンにプレゼントされたサイン入りキャデラック
☆来日の翌年には人気収束?「国民的フィーバー」の後日談
☆ホントはいつ出た? 日本盤発売日の謎等々……
音楽は音楽として聴けばいいのであって、その音楽の周辺事情は関係ないとおっしゃる純粋音楽主義者の方もいらっしゃるのかも知れませんが、個人的には大学で米国文化史なんていうのを先行専攻していたこともあり音楽の文化的側面に非常に興味があったります。そのあたりは「鳥肌音楽」を読んでいただいている方にはお分かりのことかもしれませんね。というか楽器も弾けない音痴なので純粋に音楽を語れないというか、ぶっちゃけるとゴシップ好きのところがあるので「中高生の大半がビートルズを嫌っていた?」なんていう章立てをみると読む前からワクワクしちゃっています。
僕もよくやっちゃうんですけど、ある音楽について、その音楽が流行っていた当時の状況を体験していない若い人に「アレは〇〇ですよね」とかコメントでつっこまれると、「いやいやあなたは当時をしらないから〇〇というが、あの頃を経験したオレ様から言わせると××である」みたいなことをやっちゃうことがあります。でも実際は記憶って曖昧だったり、後付けで作っちゃうこともままあるんですよね。だから記憶から書かれる音楽論なんていうのも大切だけど記録から書かれるこういう新しいビートルズ本も必要だし、この本はこれ以降のビートルズ研究(日本の)に少なからぬ影響を与えていくんじゃないかなとも思います。
と実際に本を読む前から絶賛してしまい、お前大村さんからサンプル本もらって提灯記事書いてるんだろうと思われそうですが、大村さんいわくサンプル本はないそうなのでちゃんとお店で購入いたします。冗談はさておきビートルズのファンであれば本棚に置いておいてく価値のある一冊だと思いますよ。
レココレ関連でもうひとつインフォを。長期連載されている宮永正隆さんのビートルズ来日学 が6月に単行本になるようです。こちらは来日時にビートルズに接した様々な方々に当時の写真を見せ乍ら記憶を語っていただくというもの。来日50年という記念の年にふさわしい一冊だと思います。
ビートルズ来日学 1966年、来日時の4人に接した日本人関係者の証言(仮)/DU BOOKS
¥2,700
Amazon.co.jp
PS.出版記念として4月の2日3日にトーク・イベントも開かれるようです。
→書籍『「ビートルズと日本」熱狂の記録 ~新聞、テレビ、週刊誌、ラジオが伝えた「ビートルズ現象」のすべて』発売記念イベントが4月に開催
東京なので行けませんが、大村さん頑張ってしゃべってね。
意外!? 1966年に最も売れていたミュージシャンは?
The Wrecking Crewのfacebook毎日チェックしているいるのですが、毎週火曜日(米時間)には「火曜日のトリヴィア」ということでレッキング・クルーに関連したクイズが出されます。今週のお題は1966年に最も売れていたミュージシャンは誰?というものでした。
以下は、その答えとして本日アップされていたものです。
Here's the question and the answer to yesterday's "Trivia Tuesday" post:
According to Billboard, which of these acts total album sales topped The Beatles in the year 1966.
A.) The Monkees
B.) The Beach Boys
C.) The Mamas & the Papas
D.) Sonny & Cher
E.) Herb Alpert and the Tijuana Brass
Answer-E.) Herb Alpert and the TJB. In 1966 they sold over 13 million albums, and had 5 albums in the Top 20 at the same time, and 4 of those in the Top 10.
Herb Alpert & The Tijuana Brass - Spanish Flea
(ハーブ・アルパートの名は知らなくても誰もが知ってるメロディですね)
いやぁ意外でした、1966年ビートルズ以外で一番売れていたのはハーブ・アルパートだったとは。てっきりモンキーズあたりかなと思ったのですが。
いきなりですが、私いまだにハーブ・アルパートなのかハープなのかハーブなのか、アルパートなのかアルバードなのか迷ってしまいます。
余談はさておきアルバムが1300万以上の売上ってホンマか?と少しだけ調べてみました。
以下は1966年のビルボードで1位になったアルバムを順に並べたものです。
Herb Alpert's Tijuana Brass /Whipped Cream and Other Delights dagger
The Beatles /Rubber Soul (6weeks)
Herb Alpert's Tijuana Brass /Whipped Cream and Other Delights dagger
Herb Alpert and His Tijuana Brass /Going Places
Barry Sadler /Ballads of The Green Berets SSgt. (5weeks)
Herb Alpert and His Tijuana Brass /Going Places (5weeks)
The Mamas & the Papas /If You Can Believe Your Eyes and Ears
Herb Alpert and the Tijuana Brass /What Now My Love (8weeks)
Frank Sinatra /Strangers in the Night
The Beatles/ Yesterday and Today(5weeks)
The Supremes /Supremes A' Go-Go (2weeks)
Soundtrack /Dr. Zhivago
The Monkees /The Monkees (8weeks)
"Bittersweet Samba" Herb Alpert & The Tijuana Brass
(66年の曲ではありませんが、こちらも誰もが知っているメロディーですね)
確かにハーブ・アルパートが何度もランキングしています。年間トータルでの1位獲得週をみると
ハーブ・アルパート16週
ビートルズ11週
モンキーズ8週
バリー・サドラー5週
シュープリームス2週
ママス&パパス
フランク・シナトラ
ドクトル・ジバゴ・サントラ各1週
ハーブ・アルパートが断トツですね。しかも『Whipped Cream and Other Delights dagger』 は『Rubber Soul』 の6週を挟んで1位に返り咲き、『Going Places』もバリ・サドラー軍曹の『Ballads of The Green Berets SSgt』の5週 (これが5週1位というのもすごいなぁ)を挟んで1位に返り咲きということで、1位から落ちている期間も1位に準ずる売上だったということになるわけで、『What Now My Love』までの28週は常に上位に何かのアルバムがあったということになるんだと思われます。 確かに(アメリカにおいては)1966年はビートルズでもなく、ビーチボーイズでもなく、モータウンでもなく、ハーブ・アルパートの年であったといってもいいかもしれませんね、実に興味深い。
SSG Barry Sadler - The Ballad Of The Green Berets (1966)
普段からロックばかし聴いていることもあって、60年代半ばなんてもう世間ではロックががんがん流れていて、サマー・オブ・ラヴにつながっていくなんて思っちゃうんですが、チャートで見る限りハーブ・アルパート、バリー・サドラー、フランク・シナトラ、ドクトル・ジバゴと非ロック的な歌手が計23週、年の約半分1位だったわけです。
そういった「保守的」なリスナーに「安心してください入ってますよ」と「イエスタデイ」(上記の『Yesterday&today』に収録)や「イン・マイ・ライフ」(『Rubber Soul』収録)や「エリナー・リグビー」のような「保守的」なリスナーにも受け入れられる曲を提示して解放していったのもビートルズ、さらに言えば「保守的」なリスナーに近い年齢のジョージ・マーティンだったのでしょうね。
YESTERDAY
Whipped Cream & Other Delights/Herb Alpert Presents
¥1,455
Amazon.co.jp
Very Best Of Herb/A&m
¥2,549
Amazon.co.jp
Rubber Soul (the U.S. Album)/Capitol
¥1,940
Amazon.co.jp
Yesterday & Today (the U.S. Album)/Capitol
¥1,940
Amazon.co.jp
Ballads of the Green Berets/Real Gone Music (US)
¥1,696
Amazon.co.jp
LUCY IN LONDON って知ってます?

上の写真のおばさんが誰だかお分かりになるでしょうか?
アメリカ人であればおそらくほとんどの人が知っているだろうし、日本人でも50代半ば以上の人であれば「あぁ、あの人」と思いだす人もいらっしゃるでしょう。1963年5月4日から1966年10月1日まで4シリーズにわたってTBS系列で放映されたシットコム「ルーシー・ショーThe Lucy Show」の主人公ルーシー・カーマイケルことルシール・ボールLucille Ballです。
とにかくアメリカではルーシーさん、すごい人気だったようで最初はアメリカCBSテレビで1951年10月から「アイ・ラブ・ルーシーI Love Lucy」としてスタートして57年まで続く人気ドラマとなり、その後、設定や構成を変えながら「ルーシー・デジ・コメディ・アワーThe Lucy-Desi Comedy Hour」(1957年~1960年)、「ルーシー・ショーThe Lucy Show」(1962年~1968年)、「陽気なルーシー Here's Lucy」(1968年~1974年)と足かけ20年以上にわたりお茶の間を笑わせ続けたといいます。
そういえば映画「カプリコン1」の中でアポロ11号の時は全米が生中継を観ていたが、今やロケットが月に行ってもみんな「アイ・ラブ・ルーシー」の再放送の方を観ているといった意味のセリフがありましたが、その位に人気があったということだと思います。
ルーシー人気が盛り上がっていた66年に「ルーシー・イン・ロンドンLucy In London」というスペシャル版が作られています。66年のロンドンと言えばスウィンギング・ロンドン華やかなりし時代でドラマの中でも当時のロンドンの風俗が盛り込まれていたようです。特別ゲストとしてディブ・クラーク5も登場して「ロンドン橋」を歌ったりもしています。ドラマのエンディングにはヒップな衣装のルーシーと若者たちの踊るシーンが用意されバックには「ルーシー・イン・ロンドン」というこの特番のためのエンディング曲が流されています。
ということで今日の本題はこの「ルーシー・イン・ロンドン」という楽曲、僕もとあるfacebookでたまたま知ったのですが、おそらくご存知の方少ないんじゃないかと思われる曲なのですが、聴けば誰が制作しているのかはすぐに分かっちゃうんじゃないかと思います。曲もなのですが誰が歌っているのかも、お分かりになるでしょうか?
1分7秒あたりから曲が始まります。
お分かりになりましたでしょうか?この分厚い団子になった音、いわゆる「音の壁Wall Of Sound」というやつですね。そうフィル・スペクターの手による楽曲で、歌っているのもなんとフィル・スペクター自身ということなのです。もともとテディー・ベアーズというコーラス・グループの一員だったスペクターなので歌える人なのでしょうが、なんでまた自分が歌う気になったのでしょうか?
「ルーシー・イン・ロンドン」は未CD化かと思われるので、聴こうと思えば特別編「ルーシー・イン・ロンドン」が収録されたDVDのBOXを買うしかないようです。なんとかCDにしてくれないものでしょうか。
おそらくは、そのDVDから録ったと思われる少し音のいい動画がありましたのでアップしときます。なかなかの大作かと思います。
いやぁ知らなかった・・・
マイク・ラヴの消失 ~なぜなら俺は、ビーチ・ボーズのメンバーその一だからだ

上の写真を見て何か違和感を覚えないでしょうか?ビーチボーイズの『ペット・サウンズ』のジャケット写真のアウト・テイクなのですがブライアンとデニスの間が不自然に空いているし、メンバーがひいふうみー・・・4人しかいない。
マイク・ラヴが消えている。
写真は能地祐子さんがブライアン・ウィルソンの「ペット・サウンズ・ツアー」のパンフに掲載されていたものとしてツイートしたものです。
→ノージ・アゲインスト・ザ・マシーン
>【いない速報】大将、ツアーパンフからマイクを消してる?件。いない!いないよ(;∀;)【神かくし動物園】
> ていうか、逆に消さないとあちらから請求書来るとか?ブルースははなからいないのでいいとしても(´・ω・`)
"消さないとあちらから請求書来るとか?"とかいうのがまんざら冗談にも思えないのが笑えないことなのですが、いずれにせよこの写真はいただけないなぁと思います。
「記憶」っていうのは恣意的に美化されたり、無意識のうちに上書きされたりしてしまいます。過去を引きずらずに人が生きて行く上ではそういう書き換えのようなことは必要な時もあるんだとは思いますので100%否定はしません。
しかしながら、写真や書籍といったものは「記録」です。「記憶」が間違った方向に書き換えられて行こうとするときに、その舵を修正し正しい方向にしてくれるのが「記録」だと思います。
「記録」に嘘をつかせてはダメなんだと思います。
今回の写真はマイク・ラヴの存在が消えたためにできた空間がかえってマイク・ラヴの存在を思い出させてくれるという面もあります。それは僕がビーチ・ボーイズを、マククとブライアンの関係をいくばくかでも知っているからそう感じるのであって、ビーチ・ボーイズのことを知らない人がこの写真を見れば4人のビーチ・ボーズがデフォルトになっちゃうかもしれない。悲しくて、恐ろしいことだと思う。
ペット・サウンズ(MONO & STEREO) +1/ユニバーサル ミュージック
¥1,851
Amazon.co.jp
ペット・サウンズ<50周年記念スーパー・デラックス・エディション>(初回生産限定盤)(Blu-.../ユニバーサル ミュージック
¥10,800
Amazon.co.jp
ペット・サウンズ<50周年記念デラックス・エディション>/ユニバーサル ミュージック
¥3,888
Amazon.co.jp
故意のめまい 誤字じゃないです
昨日より岡山・広島にに出張中です。久々に車で高速を走るので、何をBGMにしたろかと考えていて「高速」から浮かんだのがバックマン・ターナー・オーバードライブBachman Turner Overdriveの「ハイウェイをぶっ飛ばせRoll Down The Highway」。そこで家にあるBTOのベスト盤などなどを棚からひとつかみして出張へ。
Greatest Hits/Polygram Int’l
¥2,549 Amazon.co.jp
「ハイウェイをぶっ飛ばせ」「仕事にご用心」「恋のめまい」などのいかにも北米的なおおらかなロックでヒットを飛ばしていたのですが、日本だけなのかどうかは知りませんがキャッチフレーズは「きこり軍団」。このころは「蠍軍団」とか「地獄の軍団」とか「猿の軍団」とか「軍団」がブームだったんですかね。
まぁたしかにランディ・バックマンやC.F.ターナーというひげ面の巨漢がフロントマンでしたから、カナダ出身ということとあいまって「きこり」とあだ名されるのはいいとしても、本によっては「きこり出身のロック・バンド」とまで書かれているあったとの記憶があります。前身のゲス・フー時代には「アメリカン・ウーマン」という全米NO.1のヒットももつバックマンに対して「きこり出身」とはさすがに失礼だろうと今だから思いますが当時は・・・。
BTOがヒットしていた時期は僕が中学だったころで全米NO1にもなった「恋のめまいYou Ain't Seen Nothing Yet 」はラジオからもよく流れていました。当時は前身のゲス・フーのこともよく知らなかったのですが、高校に入りアメリカン・ロックなんかも聞き出すようになり前述の「アメリカン・ウーマン」も初めて聞いたりもしました。
で、そのときに思い出したのが「恋のめまい」で、あぁそういえばあの曲歌いだしで♪アメリカーン・ウーマン シー・プット・ア・ハードウェイ♪とか言ってたな、そうか自分の過去の大ヒットのタイトルを引用してファンの気を引いたんだなと思いました。それから40年間、時々「恋のめまい」を聞くことがあるとついつい「アメリカン・ウーマン」の入ったゲス・フーのベストを引っ張り出したりしていました、いわゆるシナジー効果ってやつですね。
で、昨日車で「恋のめまい」を聞いた後、なにげにスマホで歌詞を検索してびっくりぽん。「アメリカン・ウーマン」なんてぜんぜんうたってませんやん。
I met a devil woman
She took my heart away
おれは悪魔のような女に会った
俺の心はいちころさ
♪アメリカーン・ウーマン シー・プット・ア・ハードウェイ♪なんてぜんぜん言っていない、なんという聞き取り能力の低さ、まったくお恥ずかしい。
っていうかあたまの部分はどっちかっていうと「空耳アワー」に出してもおかしくないような歌い方だと思うのですが、どうでしょう。そう思って自分を慰めることにします。
アイコン~ベスト・オブ・バックマン・ターナー・オーバードライブ/バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ
¥1,132
Amazon.co.jp
ベスト・オブ・ゲス・フー/ゲス・フー
¥1,944
Amazon.co.jp
最後に笑ったのはジョージ・ハリスン

→元記事はコチラから
「最初の100日間のストリーミングで急上昇するビートルズ」
ザ・ビートルズが時の試練に耐えうるということの証明が必要なら、スポティファイ(Spotify)のデータをチェックすればいい。
偶像的なブリティッシュ・バンドのストリーミング・サービスがスタートしてちょうど100日となります。CNETの報告によればストリーミング回数は最近のポップ・スター、例えばシアやエド・シーラン、アリアナ・グランデといった人たちを上回っています。注目してほしいのはこれらのアーチストたちはビートルズが解散した1970年には生まれてすらいないということです。
ビートルズはストリーミング・サービスで毎月650万人のリスナーを獲得していて、その67%は35歳以下のリスナーです。
バンドは自分たちの楽曲をストリーミングすることを許可していませんでしたが昨年のクリスマス・イヴに大手のストリーミング・サービス、スポティファイ、アップル、グーグル・プレイ、タイダルそしてパンドラからリリースを開始しました。
スポティファイによればビートルズの楽曲で最もストリーミングされたのは「ヒア・カムズ・ザ・サン」で「カム・トゥゲザー」「レット・イット・ビー」「イエスタデイ」と続きます。
メキシコ・シテイの住人によるストリーミングが最も多く、ロンドン、サンティアゴ(チリ)、ロサンゼルスと続いています。
ジョージ・ハリスンの「ヒア・カムズ・ザ・サン」がストリーミングの1位。67%パーセントが35歳以下、ビートルズ解散時には影も形もないリスナーが中心。ビートルズ・ストーリーなんてほとんど知らずに楽曲単位で音楽に接しているリスナーが大部分のランキングですから、ビートルズ・ストーリー、それは大部分がレノン=マッカートニーのストーリーでもある、が頭にこびりついてる僕のような世代のランキングとは変わってくるのは当たり前なのかなとも思います。
確かに前知識なく聴いたとしても「ヒア・カムズ・ザ・サン」の優しいアコースティックな響きは万人受けするでしょうからね。ただそれでいくと2位の「カム・トゥゲザー」はちょっと解せない気もしてしまいますが・・・、アクーティック・モンキーズとかカバーが多いからかな。
このスポティファイの報告を受けてショービズ411というウエッブにこんな記事が載っていました。

→元記事はコチラから
「最後に笑ったのはジョージ・ハリスン。スポティファイで「ヒア・カムズ・ザ・サン」が最も親しまれたビートルズ・ソングに」
これは因果応報というべきか。
スポティファイにおいて一番ストリーミングされたビートルズの楽曲はジョージ・ハリスンの「ヒア・カムズ・ザ・サン」でした。アルバム『アビーロード』からのクラシック・ソングはビートルズのストリーミング開始からのわずかな期間に1800万回以上も再生されました。
次点には「イエスタデイ」「カム・トゥゲザー」「レット・イット・ビー」「ヘイ・ジュード」「抱きしめたい」が並びます。
トップ4のアルバムは『1』(ベスト・アルバム)、『アビー・ロード』『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』そして『レット・イット・ビー』。
最も重要とされる『サージェント・ペパーズ』とその収録曲が上位にないのが興味深くはないでしょうか。私は驚きました。
アルバムの中に十分な楽曲が収録されないことにハリスンは欲求不満を抱いていました。最終的には量を質が凌駕することとなりました、「サムシング」「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」「ヒア・カムズ・ザ・サン」、ビートルズのレパートリーの中でも際立っています。
やったぜジョージ!
記事を書いたロジャー・フリードマンさんはきっとジョージのファンなんでしょうね。おもいっきり溜飲を下げている感じが読み取れます(笑)。とはいえ、好き嫌いがはっきり分かれるだろうインド音楽風の楽曲をのぞけば中期以前でも「タックスマン」「アイ・ウォント・トゥ・テル・ユー」「嘘つき女」「恋をするなら」など数は少ないけどいい曲書いているし「ヒア・カムズ・ザ・サン」と「サムシング」についてはレノン=マッカートニーでもそうそう書けない名曲ですしね。
例えばビートルズ誕生から100年後の2062年、ビートルズ・ソングで一番人気があるのは何か、なんてことも思ったりします。そのころにはAIが人間を支配していて、音楽理論上最も破たんのない楽曲(って何なのかは分かりませんが)が1位になってたりしたら嫌だなぁ。
Abbey Road (Dig)/Beatles
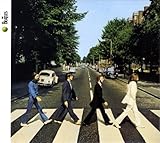
¥2,575
Amazon.co.jp
White Album (Dig)/Beatles

¥4,036
Amazon.co.jp
Let It Be (Dig)/Beatles

¥2,645
Amazon.co.jp
オールタイム・ベスト/ジョージ・ハリスン

¥2,600
Amazon.co.jp
Every Breath You Take(あら 見てたのね)
音専誌MOJOによる「Top 10 Song Meanings Everyone Gets Wrong」っていう動画がアップされていました「歌の意味が間違って理解されている楽曲トップ10」ってな感じでしょうか。
お前が息づかいのそのたびに
お前が動くそのたびに
お前が絆を破るそのたびに
お前が歩くそのたびに
いつも俺はお前を見ているよ
いつだって
お前の話すそのたびに
お前の駆け引きするそのたびに
お前が家をあけるそのたびに
いつも俺はお前を見ているよ
2位のポリス「見つめていたいEvery Breath You take」は、言葉の分からない日本ではほとんどの人がラヴ・ソングと思っているのでしょうが、英語が母国語であっても勘違いが多いようですね。本当は当時の嫁さんと離婚訴訟をやってたスティングが相手に何かアラがないかと監視していた時の気持ちを元にしてできた歌でラヴ・ソングでもなんでもないようです。ただし、とりようによっては振られた相手をあきらめきれない男の歌という風な勘違いもあるだろうなぁってことでスティングは誤解を嘆くのではなくむしろ面白がっていたということです。
1位のスプリングスティーンの「ボーン・イン・ザ・USA」、この歌の内容を簡単に言えば、アメリカのためにベトナムで命をかけて戦った帰還兵が、戦後アメリカに戻ると差別され職にもありつけやしない、兄貴は俺以上に悲惨でベトナムでイエローに殺されたが英雄にもなれない、そういうアメリカに俺は生まれたというアメリカの行う戦争を皮肉った歌なのですが、発売当時レーガンの選挙活動のテーマ的な歌として無断借用されてしまったといういわくつきの歌である。
スプリングスティーンはレーガン事務所に使用をやめるように抗議し、次作の『ネブラスカ』のツアーでは生ギターの弾き語りの陰鬱なバージョンで「ボーン・イン・ザ・USA」を歌います。
確かに、こちらのバージョンの方がスプリングスティーンの皮肉は伝わりやすいのでしょうが、歌の表現としては「俺は(こんな)アメリカに生まれた」という皮肉をこぶしを振り上げて歌うような最初のバージョンの方が歌の表現としては面白いと思います。というか生ギター・バージョンだと「皮肉」じゃなくて、そのまんまという気もします。たしか元々、この曲を作った時には生ギター・バージョンに近かったが、これでは面白くないということで発表されたロック・バージョンにしたみたいなことだったと何かで読んだ気がしますが、まさか一国の大統領(優秀な(?)ブレーンも含め)が見事に勘違いしてしまうとは想像できなかったのでしょうね。
まさに事実は小説よりも奇なりです。
さて最近の日本でも「勘違い」した歌の使い方だと一部の人から攻撃された歌があります。
そうです、4月1日2日限定で放映された赤城乳業による「ガリガリ君」値上げに謝罪するCMで使用された高田渡の「値上げ」です。
ネットでの感想では「ひねりがきいた面白いCM」とか「値上げも仕方ないとワロタ」とか「歌が面白い」「高田渡をこんな風に使うか、やられた」といった内容のものが大半をしめ、値上げをすることでイメージが悪くなることをさけるために作られたであろうCMは成功だったと思われます。
ただ、高田渡に思い入れが深いファンの中には面白く思われなかった人も少なからずいたようで「あれは値上げする側の歌じゃなくて、政治経済に翻弄される生活者の歌のはずだ」という怒りのコメントも見かけた。
たしかに、そういう気持ちは分かるのだがあまりにも「純粋」すぎるというか、このCMの仕掛け人はそういった批判も刷り込みの上であえて高田渡を使っている。それは勘違いではなく、値上げの歌詞(ちなみに歌詞は高田渡ではなく詩人の有馬敲)を言葉のまま受け取り素直に謝罪ととる人、歌詞から「皮肉」を感じる今の世の中への批判と面白がる人、高田渡がCMに使われることを許せない批判する人、そんな人がいることを計算づくで使っている。巧妙なのである。ついでに言えば4月1日の赤城乳業の値上げは「ガリガリ君」だけではなくすべてのアイスにおよんでいて高額のものはもちろん10円なんてものではない値上げをしているのである。
高田渡の歌を使うのがけしからんと言っても、はっきり言って赤城乳業はいたくもかゆくもないんだと思う、そんなことは刷り込み済みだし、そういってくるのは「ガリガリ君」をもともと食べないじいさんばっかりだろって見切られている。
だからこそ、僕は高田渡の歌の本来の意味を知ってほしいのであれば、逆にこの機を利用しなければいけないのだと思う。今回のCMで「値上げ」という歌を、高田渡という存在が何十万いやひょっとしたら何百万いたかということを考えるべきだと思う。中には「面白い」だけで終わる人もいるだろうが、「いやこの歌は実は深い意味がありそうだ」「高田渡という人は何物なんだ」と思った人は少なからず存在するはずである、そういった人たちに高田渡を知ってもらうことこそやるべきことではないかと僕は思う。それは、少なくとも「あんなCMみて面白がって高田渡を聴きたいと思うやつに、高田渡が分かるわけがない」とか「リアルタイムで高田渡が生きた時代を知らないやつには高田渡が分かるわけがない」なんて高田渡を自分だけの高田渡にするよりも何倍も健全だと思う。
今、「値上げ」で検索すると下のようなものが出てきます。
僕の思う「高田渡」像からすると、こういう継承のされ方が最もふさわしいんじゃないかなと思います。
その歌はみんなが知ってる。
誰でも知ってる。
だけど誰がその歌をつくったのか、
最初に誰が唄ったのかは、
誰も知る人はいない。
ただ歌だけが今も流れている。
歌い手にとって、まさにそれは理想である。
何十年かあとに僕の曲がどこかで流れいて、
曲名も僕の名前も誰も知らないのだけれど、
その曲だけはみんなが知っているとしたら・・・・。
想像しただけでもわくわくする。
そこまでなれたらシンガー冥利に
つきるというものだ。
(自伝 バーボン・ストリート・ブルースより)
PS.前半を書いているうちに、ちょっと前から胸につかえていたガリガリ君のCMの件が頭に浮かんでつなげて強い待ったので、ちょっと無理やりな文章になってしまいました。
こんなとこにデヴィッド・クロスビー
あの温厚そうなグレアム・ナッシュまでが「もう我慢できない」と長年の友人関係を破棄し絶交状をたたきつけたというニュースが最近あり、「何やってんだデヴィッド・クロスビー」と思っていたのですが、今度はとんでもないとこで名前が出てきました。
アンジェリナ・ジョリーがブラッド・ピットにDNA検査を要求
By TellychakkarTeam
女優のアンジェリナ・ジョリーは夫であるブラッド・ピットに歌手メリッサ・エスリッジの子供たちの父親でないことを証明するためにDNA検査を受けるよう要求しています。
オーストラリアのトークショーにおいてエスリッジは過去に彼女とパートナーだったジュリー・サイファーのためのための精子提供者としてブラッド・ピットのことを検討していたことを明かしました。
結局エスリッジは歌手のデヴィッド・クロスビーから精子の提供を受け、現在10代のベイリーとベケットが生まれました。しかしジョリーはエスリッジの子供たちの本当の父親がブラッド・ピットではないかと疑っています。
「アンジーは問題を解決するためブラッドに検査を受けさせようとしていますが、ブラッドはアンジーは誇大妄想だと言っている」アメリカのタブロイドは報じます。
報道によれば”有害な(マレフィセント)”女優(アンジーのこと)は夫にDNA検査を受けないのなら、メリッサののところに押しかけ片をつけるわと警告しているとのことです。
もちろん、ブラッド・ピットとアンジェリナ・ジョリーというトップスターのスキャンダルなので報じられているのですが、音楽ファンとしてはここで出てくるかデヴィッド・クロスビーという気持ち。不謹慎な話題とはなりますが、ブラッド・ピットのようなイケメンを精子のドナーとして考えるのは気持ちとして分かりますが、その代わりとしてデヴィッド・クロスビーだったってことですよね。まぁ確かに才能という点では素晴らしいものもお持ちなの、メリッサ・エスリッジも歌手として自分たちの子供も歌手にしたいと思ったのでデヴィッドだったのかとも思いますが、ゲスの極みの感想としては見た目の落差ありすぎですやん。
しかしアメリカではこんな風に有名人がドナーになっていることが多いのでしょうか、それもすごいことだなぁと思ってしまったニュースでした。
謎ときはディナーの後で
久々にクイズをひとつ。
以下にアップした13のヒット曲ですが、ある共通点があります。
それは何かお分かりになるでしょうか?
アドリブス/ボーイ・フロム・ニューヨーク・シティ
ルイ・アームストロング/この素晴らしき世界
バングルス/ウォーク・ライク・エジプシャン
シェリー・フェブレー/ジョニー・エンジェル
ハプニングス/シー・ユー・イン・セプテンバー
エルトン・ジョン/ダニエル
レッド・ツェッペリン/天国への階段
ジョン・レノン/イマジン
ピーター&ゴードン/アイ・ゴー・トゥー・ ピーセズ
ピーター・ポール&マリー/悲しみのジェットプレーン
ローリング・ストーンズ/ルビー・チューズデイ
フランク・シナトラ/ニューヨーク・ニューヨーク
ゾンビーズ/シーズ・ノット・ゼア
あなたの代わりなんて いないから
15日と7時間が経ってしまった
あなたが別れをつげてから
夜ごとふらつき 昼間はベッドの中
あなたが別れをつげてから
あなたがいないから 自由に過ごせる
誰とだって会える
おしゃれなレストランでディナーだって
だけど 何をやったって
何をやったって ブルーな気分
だって あなたの代わりはいないから
あなたに代わるものなんて
あなたがいなくてとても寂しい
歌を忘れた小鳥みたい
涙が流れるのをとめることもできない
何が間違っていたの
周りの男に抱きしめてもらうことは簡単だけど
あなたを思いだすだけ
医者にいったら言われたの
お嬢さん何でもいいから楽しんでおやりなさい
馬鹿じゃないの
あなたの代わりなんているわけないのに
あなたがママのために植えた
裏庭の花も
みんな枯れてしまった
あなたと暮らすのは大変な時もあった
だけど今はもう一度一緒にいたいの
あなたの代わりなんて
あなたの代わりなんて いないから
あなたの代わりなんて
あなたの代わりなんて いないから
NOTHING COMPARES 2 u, Prince. R.I.P.
ヘイ ヘイ ヘイ ショウヘイ
コネタで。
GWです。今日は娘たちも予定がなかったので家族みんなでドライヴにというスケジュールだったのですが、GW直前に二女が職場の階段から落ちて靭帯を伸ばしてしまい松葉づえ生活に。仕方ないので予定を変更して家族でカラオケに。
祖母も一緒なので娘たちも気を使って昭和歌謡中心に歌ってくれていました。二女がフィンガー5の「学園天国」を入れたのでイントロのコール・アンド・レスポンスのとこを”ヘイ ヘイ ヘイ ショーヘイ”ってCOWCOWのネタをやって思いっきり引かれたりしていたのですが、途中のハーモニカによる間奏(1分27秒あたりから)を聴きながらこれってアレですやんと思っちゃいました。
何がアレかというと、このハーモニカの雰囲気ってスティーヴィー・ワンダーがまだリトル・スティーヴィー・ワンダーだった頃の大ヒット「フィンガーティップスPart1&2」ですやん。
そうか、フィンガー5やからフィンガーつながりで「フィンガーティップス」とは、なかなかに憎いアレンジですやん、誰?と思いググったら井上忠夫さんでした、さすがは大ちゃん。
「学園天国」も「フィンガーティップス」も有名曲なので、きっと誰か2曲の関連についてブログとかに書いてるんちゃうかと思い検索したのですが、なんと出てきたのが10年前の鳥肌音楽のエントリ「恋の呪文」でした。
>「子供相手に子供だましは通用しない」という阿久/都倉俊一の哲学で作られた「個人授業」からしてイントロからファズを効かせたギターで始まるロックだし、「恋のダイヤル6700」は強烈なブラスの入ったR&B、ベースは誰だ。小泉今日子がリバイバルさせた「学園天国」ではいきなりのコール&レスポンス途中のブレイクのハーモニカはスティビーワンダー(フィンガー・ティップス!?)の引用か。「バンプ天国」なんていうそのもズバリのソウルナンバーもありました。
と「フィンガーティップス」の引用までは気づいてるのですが、”フィンガー”つながりの必然的な引用であることに、まったく気づいていないですね。なんとも情けない奴。
そんなわけでいろいろ「学園天国」について調べていて初めて知ったのですがイントロのコール・アンド・レスポンスの「ヘイ ヘイ ヘイ ショーヘーイ」はゲイリー・US・ボンズの「ニュー・オリンズ」からの引用だったようです。
ということで、引用にもある「子供相手に子供だましは通用しない」という哲学に大ちゃんがしっかりと応えていることをあらためて気がつきました。アメリカン・ポップスに精通した人が聴けば、おっゲイリー・US・ボンズにスティーヴィー・ワンダーかおぬしなかなかやるのーっていうプロの仕事ですね。
ところでこの「ニューオリンズ」を聴いていると歌の部分って、ビーチ・ボーイズが『パーティ!』でカバーしていたリヴィングトンズThe Rivingtonsの「パパ・ウム・モウ・モウPapa Oom Mow Mow」そのままと思いませんか?
ゲイリー&USボンズを今回初めて聴いてリヴィングトンズをカバーしたんだと思ったのですが実際はゲイリー・US・ボンズが先の60年発売で全米6位の大ヒット、対して「パパ・ウム・モウ・モウ」は62年で全米48位という小ヒット。分からんもんです。ついでに書いてしまうと「パパ・ウム・モウ・モウ」が小ヒットしたのでリヴィングトンズはアルバムに「バーズ・ザ・ワールドThe Bird's The World」というほとんど同じメロディで歌詞だけ変えた曲を入れちゃってるのですがこの曲を下敷きにして作られたのが、最高にパンキッシュなサーフィン・ナンバー、トラッシュメンの「サーフィン・バード」というわけです。
The Bird's The World - The Rivingtons (45s)
The Trashmen - Surfin Bird
「サーフィン・バード」の最後に「パパ・ウム・モウ・モウ」も出てきていてこの3曲が同じであるネタ晴らしみたいになっていますね。ちなみに「サーフィン・バード」は全米4位という大ヒットになっています。それにしても「ニューオリンズ」から「サーフィン・バード」へと時代は新しくなっている分けで、普通は洗練された楽曲になっていきそうなところなんですが、むしろ劣化してっているような感じがしちゃいませんか。
アメリカン・ポップス業界のこういういい加減なとこけっこう好きだったりします。
The Beach Boys - Papa-Oom-Mow-Mow (Party! Sessions Mix/Audio)
それにしてもトラッシュメン=屑屋ってバンド名は人を喰った名前です。
ゴールデン☆ベスト フィンガー5/ユニバーサル インターナショナル
¥2,037
Amazon.co.jp
Very Best of - Original Legrand Masters/Varese Sarabande
¥1,421
Amazon.co.jp
Tube City-Best of/Sundazed Music Inc.
¥2,182
Amazon.co.jp
Beach Boys’ Party! Uncovered &/Capitol
¥2,594
Amazon.co.jp
いざゆけ 遙か希望の丘を越えて Over the Hills and Far Away
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
丘を越えて行こうよ
真澄の空は 朗らかに晴れて
楽しい心
鳴るは胸の血潮よ
讃えよ わが青春を
いざゆけ 遙か希望の丘を越えて
丘を越えて行こうよ
小春の空は 麗らかに澄みて
嬉しい心
湧くは胸の泉よ
讃えよ わが青春を
いざ聞け 遠く希望の鐘は鳴るよ 作詞:島田芳文、作曲:古賀政男
「サーフィン・バード」と山田邦子の共通点とは

先日のエントリで「アメリカン・ポップス業界のこういういい加減なとこけっこう好きだったりします。」と書いたのですが、その後でトラッシュメンのこと調べているといろいろと面白いことが分かってきましたので、徒然なるがままに書いてみたいと思います。
先日ご紹介したサーフィン・バンドである彼らの名前を一躍有名にしたのは全米4位という大ヒットとなった「サーフィン・バード」です。ちなみにトラッシュメンの出身地は先頃亡くなったプリンスと同じミネアポリス。ということで海のない土地の「まがい物」サーフィン・バンドです(笑)。
The Trashmen/Surfin' Bird
写真をアップしたベスト・アルバムでこの曲の作家クレジットを見るとFrazier-White-Wilson-Russellとなっています。
これは前回書いた「サーフィン・バード」の元ネタであるリヴィングトンズの「パパ・ウム・モウ・モウ」のクレジットCarl White, Al Frazier, Sonny Harris, Turner Wilson Jr.に準じたものとなっています。当り前ですねどう聞いても同じ曲ですから。連名のうちSonny Harrisの名前が消えて「サーフィン・バード」ではRussellという名前が登場しているのはHarrisとRussellが作詞担当だったからと思われます。曲は同じだけど歌詞、といえるかどうかは置いといて、は違ってますからね。
RIVINGTONS - PAPA OOM MOW MOW
すこし本題からそれちゃいますが。62年にリバティ・レコードから発売された、この「パパ・ウム・モウ・モウ」は48位の小ヒットとなりますが、それに気をよくしたのか2匹目のドジョウを狙ってリヴィングトンズは「ママ・ウム・モウ・モウMAMA OOM MOW MOW 」という曲をシングルで発表しています。
RIVINGTONS - MAMA OOM MOW MOW
こちらもクレジットはCarl White-Al Frazier-Sonny Harris-Turner Wilson Jr.というリヴィングトンズのメンバー4人。ヒットが出た後は同じ路線でというのはよくあるのですが、ほとんど替え歌ですからね。
ところでこの「パパ・ウム・モウ・モウ」という変なタイトルはどういう意味なのか?歌詞の中ではこの「パパ・ウム・モウ・モウ」のことを”これまで聞いた中で最もへんな響き(Funniest sound I ever heard)”で全く理解できないが”今や国中にこれが広まってる(And now it's spreadin' all over the land)”と歌われていて、どうやら意味のない言葉のようにも感じます。
The Bird Is The Word by the Rivingtons 1963
ただ、前回も書きましたがリヴィングトンズはこの曲の後で、トラッシュメンの「サーフィン・バード」というタイトルに直截的つながるであろう、これまた替え歌的な「バーズ・ザ・ワードBird's The Word」(前回はBird's The Worldと書いたのですがWordが正しいみたいです)という曲を発表し、「パパ・ウム・モウ・モウ」「ママ・ウム・モウ・モウ」そして「バーズ・ザ・ワード」の3曲を収録したアルバム『ドゥーイン・ザ・バードDoin' The Bird』を発表しています。
”鳥をやろうぜ”っていうタイトルなるかと思うのですが、どういうこと?
ここで思いだしたのが映画「ブルース・ブラザース」に出てきたレイ・チャールズ御大が歌う「シェイク・ア・テイル・フェザーShake A Tail Feather」のこと。
元々は63年のファイヴ・デュ‐トーンズThe Five Du-Tonesのダンス・ナンバーのカバーなのですが、映画の群舞シーンのために加えられた歌詞ではかって流行したダンス・スタイルが読み込まれています。
Do the twist
Do the fly
Do the swim
And do the bird
Well do the duck
Do the monkey
Watootsie
タイトルも「尾羽を振れ」、そうです当時「バード」というダンス・スタイルがアメリカで流行っていてそのために作られたのが「シェイク・ア・テイル・フェザー」であり、リヴィングトンズのアルバムもタイトルにしてもデザインにしても「バード」を踊るためのダンス・ナンバー・アルバムとして制作されたと考えられます。
それを証明するかのようにシングル「バーズ・ザ・ワード」のピクチャースリーヴの裏面には「バード」の踊り方らしきものが写真入りで説明されています。
で、あらためてアルバムのジャケを見返すと、ヒット・ナンバーとして他の収録曲よりフォントも大きくかつ白抜きの文字でフェーチャーされている「パパ・ウム・モウ・モウ」と「ママ・ウム・モウ・モウ」の上にはシルクハットを被った雄鶏と髪飾りをつけた雌鶏のイラストが配されています。このことから考えると、この2曲ももともとは「バード」ダンスのために作られていたであろうことが想像できます。
では「パパ・ウム・モウ・モウ」というタイトルと「バード」ダンスには何か関係があるのかとという本題に戻ります?ですが、ここからは完全に推測となります。R&Rエラの前から現在にいたるまで西欧にはチキン・ダンスというダンスが広まっているようです。それはこんなものみたいです。
大の大人たちが子供みたいにはしゃぎまくっていますね。この「チキン・ダンス」がどれほど西欧社会で浸透しているかは検索中に偶然見つけた下のビヨンセのコンサートの動画を見ればおわかりいただけるのではと思います。
しっとりと歌っていたのにいきなりチキン・ダンス、このパフォーマンスを日本でやったとしたら「何?ビヨンセおかしくなっちゃったんじゃないの」となることは間違いなく、笑いを取るどころか思いっきり引かれてしまうでしょうね。
「チキン・ダンス」についてウィキには次のように記述されています。
The "Chicken Dance," also known as the Birdie Song or the Chicken Song, is an oom-pah song and its associated fad dance is now a contemporary dance throughout the Western world. The song was composed by accordion (Handharmonika) player Werner Thomas from Davos, Switzerland, in the 1950s.
「バーディー・ソングもしくはチキン・ソングとしても知られているチキン・ダンスは、ウム・パー・ソング(oom-pah song)です」という一文にひっかかってしまいました。「ウム・パー・ソング」って何だ、これまたウィキではこう書かれていました。
Oom-pah, Oompah or Umpapa is the rhythmical sound of a deep brass instrument in a band, a form of background ostinato.
どうやらブラス・バンドによるリズミカルはナンバーのことのようです。具体的にどんなの?ってYOUTUBEで探してみるとAnsambel Slovenski Zvoki というウム・パーの代表的なバンドの演奏がみつかりました。
Ansambel Slovenski zvoki - Venček Avsenikovih
なんかゴンチチの「世界の快適音楽」みたいないなってきましたが、実はOom-pahで検索するといちばん最初にヒットするのはこの動画です。
68年のミュージカル映画「オリバー」の中のワン・シーンです。映画「オリバー」はもともとはディケンズの小説「オリバー・ツイスト」を原作にして60年にイギリスで上演された大ヒット・ミュージカル「オリバー」が元になっていて、この「オリバー」の中の楽曲は日本でも親しまれていたようで、こんな動画も見つかりました。
ウンパッパ/杉並児童合唱団
今日は、話がどんどんそれていって申し訳ないのですが、この杉並児童合唱団が歌うのを聴いていて連想したのは邦ちゃんのひょうきん絵描き歌です。というか絵描き歌ってだいたいウンパッパーウンパッパーですよね。ルーツはこんなとこにあったんですね。
オレたちひょうきん族 ひょうきん絵描き歌1
すみません、話を戻すとこのウンパッパー先のウィキの引用でみると「Oom-pah, Oompah or Umpapa」という風に同じような音でいろいろな表記があるようです。うん、まてよこのOom-pahやUmpapaとPapa Oomってなんか似てる気がしませんか?ちょっと無理矢理のこじつけかもしれませんが「Papa Oom Mow Mow」っていうタイトルは「Oom-Pah」をもじって作られたものではないか、そう妄想していまいました。
「サーフィン・バード」と「ひょうきん絵描き歌」はルーツを辿ると同じ歌だったということになるんじゃないかと(笑)。って今回書きたかったのはそんなことじゃなくって・・・。
「サーフィン・バード」の作者クレジットは「パパ・ウム・モウ・モウ」と同じと最初に書きましたが、実は発売された当初のクレジットは違ったものでした。
ちょっと見辛いかもしれませんがスティーヴ・ワーラー(Steve Wharer)というトラッシュメンのリード・ボーカルの名前が作者としてクレジットされています。これがリヴィングトンズの関係者のめにとまり、どう聞いても同じだろということでリヴィングトンズから訴えられて、クレジットを変えさせられたということがあったようです。
と、まぁここで終わっていれば、しょうがねぇ奴らだなトラッシュメンくらいで終わるとこなのですが、さらなるエピソードがあるのはここからです。(やっとホントの本題です)。
トラッシュメンは「サーフィン・バード」の大ヒットの2匹目のどじょうを狙って同じくバードものの新曲「バード・ダンス・ビート」を発表します。
Bird Dance Beat - The Trashmen
「サーフィン・バード」が全米4位という特大ヒットでしたので、そこには到底及びませんがそれでも30位に上るスマッシュ・ヒットになっています。この曲だけを聴けば「パパ・ウム・モウ・モウ」と似てるかなくらいかも知れませんが、間に「バーズ・ザ・ワード」と「サーフィン・バード」をかませばほとんど同じ歌と思えてしまいます。ですから作者クレジットはリヴィングトンズのメンバーの名前になるかと思いきやクレジットがG.ギャレット(G.Garret)となっているのです。この名前もちろんリヴィングトンズのメンバーではなくトラッシュメンの発売元であるギャレット・レコードを主宰しプロデューサー、エンジニアでもあるジョージ・ギャレットのことと思われます。
ジョージ・ギャレットが「サーフィン・バード」のクレジットでもめて結果として印税をごっそりもっていかれた苦い経験をしながら、ふたたび「パパ・ウム・モウ・モウ」を下敷きにしたような「バード・ダンス・ビート」を発表したのは、元々48位どまりだった「パパ・ウム・モウ・モウ」のメロディをヒットさせたのはトラッシュメンによる激しいアレンジが故だという自負があり、あえてパクリと言われないぎりぎりのところまで似せたということではないのか。
いずれにせよギャレットというクレジットだとトラッシュメンには印税が入らないわけで、結局トラッシュメンはバードならぬトンビに油揚げをさらわれちゃったことになるような気がしてクズ拾いすらできなかったんじゃないかと心配になるのでした。
PS.途中「ひょうきん絵描き歌」が出てきたついでに最後に書いておきますが、日本にも「パパ・ウム・モウ・モウ」の替え歌(?)を作ってしまった奇特なお方がいらっしゃいます。もちろん大瀧詠一大先生ですね。
うなずきトリオ/うなずきマーチ
イノセンスの喪失
"All Summer Long" by The Beach Boys was recorded on this date May 6, 1964 at United Western Recorders in Hollywood. The song was written and produced by Brian Wilson. Chuck Britz was the engineer. It was from their album of the same name.
The personnel on the track were:
Al Jardine – harmony and backing vocals; electric bass guitar
Mike Love – lead and bass vocals
Brian Wilson – harmony and backing vocals; xylophones or marimba; producer
Carl Wilson – harmony and backing vocals; electric rhythm guitars
Dennis Wilson – harmony and backing vocals, drums
Steve Douglas – tenor saxophone
Jay Migliori – piccolo or fife The Wrecking Crewのfacebookより
1964年のこの日、5月6日(米時間)にビーチボーイズの「終わりなき夏」を歌った永遠の名曲「オール・サマー・ロング」が録音されました。僕の中ではこの「All Summer Long」と大滝さんの「A Long Vacation」は対になるタイトルに思えてなりません。
君の家の前に車を停め いちゃいちゃしてて
コークで君のブラウスを
ビショビショにしちゃったのを思いだすよ
Tシャツにカット・オフ・ジーンズに革のサンダル
夏の間 僕らは思いっきり楽しんだ
夏の間 君とずっと一緒だったけど
僕はまだ君のすべてを分かっちゃいない
甘酸っぱい夏の思い出を歌った歌詞はマイク・ラヴ。ビーチボーイズにとってマイクの書く詞ってのは、10代の男の子にとってのTシャツやカット・オフ・ジーンズや革のサンダルみたいなもの。素肌にぴったりくるのです。
力の抜けたマイク・ラヴのリード・ボーカルもいい感じ。マイク・ラヴが脱力して歌うと、デニス・ウィルソンが上手に歌ったように聞こえるのが面白いところ。
しかし、この曲のバックトラックもビーチボーイズのメンバーによるものだったとは、だからよけいにビーチボーイズらしい「夏」の香りがするのかも知れません。
「オール・サマー・ロング」といえば、映画「アメリカン・グラフィティ」のエンディングで印象的に流れていました。映画の舞台が1962年の地方都市で「オール・サマー・ロング」は64年の楽曲ということで時代考証がとなっちゃうとこですが、劇中じゃなくエンド・ロールで、しかも登場人物たちのその後が提示された後に流れてくるというのは、流石はルーカス狙っているなぁという感じでした。
「イノセンスの喪失」、ブライアンにとっても永遠のテーマですもんね。
謎ときはディナーの後で 答え合わせ

プリンスの急逝もあって、すっかり放置状態にしてしまっていた4月21日のクイズの解答です。
問題は以下の13のヒット曲に共通することは何か?というものでした。
アドリブス/ボーイ・フロム・ニューヨーク・シティ
ルイ・アームストロング/この素晴らしき世界
バングルス/ウォーク・ライク・エジプシャン
シェリー・フェブレー/ジョニー・エンジェル
ハプニングス/シー・ユー・イン・セプテンバー
エルトン・ジョン/ダニエル
レッド・ツェッペリン/天国への階段
ジョン・レノン/イマジン
ピーター&ゴードン/アイ・ゴー・トゥー・ ピーセズ
ピーター・ポール&マリー/悲しみのジェットプレーン
ローリング・ストーンズ/ルビー・チューズデイ
フランク・シナトラ/ニューヨーク・ニューヨーク
ゾンビーズ/シーズ・ノット・ゼア
耕作さんから「放送禁止になった歌」という回答がありました。それでもあたっているのですが、何故放送禁止になっちゃったかということをお答えいただきたかった。この13曲に共通することは、もう上に写真をアップしちゃってるのでお分かりでしょうが2001/9/11の全米同時多発テロ事件の後で全米で放送禁止となった歌だったということです。正確に言うならば全米の1300余のラジオ局を統括するクリア・チャネルが事件後に「国民感情」を考えオン・エアーは控えた方がよい「自粛」の対象とした楽曲リストのほんの一部です。
>クリア・チャネル
米国の巨大メディア企業。何故か日本では意外にも無名。1300以上のラジオ局と30以上のケーブルテレビ局、米国最大のチケット発券企業(ぴあのような)の支配者。屋外広告看板では70万枚以上、コンサートホールも100以上と世界最大。中国やオーストラリア、ニュージーランドにも積極的に進出している。
以前の標語は「あなたの目にはいるものは全てクリアチャネルから」と言った。2001年に独占禁止法に問われたが、あっさりクリア。メディア・エンターテイメント業界に大変強い影響力を持つ。 (Hatena Keywordより)
何故オン・エアーを自粛すべきなのか詳しい理由は書かれていないのですが、勝手に想像させていただくと。
アドリブス/ボーイ・フロム・ニューヨーク・シティ
ニューヨークから逃げてきた少年みたいなことなのでしょうか、基本的に「ニューヨーク」がタイトルに入っているものはNGっぽいです。
ルイ・アームストロング/この素晴らしき世界
”なんて素晴らしい世界なんだろう”っていうのは脳天気ってことでしょうか。歌詞の「空は青く」とか「空にはとてもきれいな虹がかかり」っていうのもひっかかったか。
バングルス/ウォーク・ライク・エジプシャン
テロの首謀者とされるアルカイダがムスリムということで、同じムスリムであるエジプト人がタイトルにはいっているからアウトなんでしょう。
シェリー・フェブレー/ジョニー・エンジェル
この曲がなんでダメなのか、うーん。しいて挙げるなら”Every time he says hello
My heart begins to fly(「やぁ」ってあなたが言うたびに 空をも飛べる気持ちになるの
)、”together we will see how lovely heaven can be(私たち二人でいれば素敵な天国にいられるの)という歌詞なのかな・・・。
ハプニングス/シー・ユー・イン・セプテンバー
”9月に会いましょう”と臨んだ相手は9月にはいなくなってしまった。
エルトン・ジョン/ダニエル
”ダニエルは今夜飛行機でスペインに向かい旅立つ””あぁダニエル 僕にとってにいさんは空に瞬く星”という歌詞がアウトか。
レッド・ツェッペリン/天国への階段
”天国への階段”っていうタイトルだけでアウトでしょうね。
ジョン・レノン/イマジン
この曲が「放送禁止」になったというのは日本でもニュースになりましたね。宗教なんてないとか国境なんてないというのが問題だったのかはたまた”地面の下に地獄なんて無いし 僕たちの上には ただ空があるだけ”っていう歌詞がアウトだったのか。ちなみにフォークランドの時ははっきりと「厭戦気分」を煽る歌とされて禁止だった記憶があります。
ピーター&ゴードン/アイ・ゴー・トゥー・ ピーセズ
失恋で身も心もバラバラな気分という歌なのですが、バラバラ(go to Pieces)という言葉がダメなんでしょう。
ピーター・ポール&マリー/悲しみのジェットプレーン
”僕はジェット機で去っていく”というのがアウトなんでしょう。オリジナルのジョン・デンバーにその意識があったかどうかは分かりませんが、この曲をヒットさせたPP&Mは大切な人と離れ”いつ戻れるか分からない”ところへ行くという歌詞にベトナム戦争への反戦の思いを嗅ぎ取っていたと思います。
ローリング・ストーンズ/ルビー・チューズデイ
ここまで見てくれば、こちらも予想がつくのじゃないかと思われますが、そう2001/9/11は火曜日でした。
フランク・シナトラ/ニューヨーク・ニューヨーク
ことさらに「ニューヨーク」が強調されていて思いだすだろうってことでしょうか。
ゾンビーズ/シーズ・ノット・ゼア
”あの娘はそこにはいない”うーん確かに恋人や娘や母親を失くした人はいたのでしょうが・・・・
オン・エアーを自粛しなければいけないという理由が分かる気もするものもありますが、どう考えても行き過ぎなのではと思えるものもあります。この件についてはいろんな問題があるかと思いますが、考えがまとまっていないので今日は触れませんがひとつだけ書いときます。
これらの曲をオンエアしないというのはおそらくはクリアチャネルの一部の人間によって決定されリストが作られ傘下のラジオ局に通達されたのでしょうが、内部通達なので聴いてる側には、ある楽曲が放送できない状態になっているということが分からなかったということ(後でアップすしますが「イマジン」をニール・ヤングが歌うということがあったのである程度情報はもれていたのかもしれませんが)。今まで無かったものが現れると人はもちろん気づきますが、今まで普通にあったものが消えてしまうと案外気が付かなかったりします。だから、9.11の後ラジオを聴いていて「ジョニー・エンジェル」が流れなかったとしても、それが「放送できない」から流れていないとは知る由がない。これって怖いことだと思います。先に「ジョニー・エンジェル」の自粛の理由が分からないと書きましたが、実際には「ジョニー・エンジェル」が自粛されていることすら分からないわけですから、「自粛の理由は?」という疑問すら抱きようがないわけです。なんか、どこかの国の「特定なんちゃら法」みたいな話ですね。
最後に、クリアチャネルの出した自粛すべき楽曲のリストを載せておきます。
3 Doors Down"Duck and Run"
311"Down"
AC/DC"Dirty Deeds Done Dirt Cheap""Hells Bells""Highway to Hell""Safe in New York City""Shoot to Thrill""Shot Down in Flames""T.N.T."
The Ad Libs"The Boy from New York City"
Afro Celt Sound System"When You're Falling"
Alice in Chains"Down in a Hole""Rooster""Sea of Sorrow""Them Bones"
Alien Ant Farm"Smooth Criminal"
The Animals"We Gotta Get Out of This Place"
Louis Armstrong"What a Wonderful World"
The Bangles"Walk Like an Egyptian"
Barenaked Ladies"Falling for the First Time"
Fontella Bass"Rescue Me"
Beastie Boys"Sabotage""Sure Shot"
The Beatles"A Day in the Life""Lucy in the Sky with Diamonds""Ob-La-Di, Ob-La-Da""Ticket to Ride"
Pat Benatar"Hit Me with Your Best Shot""Love Is a Battlefield"
Black Sabbath"Sabbath Bloody Sabbath""War Pigs"
Blood, Sweat and Tears"And When I Die"
Blue Öyster Cult"Burnin' for You"
Boston"Smokin'"
The Crazy World of Arthur Brown"Fire"
Jackson Browne"Doctor My Eyes"
Buddy Holly and the Crickets"That'll Be the Day"
Bush"Speed Kills”
The Chi-Lites"Have You Seen Her"
The Dave Clark Five"Bits and Pieces"
Petula Clark"A Sign of the Times"
The Clash"Rock the Casbah"
Phil Collins"In the Air Tonight"
Sam Cooke"Wonderful World"
Creedence Clearwater Revival"Travelin' Band"
The Cult"Fire Woman"
Bobby Darin"Mack the Knife"
Skeeter Davis"The End of the World"
Neil Diamond"America"
Dio"Holy Diver"
The Doors"The End"
The Drifters"On Broadway"
Drowning Pool"Bodies"
Bob Dylan"Knockin' on Heaven's Door"
Everclear"Santa Monica"
Shelley Fabares"Johnny Angel"
Filter"Hey Man, Nice Shot"
Foo Fighters"Learn to Fly"
Fuel"Bad Day"
The Gap Band"You Dropped a Bomb on Me"
Godsmack"Bad Religion"
Green Day"Brain Stew"
Norman Greenbaum"Spirit in the Sky"
Guns N' Roses"Knockin' on Heaven's Door"
The Happenings"See You in September"
The Jimi Hendrix Experience"Hey Joe"
Herman's Hermits"Wonderful World"
The Hollies"He Ain't Heavy, He's My Brother"
Jan and Dean"Dead Man's Curve"
Billy Joel"Only the Good Die Young"
Elton John"Bennie and the Jets"
"Daniel""Rocket Man"
Judas Priest"Some Heads Are Gonna Roll"
Kansas"Dust in the Wind"
Carole King"I Feel the Earth Move"
Korn"Falling Away from Me"
Lenny Kravitz"Fly Away"
Led Zeppelin"Stairway to Heaven"
John Lennon"Imagine"
Jerry Lee Lewis"Great Balls of Fire"
Limp Bizkit"Break Stuff"
Local H"Bound for the Floor"
Los Bravos"Black Is Black"
Lynyrd Skynyrd"Tuesday's Gone"
Johnny Maestro & The Brooklyn Bridge"The Worst That Could Happen"
Martha and the Vandellas"Dancing in the Street""Nowhere to Run"
Dave Matthews Band"Crash into Me"
Paul McCartney & Wings"Live and Let Die"
Barry McGuire"Eve of Destruction"
Don McLean"American Pie"
Megadeth"Dread and the Fugitive Mind""Sweating Bullets"
John Mellencamp"Crumblin' Down""Paper in Fire"
Metallica"Enter Sandman""Fade to Black""Harvester of Sorrow""Seek & Destroy"
Steve Miller Band"Jet Airliner"
Alanis Morissette"Ironic"
Mudvayne"Death Blooms"
Ricky Nelson"Travelin' Man"
Nena"99 Luftballons"/"99 Red Balloons"
Nine Inch Nails"Head Like a Hole"
Oingo Boingo"Dead Man's Party"
Ozzy Osbourne"Suicide Solution"
Paper Lace"The Night Chicago Died"
John Parr"St. Elmo's Fire (Man in Motion)"
Peter and Gordon"I Go to Pieces""A World Without Love"
Peter, Paul and Mary"Blowin' in the Wind""Leaving on a Jet Plane"
Tom Petty"Free Fallin'"
Pink Floyd"Mother""Run Like Hell"
P.O.D."Boom"
Elvis Presley"(You're the) Devil in Disguise"
The Pretenders"My City Was Gone"
Queen"Another One Bites the Dust""Killer Queen"
Red Hot Chili Peppers"Aeroplane""Under the Bridge"
R.E.M."It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)"
The Rolling Stones"Ruby Tuesday"
Mitch Ryder & the Detroit Wheels"Devil with a Blue Dress On"
Saliva"Click Click Boom"
Santana"Evil Ways"
Savage Garden"Crash and Burn"
Simon & Garfunkel"Bridge over Troubled Water"
Frank Sinatra"New York, New York"
Slipknot"Left Behind""Wait and Bleed"
The Smashing Pumpkins"Bullet with Butterfly Wings"
Soundgarden"Black Hole Sun""Blow Up the Outside World""Fell on Black Days"
Bruce Springsteen”I'm Goin' Down""I'm on Fire""War"
Edwin Starr”War"
Steam"Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye"
Cat Stevens"Morning Has Broken""Peace Train"
Stone Temple Pilots"Big Bang Baby""Dead and Bloated"
Sugar Ray"Fly"
The Surfaris"Wipe Out"
System of a Down"Chop Suey!"
Talking Heads"Burning Down the House"
James Taylor"Fire and Rain"
Temple of the Dog"Say Hello 2 Heaven"
Third Eye Blind"Jumper"
The Three Degrees"When Will I See You Again"
Tool"Intolerance"
The Trammps"Disco Inferno"
U2"Sunday Bloody Sunday"
Van Halen"Jump""Dancing in the Street"
J. Frank Wilson and the Cavaliers"Last Kiss"
The Youngbloods"Get Together"
Zager and Evans"In the Year 2525"
The Zombies"She's Not There"
当時、日本でも放送された America: A Tribute to Heroesで ニールが「イマジン」を歌うのを見て‘放送禁止なのにあえて歌うってニールってすげえ‘と思っていましたが「放送禁止(自粛)」はラジオ局で、TV局の方は関係なかったってことなのか・・・。
PS.「あなたの目にはいるものは全てクリアチャネルから」という標語を聴くとジョージ・オウェルの「1984」のBIG BROTHERを思い出してしまいました、おお怖っ。
ぼくらはまるで汽車を待つ無法者ふたりだった

寄る年波というか、最近は中学校や高校時代に夢中になって聴いていた歌手が逝ってしまうことが本当に多く、いちいち追悼の文章を書くのはどうなんだろうなぁと思ったりもするのですが、ガイ・クラークは特別だしなぁ。
追悼として、5年ほど前に書いたガイについての記事を加筆修正して再掲載させていただきます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
レコード・コレクターズの連載「サンフランシスコ滞在記」でガイ・クラークが紹介されたことがあります。筆者であるカメラマンの渡辺真也氏いわく
”70年代になって登場したシンガー・ソング・ライターの中で、おそらく誰よりも寡黙だが、その分一番に信頼していい男が、ガイ・クラークだ。”
異議なし、まったくその通りだと思います。
僕がガイ・クラークという名前を初めて知ったのは高校1年だった75年に買ったジェリー・ジェフ・ウォーカーのアルバム『ライディン・ハイ』の中の一曲「ライク・ア・コート・フロム・コールド」によってでした。
だけど僕のそばには僕が選んだレディがいてくれる
人生を共にする寒さから守ってくれるコートのようなきみが
アルバムにはジェリー・ジェフによる短文の解説が添えられているのであるが、ガイ・クラークのこのラヴ・ソングにはこう書かれている。
バルバドスで落ち着いて安らかなハネムーンをスーザンとエンジョイしていると、ガイとスザンヌが飛んできて一緒な時間を過ごした。そしてガイは僕たちのためにパーフェクトなウェディング・ソングを歌ってくれた。
この曲も含めジェリー・ジェフの歌声に惚れた僕は遡ってアルバムを買っていきます。そして73年のアルバム『ヴィヴァ・テルリングア』を聴いた時にあぁいい曲だなぁと思ったのが「汽車を待つ無法者のように」という曲でした。
僕が「レッド・リバー・バレー」を弾くと
じいさんは台所で泣いていた
「神よどうして私が掘った油井はすべて枯れてしまうのか」
70年の人生を刻んだ指先を眺めつぶやく
僕とじいさんは友達だった
まるで汽車を待つ無法者ふたり
じいさんは流れ物の油田掘り
僕には世界を教えてくれる年老いた先生
酔っ払ってハンドルが握れない時僕に運転を教えてくれた
ウィンクして女の子と遊ぶための小銭をくれた
僕たちの毎日はまるで西部劇みたいだった
まるで汽車を待つ無法者ふたり
まるで汽車を待つ無法者ふたり
僕が世の中をよちよち歩きできるようになると
じいさんはあおがえるカフェという酒場に連れて行った
そこにはビール腹の年寄りとドミノがあった
僕がそこにいる間彼らは遊び続け
僕のことをじいさんの助手と呼んでいた
まるで汽車を待つ無法者ふたり
まるで汽車を待つ無法者ふたり
ある日僕が見上げると
じいさんは80に近づいていた
タバコの煙は彼のあごのシミとなり
僕にとってじいさんは ヒーローの一人
ビールを呑み「月と42」を演っていた
まるで汽車を待つ無法者ふたり
まるで汽車を待つ無法者ふたり
じいさんが逝く前の日 僕はじいさんに会いにいった
僕はすっかり大人になり じいさんは死にかけていた
僕たちは目を閉じあの日の台所を夢見た
そしてその古い歌にもう一つの歌詞をつけて歌った
”ほら見ろ、ジャック、親不孝ものがやってくるぞ”
ぼくらはまるで汽車を待つ無法者ふたり
まるで汽車を待つ無法者ふたり
作者のクレジットをみるとガイ・クラークの名前。こうなると俄然ガイ・クラークのことが気になったのですが今みたいにヤフーで検索して、YOUTUBEで音源聴いてなんていう時代ではないですからね、スティーブ・ジョブズがガレージで試行錯誤している時代、頼れるのはレコード店だけ。しかしながら、レコード店でエサ箱を漁ってもどこにもありませんでした。
万事休すかと思ったときミュージック・マガジンに”ガイ・クラークのデビュー・アルバム登場!"の広告が載ります。なんと、まだデビューしてなかったんですね。早速予約をして発売日には手に入れ大急ぎ(といっても1時間半くらいはかかるのですが)で家に帰ってターン・テーブルに。

ジャケからそのアルバムの中味というのはだいたい想像がつく場合が多いのですがこのガイ・クラークの1stアルバム『オールドNo.1』はジャケットそのままに、洗いざらしのデニム・シャツのように暖かく柔らかで肌にフィットするような、飾りの無い歌声に満ち溢れたアルバムでした。
ジェリー・ジェフが取り上げた2曲の本人バージョンは勿論、一曲目の「リタ・バルー」から最後の「レット・ヒム・ロール」まで、すべての曲が素晴らしく何度も何度もターンテーブルに乗っけたものでした。
くだんのレココレの記事では「ザット・オールド・タイム・フィーリング」の歌詞が紹介されていました。
ザット・オールド・タイム・フィーリングが
足をしのばせてホールに入ってくる
壁にぴたり身を寄せている
冬のさなかの猫のように
ザット・オールド・タイム・フィーリングは
通りに出てよろよろしている
足に絡みつく新聞紙を蹴散らす
年老いたセールスマンのように
そしてザット・オールド・タイム・フィーリングは
街の一郭を廻りだす
子供達がいなくなって
時計をした老婆のように
渡辺真也さんはザット・オールド・タイム・フィーリングを訳すとすれば「誰でもが思い出す感覚」としています。そして、いわゆるノスタルジックな感覚とはちょっと違うのではないかと書いています。
自分の生まれる前であったりまだ小さかった頃の洋楽なんかを聴いていると、時々”あぁ懐かしい”と思うことがあります。聴いたこともない曲なのになぜ懐かしいのだろうと不思議に思います。自分が長年聴いてきた音楽が頭の中にどんどん溜まっていくことよって、帰納的に自分が生まれる前の音楽にまで擬似の音楽体験が生じてしまい、結果的に懐かしく思うのだろうか?
なんていう風に思ったこともありましたが、それは”懐かしさ”ではなく、その歌が渡辺さんのいう「ザット・オールド・タイム・フィーリング」を含んだものだからなのかも知れません。人種や言語を越えて人間の遺伝子の中に刻み込まれた感覚、例えば動物の赤ちゃんを見たら可愛いと思うような、そんな感覚がある種の音楽の中にはある、そんな気がします。
そしてガイ・クラークの歌もそんなひとつです。
75年にガイ・クラークはデビューするのですが、35歳という遅まきのデビューでした。デビューまで時間がかかったおかげというべきか、1stアルバムは素晴らしい曲ぞろいでジェリージェフの他にも多くの歌手に取り上げられた曲も収録されていました。
そんな素晴らしいアルバムでしたが残念ながら日本ではたいしたヒットもしなかったのか、ガイのレコードはこのアルバムと次の『テキサス・クッキン』あたりが出たくらいで国内盤の発売は途絶えてしまったように思います。それはガイの盟友ジェリー・ジェフも同じで国内盤がでていたのは70年代後半くらいまでです。アメリカではこの二人のアルバムは継続して発売され続けているのになんで?と思います。
ひとつの要因としては、この二人の音楽がカントリーにカテゴライズされてしまうからだと思います。70年代に日本でも人気のあったSSW~ウェスト・コーストという音楽ジャンルの中には今であればカントリーにカテゴライズされてしまうような音楽がけっこうありました。例えばイーグルスやPOCOなんてのも、今デビューしていたらカントリーにカテゴライズされてしまっていた気がしますが、70年代当時は”爽やかなハーモニーを持ったウェストコースト・ミュージック”でした。
同じ音楽であっても、聴くほうの考えるカテゴライズが変わることで聴き方が変わってしまうというのはなんとも不可解な気がするのですが、日本人(だけじゃないか)ってけっこうこの「カテゴライズ」に左右される国民のような気がします。
SSW~ウェスト・コーストという流れがAORへとシフトし、洗練されていくなか、日本の音楽ファンの心の中にカントリーっぽいものはいなたく垢抜けないものだとして敬遠されていったのか。AORだけどルックスが南部の長髪のおっさんというポール・ディヴィスのジャケを、そのままじゃ日本のファンに敬遠されるだろうとFM雑誌についてくるカセットのインデックスのようなおしゃれな写真に差し替えて発売するなんてこともありましたが、ある意味歌の良し悪しよりイメージに左右されるようになっていく。
まぁそういったようなことでジェリー・ジェフやガイ・クラークのような田舎くさいオッサンは日本では忘れ去られてしまったのは時代の流れだったのかもしれませんが僕にはとても残念に思えます。前にも書いたけどジェリー・ジェフ=Mrボージャングルじゃないんです。
なんか酔っ払いのグチみたいになってきましたが、最後にこれまたガイ・クラークの代表曲「LAフリーウェイ」を本人とジェリー・ジェフのライヴ・バージョンで聞き比べてみてください。
君のお皿を箱詰し
希望をすべてメモして
大家にあばよと言おう
アン畜生にはいつもうんざりだった
新聞やヴァニラウェハースのカビだらけの箱を放り出し
コンクリートの街におさらば
埃だらけの裏通りが僕を待っている
もし僕が殺されたり捕まったりせず
このLAフリーウェイから抜け出せたなら
煙のような雲の下 道を下っていく
お金じゃ手に入らない場所へ
年老いたやせっぽっちのデニス
ここはあんたのための場所だ
心配してくれるたった一人の人
壊れかけたベースの音が聞こえてくる
優しく静かに あなたからの贈り物みたいに
僕のためにもう一度弾いてくれないかい
今の僕たちのすべてを込めて
あんたの言葉を僕は信じる
お願いだから 弾き続けておくれ
もし僕が殺されたり捕まったりせず
このLAフリーウェイから抜け出せたなら
煙のような雲の下 道を下っていく
お金じゃ手に入らない場所へ
君は郵便受けにピンクのカードを入れ
ドアをロックし鍵を残す
あいつらはそれをきっと見つける
僕たちが忘れている何かがあるはずだ
ああスザンナ 泣かないでくれ
愛は手作りの贈り物みたいなもの
信じられる何かがきっと見つかるさ
だから そろそろ出かけよう
もし僕が殺されたり捕まったりせず
このLAフリーウェイから抜け出せたなら
煙のような雲の下 道を下っていく
お金じゃ手に入らない場所へ
歌詞がしみるなぁ。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ガイの一番最近のアルバムは2013年の『 My Favorite Picture оf You』となtります。

ガイが手に持っている「一番好きな君の写真」は40年連れ添いガンで亡くなった奥さんスザンヌの写真です。でもその写真は笑顔の写真ではなく腕を組みこちらを怒った顔でにらむ顔、何故これが一番好きな写真?
何でもこの30年ほど前にタウン・ヴァン・ザントと飲み明かしベロンベロンになって帰ったガイを待ち受けていたスザンヌが今まさにカミナリを落とそうとしているところを一緒にいた友達がポラロイドで撮ったものらしいのですが、ガイにとって馬鹿なことをした自分を本当に怒ってくれるのはスザンヌだけでありかけがえのない人という思いがあったのだろう。
”ほら見ろ、ガイ、親不孝ものがやってくるぞ”
ガイ爺さんよ、天国でスザンヌ婆さんとよろしくやってくれ。RIP。
If You Can Believe Your Eyes And Ears
California Dreaming
50年前、1966年5月のこの週に全米4位のデビュー・ヒット「夢のカリフォルニア」と全米1位の第2弾シングル「マンデイ・マンデイ」を収録したママス&パパスの1stアルバム『イフ・ユー・キャン・ビリーヴ・ユア・アイズ・アンド・イヤーズ If You Can Believe Your Eyes And Ears』が全米1位を獲得しています。
「あなたの目と耳が信じられるならば」これを聴きなさいという意味だと思われるアルバムのタイトルからしてママス&パパスの自信のほどがうかがえる一枚です。ただ、シングルの大ヒット2連発で自分たちの実力と人気を過信しすぎたのか、このアルバムは発売後すぐに店頭から回収されるという憂き目をみます。
その原因はジャケットの写真にありました。
バスルームのバス・タブの中に4人が体を寄せ合いというか3人がバスタブの中にしゃがみ込みその膝の上にミッシェル・フィリップスが乗っかっています。そしてバス・タブの横には便器が写っています。2016年の目でみれば特にどうってことないように思える写真なのですが、なにせ50年前のことですから、まずは便器が問題になります。大勢の人々の目に触れるLPジャケットに便器のような「下品」なものが写っているのはけしからんというわけです。
上にも書いたアルバム・タイトルを考えれば、グループ・サイドの思いとしては品のないジャケットだけど中身は保証付きだから信じてねということであえてこのような「下品」なジャケットにしてたと想像できるので、この回収は納得の行かないものだったのじゃないでしょうか。
それもあって、十全を期すのであればジャケットの写真をまるごと変えてしまうのが良いのでしょうが、グループの抵抗があったのか「夢のカリフォルニア」「マンデイ・マンデイ」そしてビートルズ・カバーの「アイ・コール・ユア・ネイム」というみんなが知っている収録曲を記したバナーを上から印刷するというやり方で便器の部分だけを隠して再度出荷されています。
確かに便座の部分は隠れているのですが水洗用の水道管は隠れず写っていて、そこに何があるのかは隠れていても誰もが分かる写真で果たしてこれで「修正」といっていいのか疑問が残る、臭いものにフタをしたのが一目瞭然のジャケットといえるんじゃないでしょうか。このへんママス・アンド・パパスなりの意地だったんじゃないでしょうか。全米ヒットがあったとは言え新人バンドがデビュー・アルバムでそこまで意地を張れたのは発売元がメジャーではなくロックを理解するルー・アドラー社長のダンヒル・レコードであったというのもあるかも知れません。
I CALL YOUR NAME
新しいジャケットにして再発売されたアルバムは文頭でも書いたように見事に全米NO.1を獲得することになります。めでたしめでたし。
なのですが、このアルバムにはもう一種類のジャケットがあります。それが下の画像です。
見てもらえばお分かりのように便器だけでなく、バスタブの部分もすべて黒い枠で隠されていて、バスルームで撮影したことが全く分からないものになっています。何故ここまで隠したのかを想像すると、男女四人がひとつのバスタブに入っていることがオージーを思わせふしだらであるみたいなことではないかと思われます。おまけにミッシェルの態度はSMの女王様なんてことも妄想させます、ってそんなこと思う方がふしだらなんだと思いますけど。
ダンヒル・レコードのファンのサイトの記述を見るとこのジャケットは一般流通ではなく通販用のジャケだったんじゃないかみたいなことが書かれています。店頭で直にジャケット写真を見て納得して買うのと違い、通販で到着後にジャケを見て「なんじゃこりゃ」となるのを恐れてのことなのでしょうか。とにかく見た目は「健全」なジャケットになっています。
画像は帯付きの日本盤なのですが、日本ではこの「健全」ジャケットで発売されていたんです
ね。
Prodigal Son - The Rolling Stones
ところでジャケットにトイレの写真と言えばローリング・ストーンズの『ベガーズ・バンケット』の事件を思いだす方もたくさんいらっしゃるでしょうね。
疲れてきたのでウィキの解説をそのまま引用させていただきます。
現在の本作のジャケットとして採用されている「汚れた便所の落書き」の写真は、映像監督のバリー・フェスティンとニューヨークのデザイナー、トム・ウィルクスによってデザインされた。だがデッカ・レコードは、バンドから提示されたこのジャケットデザインを拒否した。バンドはこれに抵抗し、茶色の紙袋に入れて「Unfit for Children(子供達には不向き)」というラベルを貼って出すという代案を提示するが、これも却下される。アメリカのディストリビューターであるロンドン・レコードもデッカの決定を支持し、バンドの不満は高まった。ストーンズはその報復としてデッカとロンドンの態度が軟化するまでアルバムを提供しなかった。しかしながら11月までにストーンズは招待状を真似た単純なジャケットでリリースすることを渋々認め、屈服することとなった。
金色で縁取られた薄クリーム色のジャケットには「Rolling Stones Begger's Banquet」と真ん中に、左下隅に「R.S.V.P.」('Reponse s'il vous plait, ご返事願います、の略)と黒字の筆記体で記入された。見開きジャケットの内側には、タイトルどおりこじき(Beggar)風の格好をしたメンバー5人が宴会(Banquet)を開いている情景が写されている。ビートルズが二週間前に『ホワイト・アルバム』をリリースしていたことで、幾人かの評論家はストーンズが再びビートルズを今度は単純なジャケットで真似たとして非難した。1984年のリマスター盤でようやく当初の写真が採用されるようになった。この一連の論争についてジャガーは「全くの時間の無駄だった」と振り返っている。
『ベガーズ』のジャケットについては中学生の時に元々は便所のジャケットだったということを知りますが、ジャケの写真とかも見ることができずモヤモヤしていて高校くらいで実際の便所ジャケを見ることになります。ストーンズのイメージからとか、ロック的なのやっぱコッチでしょと便所ジャケの方が絶対いいと思っていたのですが、CDで発売される際に招待状ジャケから便所ジャケがオフィシャルなジャケにされた頃からだんだんコレはやっぱり招待状ジャケの方が良かったなぁと思うようになってきて今に至ります。根がひねくれ者であることもありますが、当初ストーンズが便所ジャケでどんなタイトルにするつもりだったのか、『ベガーズ』のままだったのかは知りませんが、少なくとも『ベガーズ・バンケット』(乞食の宴会)っていうアルバム・タイトルである限りは招待状ジャケの方が相応しいですよね。皮肉も効いてるしね。
Beggars Banquet/Abkco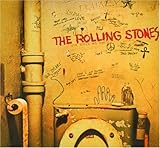
¥1,650
Amazon.co.jp
夢のカリフォルニア/ユニバーサル ミュージック
¥1,851
Amazon.co.jp
日本人の心のふるさと。日本の伝統音楽。それが演歌
本日の朝日新聞のオビニオン&フォーラム「耕論」のテーマは「演歌は日本の心、か ~女心、浪花節、せつない旋律、染みいる詞。忍ぶ恋、未練の涙、恨み節、帰らない時代。日本人の心のふるさと。日本の伝統音楽。それが演歌ー。演歌を巡る言説を考える~」というもの。
なぜ、今このテーマなのかと言うと、三人の論者の一人である阪大准教授の輪島裕介さんの文中にある<この3月、超党派の国会議員連盟が発足、政治と演歌が接近しています。そこでは演歌が漠然と「伝統的なもの」と捉えられている>という胡散臭い状況に対する「?」なのは間違いないだろう。
そして続けて輪島さんが書いているようにこの動きと言うのは<右肩上がりだった昭和を理想化し、ノスタルジーを新たに記憶しなおして「伝統」と呼ぼうとする>もので。これは安倍サンが「美しい日本を取り戻そう」という時、その「日本人の心」を歌謡として具現化しているのが演歌という「伝統」なので、今こそその「伝統」を盛り立てていこうではないかというものであるように僕には思える。
本当にそうなのか?演歌は日本の伝統なのか?
そもそも現在僕たちがジャンルとして認識する「演歌」が生まれたのはいつなのか。
「演歌」という言葉が生まれたのは明治時代とされています。となれば少なくとも100年以上の「伝統」はあることにはなりますが、そうだとしても神武天皇から2700年近い歴史のあることを思えば軽い「伝統」といえるかも知れません。それどころか、元々は自由民権運動で演説会を規制された活動家たちが歌の会と称して集会を開いた時の演説歌が略されて「演歌」と呼ばれ出したもので現在の「酒涙女」とは違い痛烈な社会風刺を含んだものだったとのこと。
では一体いつ演歌は生まれたのか?
輪島さんは「演歌と言うジャンルの呼称が生まれたのは1960年代後半」だといいます。なぜ60年代後半にジャンルとして確立されたのかについては評論家のスージー鈴木さんは、ヨナ抜きという西洋音階の日本的解釈に明治以降慣れ親しんできた日本人に、ビートルズの世界的ヒットを契機に日本でも7音階をフルに使うGSが登場し日本の音楽業界を席巻した、そのときに「洋風」のGSに対抗するための論理として、復古派が持ちだしたのが「演歌は日本人の心」という説であったといいます。
「ド演歌」が「日本人の心」という論理はやはり60年代後半に生まれたということのようです。
(ぴんからトリオ時代の映像がないのは何故?昭和47年(1972年)のヒットで、この映像自体は昭和55年(1980年)の放送からのようなのですが、曲前のコントで「こんなけなげな女性はいなくなりましたねー」と、歌詞で歌われた世界観がすでにノスタルジーであることを示しちゃってますね)
つまり、演歌の「伝統」とか言ってもたかだか50年もない、もっと言えば90年代以降の演歌のシェアは数パーセントに衰退してとてもメインストリームとは言えない状態が続いていますので、演歌が日本の歌謡界の表舞台にいたのは60年代から80年代前半まで高々四半世紀くらいのものです。
そんなものを、はたして「日本の心」としてなぜ政治が後押ししようとするのか?
批評家の大澤聡さんはこう警鐘を鳴らします。
「悪しき伝統」という場合、大半はシステムの話ですね。かたや、「良き伝統」は文化の話。昔ながらの制度を守ろうと言うと反発を生みますが、文化を守ろうと言う分にはすんなり通る。
だから文化は危機の時代にこそ利用されるのです。
輪島さんもこう締めます。
演歌を伝統だというのは、音楽における歴史の読み替えです。読み替えによる新しいスタイルの創造そのものは否定されるべきではありません。ただ、70年代に(註:寺山修司のように)体制への反発として起きたのとは違い、今の政治家や業界関係者たちは体制に寄り添う形で読み替えようとしています。どのような文化的表現を、どのように読み替えるのか、その文脈こそ考えるべきでしょう。
歌謡曲ファンがよく引き合いに出す言葉に「歌は世につれ、世は歌につれ」というのがあります。歌にはその時代の大衆の心が投影されるということかなと思います。本来世につれていない「演歌」が恣意的に「つれる」世の中になったとしたら、なんとも恐ろしいことと思います。
超党派の国会議員連のおじ様たちも、大衆の前で「演説歌」を歌うくらいの気概がある人たちならばよいうのですが、せいぜいがパーティの2次会のカラオケで「演歌」をうなって「先生おじょうず」といわれて満足しているそんな人たちばかりのような気がするのは私だけ・・・。
註:貼り付けた動画は本文と直截的な関係はございません。